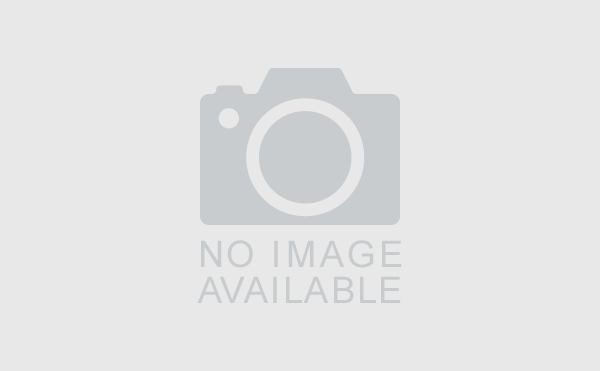令和5年8月3日 厚生委員会
2023年8月3日

子ども政策部報告、本件を議題といたします。

よろしくお願いします。まず、資料1、学童の件なんですけども、今回、学童の指定管理者の公募についてという点で、三鷹市内の学童については、地域性、エリア性、運営方法が多少異なったとしても、子どもにとって変わらない丁寧な運営をしていただいていると思います。3パターンぐらいやり方、方法がある中で、先日、井口の学童ですとか六小の学童ですとかに行ってみたところ、やはり社会福祉協議会が運営している学童と、あと保育サービスさんが運営している学童の方法では、同じように子どもたちにとってというところではあるんですけど、得意、不得意のところがあるなというのを感じております。
例えば、社会福祉協議会さんのほうであれば、保護者に向けたお便りとかいうのを今までずっと手書きだったり、それぞれ独自で作られていたのを、いろいろと社会福祉協議会さんの中でも勉強会などをしていて、一律で、どうしたら保護者にとって分かりやすいお便りにしていくかなど、すごく勉強をしているなというのを感じているんですけども。保育サービスさんは、やはり企業さんなので、その辺はアプリを使ったりですとか、運営においてすごくスマートにされているなという印象があるんですが、今回の公募によって、現在、社会福祉協議会さんから、例えば保育サービスさんに代わることとかっていうこともあるんでしょうか。

まだ公募の公表もしておりませんし、どこが申し込まれるかも分からないので、何とも分からないんですが、もちろん社会福祉協議会さんが継続されるケースもあるでしょうし、新しい、保育サービスさんも含めて、それ以外の業者さんが入る可能性もあるのかなと、今そういう考えでおります。

ありがとうございます。本当にどこの業者さんも、子どもにとってというところ、保護者にとってどうしたらいいかと考えていただいていると思うんですけども、もし保育サービスさんのほうに代わったりですとか、変化があったときの丁寧な対応と、あと各業者さんの勉強会であったり共有というのをもう少し深めていけると、管轄というか立場が違うのでなかなか難しいかもしれないんですけど、三鷹市内の学童の一律な共有というのがあると、もっともっと三鷹の学童の安全性でしたり、いろんな面でもっと高めていけるのではないかなと思っておりますが、何か今、勉強会ですとか共有などはされていますか。

やはり複数の事業者さんが入ることで、いろいろなやり方というのが出てくるので、そこについては、現在も学童保育所運営事業者の皆さんに集まっていただいて連絡会を定期的に開いております。それぞれの取組状況とかを御紹介したりして、情報の共有を図るとともに、三鷹市の学童保育所であることは変わりありませんので、どこでも一定のサービスが受けられるようにということで、そこは事業者間でも情報共有をしてもらうような取組を行っているところです。

ありがとうございます。あと、障がい児がやはり学童でも増えているというのを伺っておりまして、そのときの対応というのを、施設的にその子を落ち着かせるためのスペースがあったりですとか、1人がついてちゃんと対応できるときはいいんだけれども、やっぱり大勢を見ているときにはどうしてもそういった方々に対してのフォローというのがし切れないというような──御要望も聞いております。
その辺も、明らかにやはりそういったお子さんたちは増えておりますので、情報共有でしたり、指導の中で障がい児に対しての学童での過ごし方ですとか、そういったことも今後、どこの業者さんがなっても同じように対応できるようにしていただけたらいいかなと思っております。ありがとうございます。
次、資料2ですね。すみません、アンケート調査についてなんですけども、これ5年前にも調査をされたということなんですが、どれくらいの回収率があったかとかって分かりますでしょうか。

5年前の回収率ですが、まず子育てに関するニーズ調査のほうですが、未就学児童の保護者、まる1になりますか、郵送で実施しておりますが、ここは58%という回収率になっております。小学校2年生の保護者、小学校4年生の保護者、こちらはやはり学校さんを介して行ったということで、いずれも90%以上の回収率になっております。
また、生活実態調査のほうですが、小学生、中学生自身の調査につきましては、これは学校の時間を使ってやらせていただいたということで、100%の回答となっております。同じく、小学校5年生、中学校2年生の保護者の方についても、学校を通しておりますので90%以上となっています。児童扶養手当の受給世帯に関しましては、こちらは郵送ですが、ここはちょっと低くて38.8%という数字が前回の数字となっております。
以上です。

ありがとうございます。また、今回、令和6年度の改定に向けてのアンケート、ニーズ調査ということだと思うんですけど、この生活実態調査以外に、何か市民向けに調査や──ニーズなどは考えられているんでしょうか。

今の御質問、端的に答えると、現時点ではこの調査以外のものというのは予定してございませんけれども、恐らく御質問の趣旨というか御指摘は、やはりこういった調査とかデータに基づいてしっかり現状把握した上で、様々な市のサービスであるとか事業であるとか施策を考えるべきじゃないかというような御趣旨かなと思いますし、私どももその辺については非常に重要だというふうに思っています。
ただ、調査をやるとなると、いろいろ経費の問題でありますとか、あるいは手間の問題とかいろいろあるんですが、ただ昨今そういうウェブを使うとか、いろんな手法もありますし、その都度、例えばサービスの利用者なりを対象としたある種限定をした満足度調査みたいなものというのは、非常に確認していく必要があると思いますので、現時点で何か予定しているかということでいうと、なかなかないんですけれども、その都度いろんな事業、あるいはサービスを提供しているので、そういったものに対する利用者の方のお声というのは常に聞いていきたいと、このように考えています。

ありがとうございます。まさにこことちょっとつながるんですけども、子育て支援ニーズ調査の1番の国から示される質問項目を基に検討予定というのは、何か国から毎回そういったような、こういうのを調査をしてくださいというようなことがあるんでしょうか。

これまでも5年ごとに、国からそういった調査の方向性ですとか、こういう項目を入れてほしいとか、モデルの質問ですとか、そういうものが示されてまいりました。ですので、基本的にはここの部分についてはそれをベースに実施してきたというところで、今回もその予定でございますが、現在もこども家庭庁の創設なども相まって、なかなかちょっとそこの情報がまだ降りてきてないというところでございます。

ありがとうございます。1点思ったのが、やはり未就学児童の保護者の調査に関しては、さっきのアンケート結果、58%、38.8%ということで、回収率においても少し低いのかなというのを感じたところではあるんですが、未就学児はコロナ禍でなかなか外に出られなかったりですとか、やはり小学校ですとか、そういった周りのコミュニティ関係というのがなかなかつくれない状況の中で、特にこの未就学児は、もちろん国として考えられることもあると思うんですが、三鷹市独自の健診ですとか、そういったところの子育て支援のニーズというのは、どちらかというと保健サービスのほうにおいて、いろいろ求められるところも多いのかなと。
例えば、保護者の産後の体の状況ですとか、子どもの発達の状況ですとか、そういったところで支援をしていってほしいというような、そういったニーズも求められていくのかなという点では、三鷹市はウェルカムベビープロジェクトですとか、三鷹市独自の政策というのがかなり充実しているので、そういった点で国から示される質問もあるかとは思うんですが、三鷹市独自の今の未就学児に対しての支援ですとか施策についてのニーズ調査というのもしっかりしていただけると、コロナ禍で変化した──未就学児の方たちにとって、よりよい支援ということができていくかと思いますので。
そうですね、どちらかというと未就学児においては保健サービスの部分ですとか、そういったところが一番注目していくところになるのではないかなと思いますが、今まで、そういった保健サービスの部分とかというのを踏まえて、調査などはしていたことはありますでしょうか。

保健サービスのところの調査というのは今ちょっと確認できないところですが、今おっしゃられたとおり、確かに国のほうからベースとなる部分が示される予定でありますが、あくまでもベースですので、市独自でこういうところを加えたいということは可能だと思っておりますので、今特に健康保健サービスのところ、この辺についても加えられるかどうか、検討していきたいと思います。

ありがとうございます。まさにこの子育てガイドが未就学児についての様々なサービスの部分になると思うので、この辺のところで、例えばどういった補助に関したり、ポイントに関したり、あとは児童手当の部分に関したりというところは、三鷹で初めて出産をした方たちというのは、まずこのガイドをもらって、まず最初に保健センターのほうに行ってというところなので、若干子ども政策部の手前のところで健康福祉部との関わり合いが深くなっているのかなというところで、横の連携という意味でもこの子育て支援ニーズ調査のほうに入れていただけるといいかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。