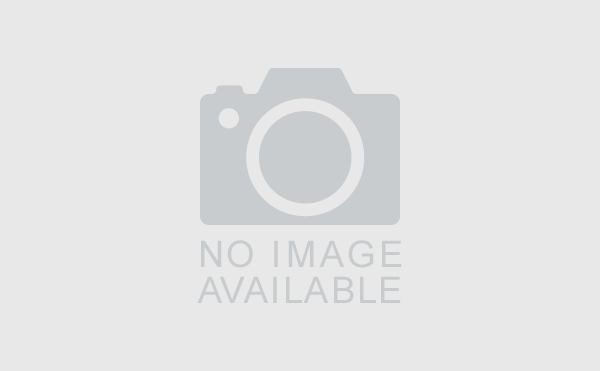令和5年6月21日 厚生委員会
2023年6月21日

議案第31号 三鷹市北野ハピネスセンター条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。

よろしくお願いします。先ほど石井委員のほうからいろいろと質疑がありましたので、私、1点だけなんですけども、通所ができなくて巡回入浴サービスが受けられない方というふうに書いてあるんですけど、送迎サービスがなしということで、これを受ける方というのは、御家族の方とか、そういった方がハピネスセンターまで連れてこられるということでしょうか。

立仙由紀子さん
送迎については、課題というふうに認識はしております。今おっしゃられたように、例えば御家族の方による送迎ですとか、あるいはハンディキャブやリフト付タクシーなどを利用して、入浴にハピネスまでいらしていただくといったことも想定しております。

ありがとうございます。
以上です。

市民部報告、本件を議題といたします。

国民健康保険における出産育児一時金を50万円に引き上げたということで、これは今までどおりの手続とは──手続に関しては変化はないでしょうか。

黒崎 晶さん
手続に関しては変更ございません。基本的に出産の際の出産費用のお支払いにつきましては、かつては全額御負担いただいて、健康保険組合や国民健康保険からお金を支給するという形でしたけれども、昨今は事前に医療機関のほうから御申請いただきまして、差額分だけお支払いいただく、要するに医療に関して御負担が、1回でお支払いいただく負担が大きいものですから、差額分をお支払いいただくという形になっております。その際、引き上げることに伴いまして、その出産された方の負担が減るような形で国として方策を示しまして、これが最終的に出産が増える方策の1つというふうに考えておりますので、今後これに関しては国の動向を注視してまいりたいと思います。特段、手続の変更はございません。
以上です。

ありがとうございます。産後、御主人だったり、パパだったり、あとやはり産後はなかなか手続に関して大変だという声をたくさん聞いておりますので、手続も今後簡素化していくことをお願いできればと思います。ありがとうございます。

生活環境部報告、本件を議題といたします。

よろしくお願いします。地域コミュニティ向けICT支援事業(Zoom講座)について内容及び手法等を見直していきますということなんですけども、私もこの講座を受けたことがあるんですが、やはり──施政方針の、すいません、65ページですね。地域コミュニティにおけるICT支援事業の拡充というところなんですが、ICT支援事業については、やはり高齢者の方はすごくハードルが高く思われている方が多いと思うんですけども、こういった方たちに、今後やはり住協でしたり、町会だったり、自治会というのは、ICTをどうしても活用していかなければいけなくはなってくると思うので、ハードルが高いと思われる方々にどのようにこのデジタル技術というのを訴求していくのかというのをどう考えているのか、教えてください。

垣花 満さん
高齢者の皆さんへのデジタル技術の活用の普及というか、そういった観点での御質問というふうに捉えさせていただきました。非常に難しい問題かなというふうに思っております。ただ、少しずつやはり進めていく必要があって、この基本方針の中で捉え直すとすると、要は、いわゆる市民活動とか町会活動とか住協活動のデジタル化、もしくはデジタル化によるより幅広い方たちの利用とか交流とか、そういった形になるかと思うんですが、いわゆるデジタルデバイドの問題については個々に対応していくしかないかなという部分がございまして、令和5年度からデジタル相談サロンという形で、個別の──特に高齢者の方、スマホにやっぱ興味があって、パソコンでZoom講座しているときとスマホでZoom講座しているときと、やっている内容は同じなんですけど、興味の持ち方がやっぱりちょっとスマホのときのほうが強い関心を持たれるという傾向も見てきていますので、今回からスマホの基本操作を中心としたデジタル相談サロンというのを7つのコミセンで、数は最初少ないんですけれども、展開しようかと思っております。また、市内では様々な団体が高齢者向けの講座なんかも開催しておりますので、そういったところとの連携も将来的にはにらんでいく必要があるかなと考えているところで、まずは最初の一歩、スマホでデビューしていただきたいといったところで考えているところです。
以上です。

ありがとうございます。やはり三、四十代と70代、80代の、この住協だったり、町会だったりという中での溝というのが、デジタルのところの部分が大きいのかなと感じておりますので、本当に皆さんで協力し合いながらだと思うんですが、ぜひこの高齢者向けのデジタルというところに力を入れていただけるといいかなと思いました。
次に、やはりこのコミュニティ、本当に三鷹は長い歴史のあるこのコミュニティ、つながりの支援ということでしていただいたかと思うんですが、今後は支援型、テーマ型、地域型ということで変化していくということがあるんですが、ここもやはり高齢者の変化というのが一番の課題かなと思っておりまして、先ほど防災のNPOでしたり、そういった形でテーマ型に変化していくというふうにあったんですけども、住協でしたり、町会というところで、高齢者の感覚の変化といいますか、地域で活動していくことが自分の生きがいになっているような方たちがたくさんいらっしゃると思うんですけど、この方たちに、支援型、テーマ型、地域型に変化していくということで──時間はかかっていくのかなと思うんですが、時間をかけて少しずつ今後のコミュニティの形を変えていくというようなイメージでいらっしゃいますでしょうか。

これ、形を変えていくのは物すごく時間かかると思います。やはり、いろいろなパラダイムシフトといいますか、大きな考え方を変革していくには時間はかかりますし、常に情報発信をしていく必要があるのかなというふうに考えているところですが、ある程度の時間の中で一定の理解を得ながら進めていきたいなというふうに考えているところです。

ありがとうございます。恐らくここ数年でなくなってしまうような町会もたくさんあるかと思っているので、その辺にちょっと丁寧な対応をしつつ、時間をかけて、今後、本当にこれまでの三鷹のコミュニティという形から変えていくというふうにしていかなければいけないのかなと思っております。
まちづくり協議会もすごく活性化している中で、これが三鷹市基本構想に関わってくると思うんですけども、やはりこの新しい方たちをこの基本構想のまちづくり協議会だけで終わらせずに、地域にもっと入り込んでもらえるような、今後、このまちづくり協議会をきっかけに若い世代がこの三鷹のコミュニティに関わっていっていただけるような、そういった流れをつくっていただけるといいかなと思うんですが、いかがでしょうか。

マチコエの活動に関しては、私の口からなかなかちょっとお答えができませんが、私どものほうの立場から考えたときに、例えば住民協議会や協働センターといったところの活動の中でぜひ一緒にやっていきたいという、もしくはいろんな意見を交換したいという声は出ておりますので、直接マチコエの活動についてはちょっとお答えできませんけれども、そういったお答えはできるので、こういった形でよろしいでしょうか。

川鍋章人さん
若干補足させていただきますと、衰退していく町会などに対する人の流れみたいな活動については、学校3部制などもあるんですけども、あらゆる──学校ですとか、そういったところを捉えて、そういう人の流れができていったらいいなというふうに思っているところでございまして、それで人が増えていくというような、そういうコミュニティが形成されているといいと思っているところでございます。
以上でございます。

ありがとうございます。学校でしたり、そのほか子育て世帯がどういうふうに地域に関わっていくかというのはすごく重要な課題だと思うんですが、現状、本当になかなか、町会ですとか、住民協議会、そういったところに子育て世帯が入っていくということがしづらい状況ではあるので、本当に、マチコエですとか、そういったことで関わった方たちが地域にもっと根差していけるような、そういったコミュニティづくりをしていっていただけたらなと思っております。ありがとうございます。

健康福祉部報告、本件を議題といたします。

よろしくお願いします。先ほどの子育て応援ギフトの件なんですけども、こちら、多分東京都の出産・子育て応援事業ギフトという形に変わられたかと思うんですけど、この利用率的なところはどのような状況でしょうか。

小島美保
利用率のところですけども、まだ始めたばかりでして状況につきましては把握ができておりませんが、使っていらっしゃらない方については連絡が来る形になっていまして、その方にまた再アプローチができるような形にはなっていますので、もうしばらくしてくると実態が出てくるかなというふうに思います。

ありがとうございます。以前はこども商品券で対応されていたかと思うんですけども、物でもらっている、商品券をもらっていると、これ使わないといけないなという意識があると思うんですけど、なかなか、QRコードを読み込むというと、忙しい子育ての中で──5万円、10万円相当をもらえるような形なので、お得なので、忘れる方はいらっしゃらないかもしれないんですけども、忙しい子育ての中でのこういった給付なので、丁寧に説明していただけると、より活用しやすいかなと思います。ありがとうございます。

項目イ(井口特設グラウンドへの市内病院の移転誘致について)に対する市側の説

これから事業者選定委員会ですとか、いろいろ決まっていくと思うんですけど、スケジュールを見ると、10月に公募要項の公表というふうに入っていまして、このスケジュール感で、選定委員だったり、公募要項を考えたり、そのスケジュール感で大丈夫とみなして、このような形だとは思うんですけど、スケジュール感は問題ないでしょうか。

池田啓起さん
スケジュールとしましては、現在、選定委員会が設置されないと検討できないということではなくて、もう既に我々の中では作業は進めております。その内容について選定委員会の先生方に内容確認をしていただいたりとか、そこでアドバイス、また方向性を指示していただいたりとか、そういう確認作業を、この公表の前には確定をしていきたいなというふうに思っています。また、こうした議会のほうにも御説明、御報告のタイミングであるとか、そういったことを踏まえて、現時点ではこのスケジュールに基づいて取組を進めているところであります。

分かりました。ありがとうございます。

子ども政策部報告、本件を議題といたします。

よろしくお願いいたします。本当に私、この三鷹市の子ども政策、この数年すごく一気にサービスが充実してきていて、本当に子育て世帯にとってすごくありがたいなと思っているんですけども、まず学童の、最優先事業の地域子どもクラブ事業の拡充の部分なんですけど、今まで令和3年、令和4年と地域子どもクラブが増えてきていると思うんですが、運営の仕方がそれぞれ違ったと思うんです、今まで。民間に頼んでいたり、社協さんが入っていたり、地域の方々がされていたりということで、地域性もあるかと思うんですけど、それぞれ運営の仕方が違う中での何か検証だったり、地域性があるかもしれないんですけど、この地域子どもクラブの中で、このまま継続している上で、いろいろ様々なやり方で、情報の共有だったり、子どもを預かる上で共有などして、今後増えていく学童の運営の仕方などを決められているのかどうかということをお伺いしたいです。

地域子どもクラブは、今おっしゃられたとおり、地域の方が中心となっていたというのがもともとだったんですが、地域の方が中心となって引き続き毎日実施をしているというところもございますし、地域の方のお話を聞く中で、少し事業者の方の力を借りることで毎日実施ができますというところがあったり、また全体的なところのコントロールを事業者さんにお願いして、安全管理ですとか企画の部分は地域でやりますとか、いろいろ地域の実情に応じてやってきたということで、いろいろな状況があるところでございます。それぞれ、月に1回程度でしょうか、運営状況について関係の方が学校の方も含めて集まって、情報共有や問題点、こういったところがちょっとうまくいかなかったということは検証しながら進めております。また、利用者の方からも、実施済みのところからアンケート調査をさせていただいておりまして、今使われている方の9割以上の方が、また来年も使いたいとか、非常に高い評価をいただいているのかなと今考えているところです。ただ、おっしゃられたとおり、大きくは今3つの方式があるかなと思っています。地域主体、あと地域と実施事業者が並列といいましょうか、そういうことと、全体を事業者がコントロールするというような、大きく言うと3つあるのかなと思っておりまして、どの形がいいのかというのはなかなか、やはりそれぞれの地域の実情があるので、まだちょっと決められないんですが、ただだんだん毎日型のところも増えているところでございますので、その中で検証しながら、一番いいやり方といいましょうか、どういう方向がいいのかというのは検討しながら今進めているところでございます。

ありがとうございます。例えば井口小学校なんかは保護者の方々が中心となって地域子どもクラブをされているかと思うんですけど、今後、毎日実施になっていくと、保護者の方々の負担だったり──時給も発生しているかと思うんですが、その中での安全面というのは、何か勉強でしたり学んでいったりしているのでしょうか。保育の専門の方々と比べると、保護者の方がするということの少しリスクがあるのかなと思っているんですけど、その辺は何か考えられていますか。

地域子どもクラブは、もともとは保護者の方の見守りといいましょうか、遊んでいる子どもたちを見守るというところからスタートしております。その中で、井口小につきましては、今、社会福祉協議会さんも中に入っていただいておりますので、大分安定的な運営ができているところですが、地域の方々についても御負担のないところで、そういうスキルといいましょうか、そういったものを学んでいただけたらなと思っておりまして、地域子どもクラブの代表者会議とか、そういうのも定期的に開く中で、いろいろな情報提供ですとか、他の地域がこういう取組をしているとか、そういうところで研修する機会というんでしょうか、そういうものに取り組んでいるところですが、今後さらにちょっと考えていきたいと思います。

ありがとうございます。恐らくといいますか、今後、学校3部制を踏まえてこの地域子どもクラブも拡大していくかと思いますので、その辺の安全性というところがとても重要になってくると思います。保護者にとってはすごくありがたい、またこれも制度になってきますので、安全面と、あと本当にどんどんどんどん実施校が増えてきているんですけど、全市的に広がっていくように、その辺の安全性を踏まえてお願いできればと思います。ありがとうございます。