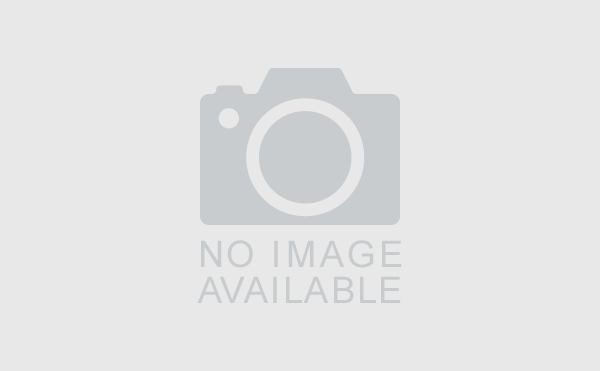令和5年11月6日 厚生委員会
2023年11月6日

本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、次回委員会の日程について、3、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか

よろしくお願いします。どんぐり山のほうで、指定管理者、社会福祉事業団がこれから進めていくと思うんですが、社会福祉事業団のほうのこれだけの事業を大きく進めていく中で、人員体制だったり、準備としての体制というのは整っているのでしょうかというところと、あと、こちら、どんぐり山の場所というのが山の上にあると思うんですけども、交通の便のところで、バス停もあって、そこから徒歩5分というところなんですけど、やはりこの高齢者の方たちが山を登って、その場所に行くと。ちょっと自転車では無理、なかなか上がっていくのが難しいというのを聞いているんですけども、交通の便のところで、地域の交流スペースですとか、日常的に地域の方たちが集まる上で、結構大変なのかなというのはちょっと思っています。
ある程度、事業団、いろいろな地域の団体さんでしたら、車で現地まで着けることはできると思うんですけど、こういった地域の通いの場の事業という点では、地域の方たちが来る交通の便というのがちょっと心配ではあるかなとは思っています。現地もちょっと見てきたんですけど、駐車場としても、何台ぐらい止められるのかなというのが、いろいろな車でたくさん来ることもないかもしれないんですけど、あそこの立地を考えると、ある程度交通の便というのを想定しておかないと、実際使い出したときに、行くのが大変だということになると思いますので、その辺はどのように想定するか、教えていただきたいと思います。

隠岐国博さん
まず、人員につきましては、こちら、指定管理になるところからして、事業計画を立てていただいております。必要な人員については適宜配置するといたしまして、現在もまだ採用を行いながらという部分はございますが、しっかり対応できるような人数を今そろえているというようなところでございます。やはり生活リハビリセンターのところの夜間の関係とかも含めまして、専門的なところとの委託をするのかどうなのか、そういうところをちょっと詰めている部分はございますが、利用者に困らない範囲、あとは施設管理として十分に対応できる人数というところで調整をしております。
そして、交通の関係でございますが、こちら、やはり御指摘のとおり、道幅も狭くというようなところもございます。そういう意味では、事業団のほうで25人乗りのマイクロバスを運転手つきで12月から運用できるように借りているような状況で、運用しようと思ってございます。
その理由といたしましては、やはりおっしゃっていただきましたように、いろんなところでの研修の関係、市民の方の利用というときに、一定の人数が御利用いただけるようであれば、例えばコミュニティ・センターにお集まりいただいて、そして、どんぐり山までお連れして、またコミュニティ・センターに帰っていただくような運用をできるのではないかと思ってございますので、そういった対応をしてまいりたい。
例えば、また町会の皆様とであれば、どこか集合場所等を決めていただけるようなことがあれば、そういった形でも運用していきたいというように考えてございます。
また、もう一点といたしましては、西部エリアのオンデマンド交通の関係で、こちらでもどんぐり山をそういった形でのポイントといたしまして、今もう運用できるような体制を整えてございますので、そういった形でのデマンド交通の御利用も御案内しながら。
それで、駐車場の関係でございますが、民間のところにも少し借りるようなところを踏まえて、少しでも利用環境を整えるというふうなところで取り組んでいるところでございます。
以上でございます。

ありがとうございます。そうですね、新しい事業で事業団の方たち、事業計画を出しているということだと思うんですけども、やはり最初は混乱でしたり、なかなかうまくいかないところもあると思いますので、しっかりと見ていっていただきたいなと思います。
あと、交通の便に関しては、マイクロバスというのを手配しているということで、少し安心しました。ぜひ三鷹市内の全体として、いろんな方が使っていただけるように、そういった形で周知だったりをして、よりよい活用をしていただけるように進めていただければと思っております。
以上です。ありがとうございます。

生活環境部報告、本件を議題といたします。

よろしくお願いします。本当にこれからのコミュニティの在り方ってすごく難しいなと思っているんですけども、やっぱり住協でしたり自治会というのは過去の歴史がある中で、また三鷹市全体で見ると、エリア性も大いにあって、そのエリアごとでの関係性だったり、とても違うので、この中でこれからどうしていくかって本当に難しいなと思っているんですが。
あとまた、やはり一番大きいのが世代間のこのギャップというところで、まとめていただいた資料の5ページ、コミュニティ行政に関わる主体や施策等というところで、この上段の住民協議会、コミュニティ・センター、町会・自治会、あと地区公会堂というのは、本当に高齢者の方々に支えていっていただいているような組織づくりになっていると思います。
この中で、今後、例えばデジタル化していくとか、あと今まで活動が生きがいになっている方々もたくさんいると思うんですけども、そういった方々へのフォロー。デジタル化していく中で、もちろん子育て世帯にとってはありがたいんですけども、やはりそこにすごく──何で今までこうだったのに、できないという、今まで支えてくださった方々へのフォローというところが一番大変かなと思うんですけども、その辺をどのように考えているかというのをまずお伺いしたいです。

垣花 満さん
非常に難しい問題かなというふうに思っておりまして、私どもも常にその辺は悩んでいるといいますか迷っているといいますか、本当にこのまま進めていいんだろうかみたいな迷いというのは常にあるんですけれども、やはり時代は進んでいくんだろうと思います。
その中で、逆に、やっぱり高齢者の方にもデジタルを知ってもらうことはすごく大事だと思っております。行政としてできることというのは、デジタル相談サロンみたいなものを今やっておりますけれども、まずスマホからいじってみようねみたいなことをやったりとかもしてございます。そういったもので、じゃあ、全部解決できるかというと、やはり最後の1センチというか、そのところはやっぱりコミュニティなのかなと思っております。やっぱり周りの人の支えというのがないと、デジタルというものの中で高齢者がうまくできない、例えばこれをやってと頼める人がすぐそばにいれば、押して予約をしてもらうとかいうことも可能ですよね。私たちが、例えばそういった仕組みづくりも含めて、応援はしていく仕組みをつくりながら、そこは最後は市民の皆さんと一緒に支えていける形にしないといけないのかなというふうに思っています。

ありがとうございます。私もそういう意味で、住協でしたりコミュニティ・センター、市民の方々の意識の改革というのがなければなかなか難しいのかなと思って、ここは地道に進めていくしかないのかなとは思っています。
あと、本当に高齢者の方、住協、町会・自治会が生きがいとなってやっている方々がいらっしゃるので、本当、そこら辺をきめ細かく、どうサポートしていくかというのをまた考えていかなければいけないなと思っています。
一方で、先ほどの、井の頭のようにデジタルを入れたことで子育て世帯が参加しやすくなったという事例があるように、本当に子育て世帯の居場所づくりというのも大きな課題です。今もう課題として出ていると思うんですけど、コミュニティ・センター、地区公会堂というのは、早い者順だったりするところがあるので、子育て世帯がほとんど取れないような環境があります。なので、そういう意味では、子育て世帯にとっては、こういった居場所づくりというところをたくさん増やしていっていただきたいというところをすごく考えております。
また、この居場所があるということに関しても、これまでコミュニティ・センター、公会堂をどう使うかというような広報活動というのは具体的に何かされてきたりはしていますでしょうか。

コミュニティ・センターは、多分盛んに広報とかにも出ているので、恐らく存在自体は認知は高いのかなというふうに思っています。ただ、やはり使い方というかルールがまちまちみたいなところというのは、やはり今後直して、やっぱり統一的なものとして、市からも情報を出していく必要があるだろうなと考えているのと。
地区公会堂につきまして、やはり町会さんに管理をお願いしているというところで、やはりこれも非常に見えづらいというところがありますので、私たちとしては、やはり町会さんの事情が許すところ、もしくは町会さんからヘルプを求められているところから、例えばデジタル化して、例えば市内どこからでも見れる、空き状況も分かるような形にしていく、それをきちっと広報していくというのが大事かなと思っています。

ありがとうございます。そうですね、うちも実家のほうは地区公会堂の管理をしているんですけども、それがちょっと大変だという声も聞いていたり、あと三鷹市内の地域では、やっぱりデジタル化で場所を貸しているというような事例は結構幾つもあって、そういったものも子育て世帯は使っていたりするので、ぜひそういったところの検討もしていただけたらいいなと思っています。
また、子育て世代に関して、以前はやっぱり対面のコミュニティというのが多かったんですけども、コロナ禍の中でコミュニティの形がデジタル、オンラインだったりというので、すごく変化しているので、オンライン化してきた子育てのコミュニティをまたこういった地域のコミュニティ・センターとか公会堂という対面のコミュニティづくりというところへといった周知というのもしていただけると、同じようにコミュニティ・センター、地区公会堂というのの活用につながっていくのかなと思います。
あと、私も住協に所属していたんですけども、やはり年齢的に高齢化しているというところでは、学校と住協との連携というところで、どうにかできないのかなというのを考えてはきたんです。やっぱり学校を卒業すると地域から離れてしまうという方々も多いので、学校に子どもが所属しているときには地域に関わるけれども、学校を卒業したときに地域から離れてしまうという方々に対して、住協だったり自治会というところと関わりやすい環境づくり、先ほどもおっしゃっていましたけども、やはり会議が夜の19時からとかっていうのは、子育て世代は参加しづらいですし、また昼間というところも、時間をちょっと考えていただかないと参加しづらいというところがあるので、やっぱり組織だけでなくて、運用方法というところもしっかり御指導いただけたりとか、お話ししていただけるといいかなと思います。
運用方法等は、やはり市民主体なので、市のほうから何かこうしたほうがいいとかということはお伝えしたりとかしているんですか。

いわゆるいろんな施設の運用方法ということでよろしいかと思いますけれども、当然、私どもだけで決められることではないので、こういうふうに変えたほうがいいんじゃないかという御提案をしながらやっていく。
あと、例えばそれぞれの会議の在り方みたいなもの、例えばそういったものについても、先ほどちょっとお話ししたとおり、若い世代の方が入っていく、もしくは今までコミュニティに属していなかった方が入っていくためには、やはりその負担の在り方とか、会議の時間帯とか、あと会議の参加の仕方、例えば対面でもいいし、忙しいときはZoomでもできるよとか、そういう多様性みたいなものを生み出していかなきゃいけない。
これ、じゃあ、行政が何ができるかというと、そういう啓発をしていくしかないと思うんです。実際、行政がそこの団体を運営していくわけにいかないので、やはりそういった啓発だとか気づきみたいなものを出していけるようにするのが、中間支援組織の強化というところでもちょっと考えているところでございます。

ありがとうございます。あと、一番大きな課題かなと思っているのが、この無関心層への市民コミュニティの意識向上というところが、これがまたとても難しい部分かなと思っているんですけども。具体的に、地域福祉コーディネーターによる相談事業を考えていたりとか、そういった自分の生活に関わることで、少しでも無関心層の方々へ意識を持ってもらいたいということだとは思うんですけども、この無関心層へどうしていくかというのはどのようにお考えでしょうか。

これまた難しい御質問で、無関心だから無関心層なんですよね。これが、なかなか難しいんですけれども、ただ知らなかったから無関心だったという方も多いかと思うんですよ。ですから、先ほどからもちょっと申し上げた、例えばコミュニティ活動の見える化ですとか、もしかすると、例えば目につきやすいところでの啓発事業みたいなものだとか、場合によっては、もしかすると、お声がけして、ちょっと話しませんかみたいな仕組みみたいなものも必要かもしれません。
ただ、やはり、ここのところって、なかなかそう簡単には変わっていかないとは思っておりますけれども、少しずつ市民団体さんなんかとも一緒にそういったことをアピールして、出していくことで、ちょっとずつ取り込んでいけるんじゃないかなというふうには考えています。

ありがとうございます。私も地域団体をやっていたことがあるので、本当にそういうところで、どうやったら関われますかですとか、全く関心のない方もどんなきっかけで関心を持つか分からないので、本当に広くこういった地域に関わるということを子育て世帯、若い層に向けてもいろいろ周知していただければなと思っております。
以上です。