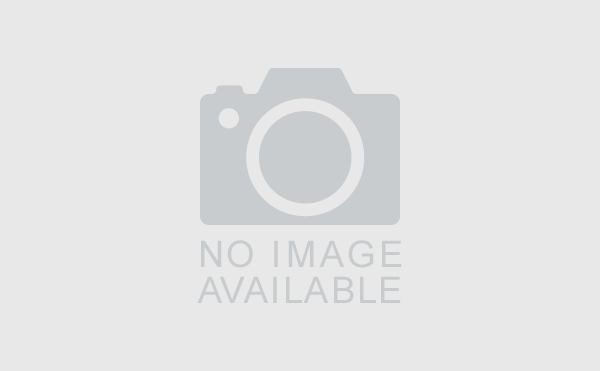令和6年3月7日 厚生委員会
2024年3月7日

議案第10号 三鷹市介護福祉条例の一部を改正する条例、議案第11号 三鷹市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、以上2件を一括議題といたします。

よろしくお願いします。25ページの施設の人員、設備及び運営の条例を改正するあらましについてなんですけども、今回、地域包括支援センターの業務の見直しという点で指定介護予防支援事業者の対象が拡大されたということなんですけども、この介護予防支援事業を行う者というところで、ケアプランの作成以外に何か地域包括支援センターがやっていた業務とかでできることというのはあるんでしょうか。

小嶋義晃さん
今回、地域包括支援センターの業務の見直しということで、ここにも書いてありますように、基本的に今回はケアプラン作成のみということで、相談業務は引き続き地域包括支援センターが行うというところでございます。

分かりました。先ほど部長のほうからもお話あったように、7つの住区の特色に合わせて地域包括支援センターの役割というのが多岐にどんどん広がってきている現状があるかと思うんですね。地域包括支援センター、社会福祉協議会ですとか地域と連携して、本当に現場に入って、少ない人数で動き回っている状況がありますので、先ほど部長もおっしゃっていたんですけども、人数ですとか人員に対しても、もし見直し等ができると、より本当に地域包括支援センターが向き合わなければいけない高齢者の方たちとしっかり向き合っていけるのではないかなと思いますので、その辺なども検討していただければと思います。
以上です。

では、6請願第1号 国民健康保険税、介護保険料の値上げを中止し、後期高齢者医療保険料の値上げ中止を求めることについて、本件を議題といたします。

今日はありがとうございます。私自身も両親ともに後期高齢者という中で、本当に生活、大変な思いをしているのを実際目の前で見ているんですけれども、先ほど君塚先生のほうから、施設の運営の中で共助が大切だというお話があったと思うんですけども、本当に、人生100年時代ということで高齢者が増えていく中で、そのような予防の部分でいろいろ取組をされているかと思うんですけども、そういったところで効果的なものとかありましたら、それを教えていただけますか。

君塚雄二さん
去年、当みなみうら診療所の2階で認知症講習会を開催しました。当初は20名から30名ぐらいかなと思ったんですが、NPOさんの協力もあって、実は入り切らないぐらい、50名以上の方が認知症の講習会に来ました。市民の皆さんがやはり気にするのは、認知症の仲間をどう支えたらいいか。それから、自分が認知症にならないためにはどうしたらいいか。それから、認知症になったら、今度は介護の問題だとか、様々な問題、特にひとり暮らしの高齢者の方、お子様がもう成人して、市外、遠くのところに住んでいる方は非常に皆さん心配な状況です。その中でやはり、先ほども言いましたように、認知症の始まりはいつなのかなということなんですが、医療のいろいろな先生の方々は様々な意見がありますが、実は長期にわたってやっぱり認知症の進行というのは始まってきておりますので、早期の発見、これがポイントなんですね。早期の発見をするには、やはり医療機関に来て、例えば長谷川式の認知症検査だとか、そういうものを早めに受診することによって認知症の傾向を測る。それから、お友達の皆さんから、どうもあの人おかしいよというような声が出た場合には、やはり皆さんで、1回検査してみたらというような、そういうネットワークができるということが非常に大事なことで、そういう意味でも、私どもの生活協同組合では、組合員のイベントや様々な行事を通して触れ合いの場をつくっております。その中で、やはりそういうことで早期の認知症の発見があった方が数多くいらっしゃいます。理事の方でも、認知症になって、会議の時間を忘れたり、出席できなかったりという方も何名かいらっしゃったりします。そういうことで、何が大事かというと、先ほど言いましたように、保険料が足りないから上げるというだけじゃなくて、疾患に──認知症も疾患ですね、疾患ではないというので介護のほうなんですけど、最初の出足は疾患なんですよ。その制御をどうしたらいいかということを国全体、もしくは自治体でも積極的に考えていかないと、自治体の運営がままならなくなる時代が当然、今後やってくると私は思っております。
そういう意味でも、議会のこの委員会の中でも、保険料の算定の制御はもちろんですけども、加えて、疾患にならないためにどうしたらいいか、市民の方に協力していただいて、どうしたら認知症や肺疾患、肺炎とか、大腸がんだとか、そういうものにならないようにして、初期の段階で医療の受診をしてもらって、そこで後にかかる医療費の費用の増大を防ぐというような取組も併せてしていただくということが非常に大事じゃないかなと私は思っております。そういう意味でも、今回の医療費の保険料の値上げというのは、これから、じゃあ、この値段でもう上がらないよというようなことが言えるのかどうなのか。毎年毎年、窓口割合は今度は3割だ、国民健康保険は赤字だからもっと上げなきゃいけないと、このようなことをやっていれば、当然、10年後には市民は生活ができなくなるぐらいの困窮を極めると思います。特に50代、60代、まだ就業しているときには社会保険がありますが、いずれ定年して国民健康保険に移っていきます。その際に、現在、年金の受給が毎年毎年延ばされて、高齢者も働けというようなことを言っていますが、その高齢者の就業人口がかなり少なくなる中でもって、高齢者が働くには体が健康でなければいけません。そういう意味でも、国民健康保険の重要性というのはこれからすごく増すと思うんですね。そのときに、どんどんどんどん値上げをしていく、ただ財政が厳しいから値上げをしていくということであれば、いずれこの社会は崩壊するんじゃないかなと私は思っておりますので、その辺も含めて、一地方自治体ではありますが、東京都や国にやっぱり働きかけをしてもらって──プロジェクションマッピングというか、都庁に映像を映して7億円ってお金を使うわけですよ。オリンピックでも何億円ってお金を使うわけですよ。ただ、それでも、観光客は呼べても、国民は幸せにならないですよね。都民も、まして三鷹市民も。そのようなお金の使い方の構造改革を提言していかないと、いずれは地方自治体は倒産していくような状態になるんではないかと思いますので、その辺もひとつよろしくお願いします。

ありがとうございます。先生がおっしゃるように、地域で元気な高齢者の方たちが多くいていただけるように考えていきたいと思います。ありがとうございます。

生活環境部報告、本件を議題といたします

よろしくお願いします。令和6年2月に住民協議会への説明、ヒアリング、2回目ということをされたと思うんですけども、このときに、これまで住民協議会にも何度もこの基本方針の仮称の案についてヒアリングしてきたと思うんですけど、何か意見とか出たものがあれば教えてください。

垣花 満さん
私もちょっと全部行ったわけではないんですけれども、課としては7つ全部回らせていただきました。おおむねなんですけれども、すごく応援をしていただけているなという気がしました。例えば、何か御質問ありますかと聞いたときに、挙手していただくんですけれども、それって本当にうまくできるのと御質問しそうなのかなと思ったら、早くやってとか、そういう御質問というか御意見があったりとか、今の住民協議会に対する課題提起についてはおおむねそのとおりだという御認識をお持ちのようで、あとは具体的にどういう手順で、どれだけ早くやってくれるのかというようなところの御質問が多かったかなと思います。一部、変わっていくことに対する御不安とか、でもうちの住協は特別だしみたいな御意見も若干ございましたけれども、おおむね御賛同いただけているのかなと思っております。
以上です。

ありがとうございます。住協の期待感もすごく感じていますので、よろしくお願いします。
あと、基本方針の今回の追記事項について幾つか質問させてもらえればと思います。3ページ、全体の基本方針の3ページに追記事項があります。網かけの部分なんですけど、各住民協議会が発行する周年記念誌やNPO法人三鷹ネットワーク云々ってあるんですけど、この各住民協議会が発行する周年記念誌になっている理由というのは、なぜ周年記念誌かという理由があれば教えてください。

これは、周年記念誌って割とその歩みのまとめとか、考え方とか、そういったものが記載されていることが多いんですね。特に、割と古い時代の周年記念誌にはそれが顕著で、非常に、私たちもそれを読んで勉強できるようなことも多かったので、こういう書き方をさせていただきました。

ありがとうございます。各住協によって歴史が違う中で、なぜ周年記念誌であったのかなというのを思ったんですけど、分かりました。ありがとうございます。
今回、基本方針策定においては、学識経験者だけでなくて、地域で活動している様々な団体や現場に入ってきていただいて、現状の把握からこれからのコミュニティの在り方について時間をかけて意見交換していただいて、本当にありがとうございました。
続きまして、追記事項についてなんですけども、50ページの現代都市におけるコミュニティの追記事項の部分で、先ほど、市長も楽しくコミュニティをしていかなきゃいけないというところを、具体的に入れてみたということだと思うんですけども、課題や興味を持って始まる地域活動であり、まず緩やかなつながりでしたり負担のない活動から始まったとしても、その活動が地域に求められて、やりがいになり、地域の人材になってくるまでに、実際にその活動にのめり込んでも、いつの間にか負担になっていくという、地域活動というのはだんだんそういうふうになっていくものだと思うんですけども、その辺を懸念して、その後の行に、行政組織の一部ではないことを理解した上での連携や協働の推進が重要ですというふうに書いてあるんですけども、やはり地域の人材になっていくには、ボランティアでの負担というのが大きく関わってくると思うんですけども、その辺というのはどのようにお考えでしょうか。

これ、非常に難しい話かなと思っておりまして、私ども市としても、例えばボランティアポイントみたいなものも今施策として出しておりますし、ここの、先ほど取り上げていただいた、市の一部じゃないというか、そういったことの、こういうことを行政として出すのは結構慎重に考えたんですけれども、やはり今の、楽しんでやっていらっしゃる団体さんはまだいいんですけど、やっぱり苦しんでいる団体さんを見たときに、もう辞めたらと言ってあげたくなるような、本当にお一人で全部しょってしまっているような状況も見受けられると。そのときに、やはり、そこまで全部やらなくてもいいんじゃない、これだけでもいいんじゃないと言ってあげる人がいたり、もしくは行政が言ってもいいんですけれども、そういうスリム化、いわゆるお仕事のスリム化と、それから先ほど申し上げた中間支援機能とか、行政がつくる、例えばアドバイザー派遣だとかお手伝いだとか、そういったものをやっぱり組み合わせてやっていくこと、そこに費用をやはり行政としてはかけて──皆様の御負担に対して何か弁済という形はなかなか取れませんけれども、そういう仕組みづくりの中で費用をかけていくべきなのかなというふうに考えています。

ありがとうございます。今、部長のほうからも費用というお話が出たんですけども、私も長年地域活動をしてきた身として、皆さんが言われているのは、やはり場所の面と資金面というところが、地域活動を長年していくと、すごく課題になっていくところで、そこで先ほどの地域ボランティアポイントですとか、そういった取組も検討されていると思うんですけども、現在三鷹市でのそういった地域活動の補助としては、社会福祉協議会が行っている地域サロン活動資金助成の1万円というのを使って皆さんどうにかこうにかやっているというところがあるので、直接的なお金でなくても、先ほど部長がおっしゃっていただいたような、そういったこともこれから具体的な策定のときに検討していただけると、ここの内容というのがより響いてくるのではないかなと思いますので、よろしくお願いします。

一応、もう一度繰り返しになってしまいますけれども、やはり、いわゆる中間支援機能ですとか、いわゆる何か事務の負担を下げられるようなアドバイスができる人たち、例えば東京都のつながり創生財団の専門家の人だとか、あと行政書士さんだとか、もしかしたら将来的には何々士、何々士といういろんな方たちがもし連携できたら、それはいいことだなと思っていますし、それから、例えば集まる場所の確保。今、地区公会堂、コミュニティ・センター等がございますけれども、必ずしも、使いやすい状態になっているかというと、いろいろと課題もあると。それから、例えば商店街のちょっと時間の空いている店舗を活用できないかとか、いろんな集まる場所の工夫、そういったところの工夫とか支援というのは市が中心にやっていきたいと。なかなか直接的な費用となると難しいなというところはあるということを申し上げておきたいと思います。

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、51ページで、先ほども部長がおっしゃられたように、世代間の相互理解という点でこのような記載があったというところなんですけども、やはり住民協議会ですとか、既存の組織に対して若い世代が入るときに、そこは世代間の相互理解という点と次の世代への引継ぎというところの、ここの視点というところはこの中にも入っていますか。次の世代への引継ぎがうまくいかないという課題があると思うんですけど、その辺の意図というのはこの中に入っているんでしょうか。

次の担い手をつくっていかなきゃいけないというところの視点というのは、ここだけじゃなくて、割とあらゆるところに入れさせていただいております。
以上でございます。

ありがとうございます。
すみません。続きまして、53ページ、ここも黄色の網かけの部分なんですけど、今後、本当に、今までの既存の住協ですとか町会というところからテーマ型コミュニティ、若い世代に向けてここをどうしていくかというところが大きな軸になると思うんですけども、このテーマ型コミュニティというのは、特に自主的に目的を持って活動していく形になると思うので、今、そういった中間支援でしたり、そういった横のつながりというのをつくっていたとしても、そのコミュニティ、テーマコミュニティ自体が地域につながれていない場合というのが予測されるんですが、そういったところはどのように情報をキャッチしていくというふうに考えられていますでしょうか。

私たちのほうとつながりがないとか、何ていうんですかね、地域と全く関係なく活動されている人たち、それはそれで、その方たちがそれでよければそれでいいのかなという気はしているんですね。あまりそこを全部ひもづけていく必要もないとは思っておりますが、逆につながりたい場合につながれないことが問題で、そのための、例えばコミュニティ・センターでの啓発講座だとか、イベントなんかを例えば協働センターがやることで、そこにまず最初の一歩来てもらうとか、あと各NPOでやっぱり最初の一歩目に入りやすいような委員会とかグループをつくっていると思うんですね。観光協会なんかも、興味あったら来てみてというような、そういう会議を月に1回やっています。そういったところに、まず入りやすい、一歩目を何とか気楽に入ってもらって、嫌だったら来なくていいよと、そういうようなつながり方というのをしていくことで少しずつ、つながりたい人とつなげてあげたい人がマッチアップしていくようなことをしていかないといけないのかなと思っています。

ありがとうございます。そうですね。あえてつながらないという方たちもいますよね。分かりました。ありがとうございます。
次に、56ページの追記事項、緑の部分なんですけども、組織横断的な連携が重要である。本当にそれが重要であると思うんですけども、多様なコミュニティが生まれれば生まれるほど、その状況──今の話も関連するんですが、把握するのは難しくなると思いますが、もう既に、例えば子育て支援、高齢者支援、福祉の部分であれば社会福祉協議会が取りまとめていたりですとか、まちづくりに関心がある方は商店会という、ある程度枠組みで、ここに人が集まっているなというところがあるかと思うので、そういったところのまずは大きな枠組みでのつながり、活動をうまく把握していくということもできると思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。

行政が、ここの部署でこの部分でいくと、そういう縦割りじゃなくて柔軟な対応をして、市として包括していくというか、一緒にやっていくような体制をどうつくるかという御質問だと思うんですけれども、これ、なかなかまだ正解が見つかっていません。ピラミッド型につなげてもなかなかうまくいくものでもないですし、やはりそれぞれの部署がクモの巣状というかインターネット状につながっていかないと、なかなかうまくいかないのかなというふうに思っております。ただ、これはちょっと今後の検討課題かなというふうに思っていて、私どもも大きなプロジェクトをやるとき、なかなかうまくいかないで苦しむことも多いんです。自分たちのことでもそういうことがあるんですね。だからその辺の辺りは今後研究を重ねてまいりたいと思っております。

すみません。ありがとうございます。
あと2つ、すみません。60ページの追記事項なんですけども、中間支援機能の強化ということで、地域課題解決のための仕組みのプラットフォームを担えるコーディネーターやプラットフォーマーの育成という点では、とても大変なことだと思うんですけども、これを市民協働センターを中心に機能を生かしていくという、このメリットはどこにあるように考えますでしょうか。

こういったコーディネーターがいることのメリットという御質問でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
まずは、こういったコーディネーターさんを育成するというのはすごく大変なことだと思います。すごく、素養といいますかね、そういったものも関係してくると思うんですけれども、三鷹にはやっぱりそういった素養を持った方が結構いらっしゃって、そういった方たちをきちっと養成していけるような講座だとか、そういったものもそのうち展開をしていきたいなと思います。そういった方たちがどこにいるべきかというと、別に協働センターだけである必要は全くなくて、まずコミュニティ・センター、そういったところにいてほしいですし、それから、例えば商店街の中でいていただいても結構ですし、いろんなところにそういったコーディネーターさんがいることで、何か地域課題で困ったことがあったときに、その方に相談をしていただくことでいろんな団体をつないでいってもらうことができるということが、私のこの中間支援機能の強化というところで考えたメリットでございます。
以上でございます。

ありがとうございます。
すみません。最後に、プリントの3の(2)の部分で、有識者からの意見というところで、市民活動は事業化し、専門性を高めているというのは、これは具体的にNPO法人ですとか、そういった事業化していくことというのが高まっているということですか。

例えばですけれども、食品のお土産を作りたいというような形になったときでも、そこに関わってくる法律って物すごい数があるんですよね。それから、例えば子育ての場所をつくりたいといっても、やればやるほど、預かったときの責任はどうなるんだとか、いろんな法的な問題も出てきたりする。1つのパソコンをみんなで買っただけでも、解散するときに大もめになったりとか、そういったことも重々あるので、そういったことをきちっとやっぱり、活動を深めていくためには、そういった専門的な見地からどんどんアドバイスをしてくれる人が必要だという点と、それから活動自体も、おっしゃるとおり、すごく、NPO化したり、株式会社化したり、いろんな形で専門的に、一番究極はビジネス化していくということだと思いますけども、そういった団体も増えてきていますので、そういったものに対してきちっとアドバイスができる人材をそろえたほうがいいと、そういうことでございます。

ありがとうございます。すみません。様々質問させていただいたんですけども、本当にこのコミュニティ創生、過渡期に来ていて、新たな取組だったり、これまでの取組というのをどう生かしていくかというところだと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。

子ども政策部報告、本件を議題といたします。

よろしくお願いします。三鷹市がほか自治体に先駆けて行ってきた子育て世代包括支援センターであり、様々な成果が出てきたとこれまでも思うんですけれども、今回の、特に虐待の相談対応でしたり、子育てに困難を抱えている世帯がという点では、これまでの取組の中でどのように、同じような機能を持っていた子育て世代包括支援センターの中でどのような評価をされているか、お伺いできればと思います。

高橋淳子さん
子育て世代包括支援センター会議を立ち上げましたのが令和2年度からになります。平成29年度から子育て世代包括支援センター機能は稼働はしておりましたけれども、具体的に関係機関が集まって、しっかり連携を図っていく、連携強化していくという取組につきましては令和2年からスタートしたということになりますけれども、その中で、例えば連携強化が大きなテーマにはなっていたんですね。全ての子どもと子育て家庭を切れ目なく包括的に支援をするということがテーマでしたので、そのためにはやはり連携が必要だということで、連携のための様々な取組をする中で、具体的な事業も構築してきたということがございます。特に、総合保健センターと同じ建物ですので、子ども発達支援センターが同じ建物で、乳健からの子育て支援プログラムを構築したことによりまして、かなり早い段階から要支援の御家庭を発見するというところが共にできるようになりまして、子ども発達支援センターと子ども家庭支援センターも同じ所管ですので、そこでかなり連携を強化しながら、早い段階から支援ができたり相談ができるというようなプログラムができたということも1つの成果だというふうに考えております。

ありがとうございます。本当に三鷹市、先駆けてこのような取組で連携というところにすごく力を入れていただいて、大変ありがたいなと思っております。
また、子育て世代包括支援センターが今回、こども家庭センターの位置づけとして同様に機能として、法が定める事業として行うということなんですけども、今までも機能としての子育て世代包括支援センターで、センターとしては設置してこなかったと思うんですが、今回もまたセンターは設置せず、機能として行うという、この意図を教えてください。

秋山慎一さん
なかなか、子ども家庭センターを、じゃあ、新たに設置するかということでいうと、今すぐはなかなか難しいということがございます。今ここに記載している3施設はそれぞれ元気創造プラザと教育センターにございますけれども、そういう点では、今回のこの法改正に合わせて、じゃあ、1つのセンターをどこかに設置するというところまではなかなか一気には行けなかったところですね。ただ、当然、相談のしやすさであるとか、今高橋課長が説明したような連携のしやすさからすれば、一体で行うことは当然望ましいと思いますので、これについては引き続き研究しながら、ほかの自治体でもそういう事例ございますので、三鷹市として将来的な課題として、子ども家庭センターとして一体的な運用ができるかどうかということも研究してまいりたいというふうに考えています。

ぜひよろしくお願いいたします。
続きまして、これまでの子育て世代包括支援センター機能が子育て世代包括支援機能、子育て世代包括支援センター会議が子育て世代包括支援会議になることで、変化する部分、拡充される部分があれば教えてください。

まず、基本的にはセンター機能については、先ほど申し上げたように、もともとこの子育て世代包括支援センターというのは、母子保健の中でこういう、何でしょう、施設というか機能というか、そういうものが用いられたんですが、今回の改正法によって、それがなくなりましたので、少なくともセンターという呼称は紛らわしいのでやめようかという話をしました。ただ、じゃあ、それを、法律の上でいうとこども家庭センターに変わっているので、子ども家庭センター機能と言うかという話もいろいろ考えたんですが、それもちょっとまた分かりにくいので、子育て世代包括支援というのは、子育て世代を包括的に支援するという文字どおりの表現なので、これは引き続き、センターという呼称は取りますけれども、読んで何をしているかというのが分かるという点では、その考え方を継承して、残したということになります。
会議についても当然、呼称としてはそれを引き継いだわけですが、実はこれまでの子育て世代包括支援センター会議というのは、子ども発達支援課長が会議の座長を務めて、子ども政策部長は、センター長なんですけど、オブザーバー的にその会議に位置づけられて運用してきましたので、私も必ず毎回会議には出ていたんですけれども、この子育て世代包括支援会議については、今後要綱を改めますけれども、子ども政策部長が会議を主宰するという形で、関連各課をそこに入れてやるということで今考えていまして、実はちょっと説明をしなかったんですが、図1の右側のこのグレーのところに、これがいわゆる会議体の示しているところですけど、子育て支援課をここに追加しています。やはり、ひとり親の課題でありますとか、どうしてもこういう協議をしていく中で子育て支援課が非常にやっぱり重要なポイントにもなりますので、今回そこについては新たに構成員として課を入れたというところが変更点となります。

ありがとうございます。子育て支援課が入ってよかったです。
続きまして、今回、この大きな変化として、健康福祉部の健康推進課から母子保健事業を子ども政策部に移動するという点がすごく大きな点になるのかなと思うんですけど、この辺の母子保健事業というと、妊娠届を出してから健診でしたり、総合保健センターにこれまで本当によく行っていた部分が多いと思うんですけども、その辺の事業のすみ分けというのはどのようになると想定しているんでしょうか。

基本的には、今、総合保健センターの母子保健でやっている業務がそっくり子ども政策部に、母子保健係として位置づけてやりますので、総合保健センター自体というのはそのまま存在するわけです。これ、非常に分かりにくくて申し訳ないんですが、子ども家庭課の母子保健係も今の総合保健センターの中の一部には位置づけられるんですね。ですから、業務を持って組織が子ども政策部に移転してくるという言い方はおかしいですけど、執務場所はちょっと変えませんので、組織の構成が変わって、部という1つの組織体の中で、指揮命令系統の中で、今まで母子保健でやっていた業務を行うということですので、基本的には健康福祉部の健康推進課の母子保健でやっていた業務がそっくり子ども政策部に位置づけられるという、それで一体になるということです。両方に存在するということではなくて、全て子ども政策部の中に包含されるという、そのように御理解いただきたいと思います。

ありがとうございます。そうしますと、ゆりかご面接ですとか健診というのは、もう総合保健センターの場所でやらないということですか。

総合保健センターの今やっている場所でやります。場所についてはそうです。当然、ですから、本当に簡単に言いますと、組織が変わるというところですよね。部が子ども政策部に変わって、やっている業務とか執務スペースとかは基本的に変わらないということになります。組織で指揮命令系統が一本化されるというのはありますけれども。ですから、先ほどの御質問に絡めて言えば、新たにそういう、例えばセンターという建物を建てて、その中で例えば事業を行うということであればそういうことになりますが、今回そういう形にしませんので、現状の元気創造プラザの2階がいわゆる健診の場所であったり相談の場所にもなるというところは変わりません。

すみません、何度も。そうすると、相談も、その作業というか執務するのも保健センターの今までの場所で行って、組織だけが、保健センターのあった組織が組織としてくっつくというだけで、実態は変わらないということですか。

実態は変わらない、確かにそうですね。事業としては、その場所で引き続き行われている。ただ、組織を改めますので、そこのところでは子ども政策部の事業として行いますし、部の中の組織体としてのいわゆる指揮命令系統とか相互の連携とか、そういうのを図りやすくするということが狙いとなっているところです。

分かりました。ありがとうございます。
ちょっとこれに関連するんですけども、そうしますと、子ども発達支援課、これまで元気創造プラザの1階、子ども家庭課になるということで、ここも今までどおり元気創造プラザの1階での対応ということになるんでしょうか。

おっしゃるとおりでございます。

分かりました。ありがとうございます。
続きまして、子ども家庭課に今回、子ども家庭総務係と母子保健係を同一の課にしているんですけども、この狙いは何でしょうか。

まず、今回、子ども家庭課というのは、子ども発達支援課をベースにして新たにつくりました。それを部の筆頭課ということで位置づけをしてございます。三鷹市におきましては、部の筆頭課において、いわゆる調整事務とか、あるいは部における企画とか政策とか、そういった調査研究などを行う機能というのはどこの部も持っておりますので、そういう意味で、子ども家庭課を設置するに当たりまして、筆頭課の筆頭係として子ども家庭総務係というのを新たに設置したところです。同様に、母子保健係については、先ほど申し上げたように、健康福祉部から移管して、母子保健をやる業務を一体で係ということで位置づけております。
子ども家庭課をここで設置したという、しかも筆頭課にあえて持ってきたというのは──子ども政策部ができたのは平成22年なんですね、このときには実は3課で構成されておりました。今の児童青少年課と子ども育成課と子育て支援課、この3課が当時、名称は若干違ったと思いますが、平成22年に子ども政策部としてスタートしています。ですから、その当時の子ども政策部の仕事、子どもに関する仕事というのは、主として学童保育であるとか保育園であるとか、子育て支援課も基本的には子どもの手当だけをたしかやっていたと思うんですが、そういうものがあったんですが、その後、非常に業務が増えてまいりましたし、今、子ども発達支援課をつくったときには、そういう発達支援という取組が非常に重要になってきているということで課をこのときに新設したんですけども、今やはりそこの部分が非常に、子ども政策を考えていく中では大きなウエートを──もちろん保育園や学童も非常に重要な仕事なんですけれども、やはり今発達支援課でやっているような仕事は非常に重要だということもありましたので、ここは筆頭課に持ってきて、筆頭課であるということは、やっぱり部全体の仕事を包括的に考えるという、そういう役目も担いますので、今回、その中で筆頭係として、子ども家庭総務係という名称にしましたが、そういう機能をここに置いたというふうに御理解いただければと思います。

ありがとうございます。
続きまして、今回、子ども育成課をこれまでよりも細分化して、今までになかった保育園入所・認定係という──この係ではどのようなことに重点を置くと考えておられるか、教えてください。

清水利昭さん
まず、保育施設係を2つの係、新たには保育園の入所・認定係、それから保育施設係、これ2つに分けておりますのは、一つには入所のところの認定とかをもっと細かくやっていく。例えば、育休に入られた方の保育園に預ける期間を、今は基本的には育休に入られる前と変わらないような形にしておりますけれども、実際お子さんを見られる時間というのは違っていますから、他の市などでは、そこで認定を1回変えて、実態に合った形に切り替えるなんていうこともしておりますけど、三鷹は今までそういう部分はしていませんでした。ですから、そういうところ、きめ細かく認定を区切ってやっていくというようなことをしていきたいということとか、あとは保育の施設が非常に増えてきておりますので、そこのところの管理をより手厚くしっかりやっていくというところで、係を分け、人員体制も新たな形で拡充をして取り組んでいきたいというふうに、そういうふうに考えているところでございます。

きめ細かな認定をしていくということで、本当にこの保育園の認定については市民の方からいろんな御意見をいただいているので、ぜひきめ細かな認定というところで柔軟に対応していただけるようになればいいと思います。よろしくお願いします。
すみません。あと、同様に、保育支援係、指導検査係についても、どのような部署になるのか、教えてください。

ここのところは、まさに今、運営支援係の中で同じ職員が、一部係を分けている部分もありますが、重なる部分も持つような形で指導検査と保育巡回とを実施しています。ですので、年間の中で、巡回に行く日もあれば、指導検査として行くというような面もあります。実際は、これは受け手の側からしますと、保育巡回というのは、どっちかというと寄り添ってサポートするというような形の内容になります。一方で、指導検査というのは、これは厳しく、実際にルールどおりに運営がされているのか、規定をきちんと守られているのかというのをチェックするという機能があります。ですので、同じ人間がその2つをやると、やっぱり受ける側としては非常に複雑な気持ちになるということもありますので、そこはきっちりと職員を分けて、サポートする側はもう本当にサポートに徹する、検査をするほうはもう本当に厳しく検査に徹するという、そういう体制を取っていきたい。それから、人員も拡充することで、今よりも多くの園を1年間の中できちんと回っていくことができるようにしたいということでの今回の組織改正になっています。

ありがとうございます。きめ細やかにいろいろ対応していただけるということで、大変ありがたいなと思います。
先ほどの部長の話からも、実態としては、場所ですとか、そういったものが変わらないというのを聞いて、かなり混乱していくだろうなというのはもう想定されますし、なかなかそれをどう理解していくのかという、難しいなというのは正直思います。あと、本当に当事者としては、本当は期待するところとしては、やっぱり家庭センターという形で一括で子育てのいろんな相談だったりできるというところを期待するところではあったんですけども、今回の体制変更においても、子育て世帯の利便性向上というところでは、現在と同様に、子ども家庭課が本庁にあって、総合保健センターに発達支援センターがあって、家庭支援センターが教育センターにあるという、やはり3か所を行き来しなきゃいけないという、この辺の現状についてはどのようにお考えでしょうか。

御指摘のとおり、やはり、今分散しているというところは、1つ三鷹市の課題といいますか、そういう点はあるかなと思っています。やはり、何ですかね、ワンストップというか1か所で全てが完結するというのは大変理想的なところでありますので、今すぐにそれをじゃあ実現できるかというと、やはり物理的な課題とかありますので、そこは難しいなと思っておりますが、将来的な検討課題ということでは十分ありますので、いわゆるワンストップの総合相談窓口みたいなものと併せて考えていく必要はあるというふうには認識しています。

課題としてということなんですが、家庭センターができなくても、せめて1か所で終わるという、そういったことができれば、すごく制度として──機能としては本当に、子ども発達支援センターがあって、総合保健センターがあって、子ども家庭支援センターがあってということで充実しているので、ここをどういうふうに使いやすくしていくというのが、今部長もお話があったとおり、課題とともに、またこれも周知がなかなか難しいというところでは、日頃から活動で使っている、すくすくひろば、のびのびひろば、児童館とも連携しながら、ちょっとこの辺の分かりづらくなってきてしまっているところをうまく、分かりやすく当事者に向けてお伝えしていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。
以上です。