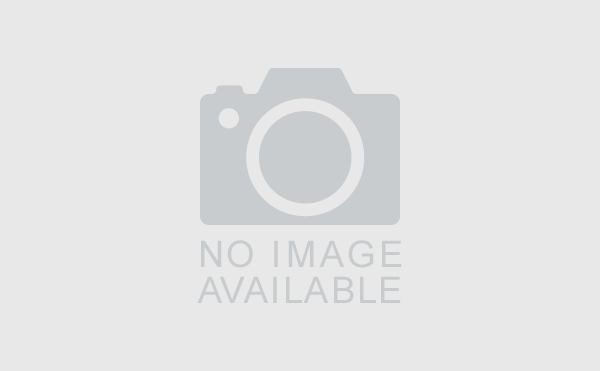令和6年6月19日 厚生委員会
2024年6月19日

生活環境部報告、本件を議題といたします。
本件に対する市側の説明を求めます。

よろしくお願いします。今回ちょっと、そもそもなんですけど、コミュニティ・センター等のデジタル化の推進ということなので、これはあくまでもコミュニティ・センターの中における事務局の体制の事務の標準化、平準化というところを目指しているということでよろしいでしょうか。例えば、各部会ですとか、住民協議会を支える様々な部会の中で様々な事務が発生していたり、本当に長年やってきているこの住民協議会においては、手書きだったりファクスだったりというものがたくさんあるんですけども、今回のコミュニティ・センター等のデジタル化というのは、あくまでも事務局の中においての標準化を目指しているということでしょうか。

ここにメインで掲げさせていただいているのは、まさに住民協議会と市民との関係性の在り方とか、そういった中でのデジタル化の推進なんですが、コミュニティ創生基本方針の中で掲げているデジタル化の推進はもう少し傘が広くて、いわゆる地域のコミュニケーション、そういったものもデジタル化していく必要があると、ですから町会さんなんかも含めてですけれども、そういった意味では、住協さんの中の部会の中での事務のやり方とか情報共有の仕方みたいなことにも波及させていきたいですし、していかないといけない。まさにそこで、10人に電話して連絡取っているみたいなやり方だと、なかなか疲弊していってしまうので、そういったことも含めて検討はしていますが、ここに特化して出しているのは、コミセンのウェブだとか、それから予約システムのことを指しております。

では、まずはそこから進めていくということで、やはり住協の大きな部分というのは、部会でしたり、部員の方たちが継続していくために、どういうふうにIT化でしたりデジタル化していくことで、本来向き合わないといけないコミュニティとか交流という機会をICTを入れることでいかにつくっていけるかということが、デジタル化をしていくことの意味に大きく関わると思うので、ただ単にデジタル化すればいいということではなくて、本来、このコミュニティでしたり住協の在り方というところで、どういうふうにデジタル化をうまく使っていくかというところが重要になってくると思うので、今回、まずはコミュニティ・センターの施設でしたり事務局のいろんな標準化というのは、7住協の標準化、平準化というところだと思うんですけど、やはりそこの奧の一番重要な点というところは、市民の方たちがこの住民協議会だったりコミュニティ・センターをどうやって使っていくかという上で、やはりそういったところが大事かなと思っていますので、今後、そういったところでは、各部会の作業の棚卸しというのも必要になってくると思いますし、あと組織の中も、ICTを入れることで、組織だったり各部会の形というのも大分変わるのではないかなと思うので、そこも、次の段階かもしれないんですけど、事務の部分だけではなく、考えていっていただけたらいいなと思います。
あともう一つ、先ほどの3つのワーキンググループに関しては、これは住協の方は入ってはいないんですか、事務局の方だけですか。

3つのワーキンググループの構成メンバーなんですが、まず、全てのコミュニティ・センター、住民協議会の事務局長さんは全員マストで入っております。割り振っております。それ以外に、事務局の職員に向けて公募という形で、手挙げ方式で、積極的にやる気のある方ということで手を挙げていただいて、入っていただいたという経緯でございます。

すいません。市民の方、住協に所属している方というのは、このワーキンググループには入ってはいないんですか。

先ほどの御質問とも関連されているかなと思いますが、今回ここでやろうとしているのは、事務局の様々な機能のデジタル化ということなので、そこの部分については、ワーキングには事務局職員、実際に現場が分かっていて、何をどうしていくべきかという議論ができる、細かい話ができるメンバーで入っています。ただ、この結果というのは、事務局長連絡会議で諮った後、今度、在り方検討委員会、ここには会長が入っています。それから、最終的には、今年度から機能をちょっと強化したんですが、住協連絡会という、7つの住協の会長、副会長と事務局長で組織している意思決定機関があるんですが、そこに諮っていって決めていく、そういう段取りで考えているところです。直接ワーキングの中に住民の方、委員の方は入っていないというのがお答えになります。

ということは、こういうふうな形で方向性が決まりましたということに対して、意見を会長なり副会長にもらっていくというような流れになっていくんですかね、このワーキンググループ。

大きな、こういうホームページでいこうとか、そういうところは在り方検討委員会で議論をしているんですね。このワーキングでやるところは、本当に技術的なところです。例えば、ホームページのコンテンツをどういうふうに移行していくかとか、どういう項目立てをしていくかとか、そういった部分が多いので、大きな方針というのは常に在り方検討委員会と住協連絡会のほうで諮りながら、細かい作業をワーキングでしているというふうに御理解いただけたらいいかと思います。

分かりました。ありがとうございます。やはり、住協の方々、高齢化しているので、なかなか細かい部分までは分からないところは多々あると思うんですけども、今までもやっぱり、ある程度検討して、これでどうですかという形で住協に諮られることが多かったような気がするので、できるだけ検討の段階から市民の方が入っていただけると、聞いているよということで、様々、部会だったり、いろんな方たちに話もまた下りて、そこから話が上がってくることもあるかと思うので、なかなか意見を言える方たちも少ないとは思うんですけども、結構大きな動きにはなると思いますので、このホームページを使ってこれから予約システムができるですとか、施設を使う上ではすごく大きな変化になると思いますので、できるだけその住協の参加している方たちも巻き込んでいただけるような仕組みにしていただけるといいんではないかなと思っております。
先ほどの具体的な部会ですとか、そういったことはまた次だと思いますので、またそのときによろしくお願いいたします。
以上です。

健康福祉部報告、本件を議題といたします。

よろしくお願いいたします。まず、ちょっとお伺いしたい部分が、この春から母子保健の部分が子ども政策部のほうに移動したかと思うんですけども、ここの部分で、今まで健康福祉部で行っていた部分ですとか、今後、子ども政策部と連携していく部分というところで強化していく部分ですとか、対応していくというところをどの辺と捉えているのか、お伺いしたいと思います。

小嶋義晃さん
この4月より母子保健の部分が子ども政策部に移管となりました。ただ、事務所的にも、御存じだと思いますけど、同じ総合保健センターの中の2階の部分で、子ども家庭課も今週からまた、一時1階にいたんですが、2階にまた上がってきてもらって、担当課長も上がってきてもらったので、そういったところで、まず事務、スペース的にも、空間的にも非常に連携しやすい体制だと思っていますし、やはり健康福祉部と子ども政策部、母子保健に限りませんけども、先ほど重層的支援体制の話も出てきましたけども、重なる部分が非常に多いので、そこはしっかりと連携しながら取り組んでいきたいと考えています。
以上でございます。

よろしくお願いします。やはり一番ちょっと懸念していたのが、体制の変更ということで、実質上、業務的な部分では大きく変わらないとは聞いていたんですけども、この母子保健の部分が子ども政策部に替わるということで、どう連携をしていく、またごそっと抜け落ちる支援が出てくるのではないかというところを懸念しておりますので、その辺はうまく連携していって、引き続き母子保健の部分でもしっかりと体制を整えていただければと思います。よろしくお願いします。
続きまして、1番の地域福祉コーディネーターの部分なんですけれども、こちら、77ページの施政方針のほうに、月1回の各コミュニティ・センターで実施している地域福祉コーディネーターによる相談サロンに加え、地域ケアネットワークやほのぼのネット等の地域活動、地区公会堂を活用した巡回相談を実施しますと書いてあるんですけども、地区公会堂を巡回するという形で、ここに来られない方というのは、あくまでもここに来た方たちに対して相談機能の拡充ということで対応していくということでしょうか。

木村祐介さん
各コミセンの相談サロンに加えて地区公会堂でのサロン実施なんですが、こちらはもともと一番最初に始めた大沢地域の地区公会堂で実績としてあります。今年度としましては、各コミセンの相談サロンという窓口で他の地域では実施しておりまして、今後ニーズがあれば、地区公会堂での実施も予定しております。また、こういった場にお越しになれない方に関しては、直接御訪問させていただいて、相談させていただくという形を取らせていただいております。
以上です。

ありがとうございます。本当にこの7住区に全地区配置の地域福祉コーディネーターというのは、社協だよりにおいても顔出しをしてコーディネーターの方を紹介したりですとか、ほのぼのネットでしたり、いろんな形で相談機能の拡充というのは大変見受けられるんですけども、やはりそこの場に来られない方たちに大きく課題があるなというふうに感じていますので、訪問していくというふうに先ほどおっしゃってくださったんですけども、その辺、地域の方がすごく情報を持っておりますので、その地域の方と連携しながら、訪問の機会というのも積極的にしていただけるとありがたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、3番の認知症にやさしいまち三鷹、こちらの2個目に認知症サポーターの養成(通年)とあるんですけど、この通年というのはどのような取組をしていく形でしょうか。

鈴木政徳さん
認知症サポーターの養成講座につきましては、主には地域包括支援センターの職員が講師になって開催はしておるんですが、認知症の方の生活スタイルで、地域で買物したりということもありますので、商工会とも連携して開催をできないかということを今年度検討してまいりたいというふうに考えています。

年に何回ぐらいあるんですか。

養成講座のところは、昨年度、令和5年度は全部で36回開催をしております。

分かりました。結構頻繁に行っているということでしょうかね。ちょっと、いつやっているか分からないというので問い合わさせてもらったときに、まだ開催日程決まっていないという報告を受けたことが昨年ありまして、人数がある程度集まったら開催するという形ではないですか。

隠岐国博さん
地域包括の方に人を集めていただいたりというのは運用上なので、必ず何人いなきゃいけないとかいうわけではございませんが、やはりできるだけ多くの方に御参加いただきたいというようなやり方の中で実施させていただいております。また、キッズサポーターの関係も、地域包括のほうで学校と調整していただいて取り組んだりというところも含めまして、通年というのはそういった意味で、年間を通して広く養成させていただいているということで、ある一定の期間に集中して取り組んでいる事業ではないというように御理解いただければというように思います。

分かりました。通年というふうに記載あったので、ちょっとそこで、定期的に行っているのかなと思ったので、すいません、細かく伺ってしまったんですが、結構市民の方でも、両親でしたり、この認知症サポーター養成講座を受けたいというような声を聞きますので、市民の方にどのような形で講座を実施しているかというのを分かりやすく出していただけるとよいかなと思いますので、その辺、何か取組を考えられるようであれば、お願いいたします。

まさに認知症に関しましては、先ほど御報告の中でも、計画、条例というところを含めまして、これからますます市民の方に御理解をいただかなきゃいけないということにつきましては深く認識してございますので、その取組の周知というところには、今まで以上に、これまで以上に行き渡るように、地域包括とも連携、地域の皆様とも連携しながら、また、認知症サポーター養成講座を受けていただいた方からいろいろ広がっていくような取組に展開してまいりたいというように考えております。
以上でございます。

分かりました。よろしくお願いいたします。
最後に、どんぐり山の運用実績について何点かお伺いしたいと思います。こちらもまだ1年たっていないので、具体的にというところは難しいかもしれないんですけど、やはりどんぐり山も市民の方からすごく関心が高い事業になっておりまして、多くの方から、行ってみたいんだけどというような声を伺っております。先日、ちょっと私も問い合わせたところ、直接事業団のほうに連絡を取ってくださいというような対応で、事業団のほうと調整しているんですけども、まず令和5年度の市民の方の見学状況など、把握していたら教えてください。

申し訳ありません、ちょっと細かなデータはないんですが、かなり多くの御視察をいただいたというように認識しておりまして、多くバスの御利用もいただいて御利用いただいたということで、バスの利用も全てで33回ほど御利用いただきながら、研修、また視察というような形で御利用いただいておりますので、そういう意味では、まだお声が受け切れていないようであれば、しっかり対応できるようにしてまいりたいと考えております。また、生活リハビリセンターの部分につきましては、少しプライベートゾーンというようなところもございますので、ちょっと御見学というところは事前に少し調整が必要な場合もございますので、その辺も含めてしっかり調整させていただければと思います。

ありがとうございます。マイクロバスの利用状況についてもお伺いしようかなと思ったんですけど、同様なので、こちらは割愛させていただきますが、地域の、町会ですとか住協でしたり、結構団体の単位で行ってみたいという方たちの声も多く聞いておりまして、そういった方たち、ぜひマイクロバスもありますのでというような案内もさせてもらっているんですけども、実際行った方からの声みたいのは伺っていたりしますか。

やはり御不便な地域といいますか、そういったところからの利用としては、バスがあってよかったというような形で、やはりかなり利用も、乗り切れないぐらいの形で、1台ほかの車で来ていただいたりという運用の仕方もあるようですので、ここはしっかりと──人数が少ない研修なんかですと、5人とかでも利用していただいたりしていますので、そこは小まめにできているのかなと思いますので、そういった意味では、利便性を高めて、市民の方からも御満足いただけるような取組になっているかなというふうに認識しております。
見学の方からの御利用の声ということにつきましては、いろいろ、実際見学いただく際にミニ講座のようなことも開催しておりますので、やはり、施設を理解できるとともに、そういった少しスキルもつけられてよかったというような形でのお声をいただいたりというところで頂戴しております。
以上でございます。

ありがとうございます。高齢者の方から、やはり自分がいざというときにこういう施設が三鷹市内にあるということが安心につながるということで、関心が高いという方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひぜひ見に行ける機会というのを増やしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
あともう一点、このどんぐり山を運営している事業団の運営状況というのは、人材でしたり体制等、問題はないでしょうか。大丈夫でしょうか。

どんぐり山の運営に関しましては、令和6年度も指定管理料のところで夜間の勤務、夜間の関係を増やしていただいたりということで、体制としてはできるだけ充実を、議会のほうでも御予算を認めていただいて、体制をつくっているところではございますが、まだ始めたところということで、課題が見えてくるケースもあると思います。また、生活リハビリセンターにつきましては、いろいろな、先ほども御紹介しましたが、介護度によっても、やはり関わる職員というところも替わってくる可能性もございますので、そこは引き続き、市民の皆様の御利用をしっかりできるような体制、また事業団の職員もしっかりとした勤務体制が取れるようなことというのは必要と認識しておりますので、必要な部分については、また議会のほうとも御相談させていただきながら、運営に支障がないように努めてまいりたいというように考えております。

ありがとうございます。やはり半年少し運営していく中でいろんな課題がきっと出てきていると思うので、その辺、うまく連携といいますか、市のほうとの相談でしたり調整というのをしっかりとしていっていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

すいません。よろしくお願いいたします。ちょっと聞き漏らしてしまったかもしれないんですけど、もう一度確認をさせてください。三鷹市においてのマイナンバーカードの取得率と、あとマイナンバー保険証の取得率をもう一回教えてもらっていいですか。

黒崎 晶さん
先ほど私のほうで御説明させていただいたのは、マイナンバーカードを保有している方で被保険証と連携している方というふうになるんですけれども、それが三鷹市では48.27%という形で、被保険者数が大体3万4,000人ぐらいなんですけれども、約半数の方が保険証とのひもづけを行っているというところでございます。
以上です。

金木 恵さん
今の答弁に若干補足をさせていただきますと、市としては、大体年度末ぐらいのマイナンバーカードの普及率は、おおよそ4分の3ぐらい、75%をちょっと超えるぐらいというふうに認識をしてございます。ただ、私どものほうには、そのうちどれだけマイナ保険証に連携をしているのかといった情報の提供はございません。基本的にはそれぞれの保険者さんのほうで把握をしているものになるので、実際の総体として三鷹市民がどのぐらい連携されているのかといったものについての情報提供は国や都からは特段下りてきていないのが現状です。
以上です。

ありがとうございます。分かりました。恐らく、マイナンバーカードは取得しているけれども、マイナンバー保険証は取得していないという方も多くいらっしゃるかと思いまして、いろいろな御意見がある中で、このマイナンバーカードに対する考え方というところでまず1つのハードルになると思うんですけども、その上で、また保険証というふうになってきたところで、どれくらいの方が入っているのかなと思ったんですが、そもそもこのマイナンバーカードにおいてのメリットといいますか、やはりこの辺のマイナンバーカードをどういうふうに使用していくことで、安全性はもちろんなんですけれども、こういった活用が広くできるですとか、そういったことを具体的に分かりやすく伝えていくことが、まずはこのマイナンバーカードの普及にもつながり、保険証に対しての理解も深くなると思うんですけども、やはりどうしてもマスコミだったり、いろんなところで、悪い情報のほうが多く出てしまう部分が多いと思いますので、その辺はちょっと理解を深めるような形で広報もしていただけるといいかなとは思います。
あと、先ほど部長のほうもおっしゃっていた、年齢によって保険証の時期が違うという点は、少し混乱を招く部分かなと思いますので、ここの部分をしっかりと分かりやすく、保険証と資格確認書ですとか、高齢者の部分ですね。年齢的に違う、ここをしっかりと広報等でやっていただければなとは思っております。この辺は具体的にスケジュールというのはもういろいろ決まっていたりしますでしょうか。

黒崎 晶さん
若干ちょっと前の質問の関連なんですけども、国のほうのデータでは、全国民のうち、マイナンバーカードの保有状況というのが全人口の約73%ぐらいですね。逆に言うと、27%の方がマイナンバーカードを取得していないという状況です。その中で、その73%取られた方の約78%、こちらの方がマイナ保険証の登録をしているという状況で、それで、先ほど私が57%とお答えさせていただいたのは、保有しているのが大体、先ほど金木部長がおっしゃったとおり、三鷹市の状況ではそうですけれども、国全体として、これは国民健康保険だけではなくて、全部の保険者になりますけれども、大体イメージとしては7割の方がお持ちになって、約8割の方がその中で登録をしているという状況です。
それで、委員御指摘の、こちらの加入者情報の通知の時期が違うことに伴いまして混乱を招く可能性がありますので、その辺りは広報、ホームページ等を通じて周知してまいりたいというふうに考えております。
以上です。

何度もちょっと申し訳ないんですけど、今のお話で、全国の73%がマイナンバーカードを持っていて、78%がマイナンバー保険証に入っているということでしょうか。
(「57%」と呼ぶ者あり)
57%ですか。分かりました。すいません。ありがとうございます。分かりました。そうですね。本当にこのマイナンバーカード、いろいろ意見あるかと思うんですが、災害時なんかにも本当にこれが活用された事例も多く出ていて、このやっぱりマイナンバーカードを通していろいろ管理できるということがいろんな事例に波及しておりますので、この辺のメリットの部分、もちろん情報、個人情報に当たるので、しっかりやっていかなきゃいけない部分もたくさんあると思うんですけども、今後のデジタル化というところでも、しっかりとその辺の認知を、市民の方にも分かってもらえるような広報活動のほうをよろしくお願いいたします。
以上です。

健康福祉部報告、本件を議題といたします。

養成講座のところは、昨年度、令和5年度は全部で36回開催をしております。

分かりました。結構頻繁に行っているということでしょうかね。ちょっと、いつやっているか分からないというので問い合わさせてもらったときに、まだ開催日程決まっていないという報告を受けたことが昨年ありまして、人数がある程度集まったら開催するという形ではないですか。

隠岐国博さん
地域包括の方に人を集めていただいたりというのは運用上なので、必ず何人いなきゃいけないとかいうわけではございませんが、やはりできるだけ多くの方に御参加いただきたいというようなやり方の中で実施させていただいております。また、キッズサポーターの関係も、地域包括のほうで学校と調整していただいて取り組んだりというところも含めまして、通年というのはそういった意味で、年間を通して広く養成させていただいているということで、ある一定の期間に集中して取り組んでいる事業ではないというように御理解いただければというように思います。

分かりました。通年というふうに記載あったので、ちょっとそこで、定期的に行っているのかなと思ったので、すいません、細かく伺ってしまったんですが、結構市民の方でも、両親でしたり、この認知症サポーター養成講座を受けたいというような声を聞きますので、市民の方にどのような形で講座を実施しているかというのを分かりやすく出していただけるとよいかなと思いますので、その辺、何か取組を考えられるようであれば、お願いいたします。

まさに認知症に関しましては、先ほど御報告の中でも、計画、条例というところを含めまして、これからますます市民の方に御理解をいただかなきゃいけないということにつきましては深く認識してございますので、その取組の周知というところには、今まで以上に、これまで以上に行き渡るように、地域包括とも連携、地域の皆様とも連携しながら、また、認知症サポーター養成講座を受けていただいた方からいろいろ広がっていくような取組に展開してまいりたいというように考えております。
以上でございます。

分かりました。よろしくお願いいたします。
最後に、どんぐり山の運用実績について何点かお伺いしたいと思います。こちらもまだ1年たっていないので、具体的にというところは難しいかもしれないんですけど、やはりどんぐり山も市民の方からすごく関心が高い事業になっておりまして、多くの方から、行ってみたいんだけどというような声を伺っております。先日、ちょっと私も問い合わせたところ、直接事業団のほうに連絡を取ってくださいというような対応で、事業団のほうと調整しているんですけども、まず令和5年度の市民の方の見学状況など、把握していたら教えてください。

申し訳ありません、ちょっと細かなデータはないんですが、かなり多くの御視察をいただいたというように認識しておりまして、多くバスの御利用もいただいて御利用いただいたということで、バスの利用も全てで33回ほど御利用いただきながら、研修、また視察というような形で御利用いただいておりますので、そういう意味では、まだお声が受け切れていないようであれば、しっかり対応できるようにしてまいりたいと考えております。また、生活リハビリセンターの部分につきましては、少しプライベートゾーンというようなところもございますので、ちょっと御見学というところは事前に少し調整が必要な場合もございますので、その辺も含めてしっかり調整させていただければと思います。

ありがとうございます。マイクロバスの利用状況についてもお伺いしようかなと思ったんですけど、同様なので、こちらは割愛させていただきますが、地域の、町会ですとか住協でしたり、結構団体の単位で行ってみたいという方たちの声も多く聞いておりまして、そういった方たち、ぜひマイクロバスもありますのでというような案内もさせてもらっているんですけども、実際行った方からの声みたいのは伺っていたりしますか。

やはり御不便な地域といいますか、そういったところからの利用としては、バスがあってよかったというような形で、やはりかなり利用も、乗り切れないぐらいの形で、1台ほかの車で来ていただいたりという運用の仕方もあるようですので、ここはしっかりと──人数が少ない研修なんかですと、5人とかでも利用していただいたりしていますので、そこは小まめにできているのかなと思いますので、そういった意味では、利便性を高めて、市民の方からも御満足いただけるような取組になっているかなというふうに認識しております。
見学の方からの御利用の声ということにつきましては、いろいろ、実際見学いただく際にミニ講座のようなことも開催しておりますので、やはり、施設を理解できるとともに、そういった少しスキルもつけられてよかったというような形でのお声をいただいたりというところで頂戴しております。
以上でございます。

ありがとうございます。高齢者の方から、やはり自分がいざというときにこういう施設が三鷹市内にあるということが安心につながるということで、関心が高いという方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひぜひ見に行ける機会というのを増やしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
あともう一点、このどんぐり山を運営している事業団の運営状況というのは、人材でしたり体制等、問題はないでしょうか。大丈夫でしょうか。

どんぐり山の運営に関しましては、令和6年度も指定管理料のところで夜間の勤務、夜間の関係を増やしていただいたりということで、体制としてはできるだけ充実を、議会のほうでも御予算を認めていただいて、体制をつくっているところではございますが、まだ始めたところということで、課題が見えてくるケースもあると思います。また、生活リハビリセンターにつきましては、いろいろな、先ほども御紹介しましたが、介護度によっても、やはり関わる職員というところも替わってくる可能性もございますので、そこは引き続き、市民の皆様の御利用をしっかりできるような体制、また事業団の職員もしっかりとした勤務体制が取れるようなことというのは必要と認識しておりますので、必要な部分については、また議会のほうとも御相談させていただきながら、運営に支障がないように努めてまいりたいというように考えております。

ありがとうございます。やはり半年少し運営していく中でいろんな課題がきっと出てきていると思うので、その辺、うまく連携といいますか、市のほうとの相談でしたり調整というのをしっかりとしていっていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

市民部報告、本件を議題といたします。

すいません。よろしくお願いいたします。ちょっと聞き漏らしてしまったかもしれないんですけど、もう一度確認をさせてください。三鷹市においてのマイナンバーカードの取得率と、あとマイナンバー保険証の取得率をもう一回教えてもらっていいですか。

黒崎 晶さん
先ほど私のほうで御説明させていただいたのは、マイナンバーカードを保有している方で被保険証と連携している方というふうになるんですけれども、それが三鷹市では48.27%という形で、被保険者数が大体3万4,000人ぐらいなんですけれども、約半数の方が保険証とのひもづけを行っているというところでございます。
以上です。

金木 恵さん
今の答弁に若干補足をさせていただきますと、市としては、大体年度末ぐらいのマイナンバーカードの普及率は、おおよそ4分の3ぐらい、75%をちょっと超えるぐらいというふうに認識をしてございます。ただ、私どものほうには、そのうちどれだけマイナ保険証に連携をしているのかといった情報の提供はございません。基本的にはそれぞれの保険者さんのほうで把握をしているものになるので、実際の総体として三鷹市民がどのぐらい連携されているのかといったものについての情報提供は国や都からは特段下りてきていないのが現状です。
以上です。

ありがとうございます。分かりました。恐らく、マイナンバーカードは取得しているけれども、マイナンバー保険証は取得していないという方も多くいらっしゃるかと思いまして、いろいろな御意見がある中で、このマイナンバーカードに対する考え方というところでまず1つのハードルになると思うんですけども、その上で、また保険証というふうになってきたところで、どれくらいの方が入っているのかなと思ったんですが、そもそもこのマイナンバーカードにおいてのメリットといいますか、やはりこの辺のマイナンバーカードをどういうふうに使用していくことで、安全性はもちろんなんですけれども、こういった活用が広くできるですとか、そういったことを具体的に分かりやすく伝えていくことが、まずはこのマイナンバーカードの普及にもつながり、保険証に対しての理解も深くなると思うんですけども、やはりどうしてもマスコミだったり、いろんなところで、悪い情報のほうが多く出てしまう部分が多いと思いますので、その辺はちょっと理解を深めるような形で広報もしていただけるといいかなとは思います。
あと、先ほど部長のほうもおっしゃっていた、年齢によって保険証の時期が違うという点は、少し混乱を招く部分かなと思いますので、ここの部分をしっかりと分かりやすく、保険証と資格確認書ですとか、高齢者の部分ですね。年齢的に違う、ここをしっかりと広報等でやっていただければなとは思っております。この辺は具体的にスケジュールというのはもういろいろ決まっていたりしますでしょうか。

若干ちょっと前の質問の関連なんですけども、国のほうのデータでは、全国民のうち、マイナンバーカードの保有状況というのが全人口の約73%ぐらいですね。逆に言うと、27%の方がマイナンバーカードを取得していないという状況です。その中で、その73%取られた方の約78%、こちらの方がマイナ保険証の登録をしているという状況で、それで、先ほど私が57%とお答えさせていただいたのは、保有しているのが大体、先ほど金木部長がおっしゃったとおり、三鷹市の状況ではそうですけれども、国全体として、これは国民健康保険だけではなくて、全部の保険者になりますけれども、大体イメージとしては7割の方がお持ちになって、約8割の方がその中で登録をしているという状況です。
それで、委員御指摘の、こちらの加入者情報の通知の時期が違うことに伴いまして混乱を招く可能性がありますので、その辺りは広報、ホームページ等を通じて周知してまいりたいというふうに考えております。
以上です。

何度もちょっと申し訳ないんですけど、今のお話で、全国の73%がマイナンバーカードを持っていて、78%がマイナンバー保険証に入っているということでしょうか。
(「57%」と呼ぶ者あり)
57%ですか。分かりました。すいません。ありがとうございます。分かりました。そうですね。本当にこのマイナンバーカード、いろいろ意見あるかと思うんですが、災害時なんかにも本当にこれが活用された事例も多く出ていて、このやっぱりマイナンバーカードを通していろいろ管理できるということがいろんな事例に波及しておりますので、この辺のメリットの部分、もちろん情報、個人情報に当たるので、しっかりやっていかなきゃいけない部分もたくさんあると思うんですけども、今後のデジタル化というところでも、しっかりとその辺の認知を、市民の方にも分かってもらえるような広報活動のほうをよろしくお願いいたします。
以上です。

子ども政策部報告、本件を議題といたします。

よろしくお願いいたします。まず、先ほど健康福祉部のときにもちょっと冒頭に確認させていただいたんですけども、この春から母子保健事業が子ども政策部に移管したことにおいて、子ども政策部で力を入れていく部分ですとか、大きな変化というのは何かありますでしょうか。

近藤さやかさん
これまで母子保健、健康福祉部にあったことで、もちろん連携して一緒にやっていましたし、ネットワークをつくって、母子保健とこれまであった子ども政策部の様々な部署でやっておりましたが、今回、組織が一体となることで、中身だけじゃなく、形としても切れ目のない支援がよりできるかなと思っていることと、かつ今回の組織改正で新たに子ども家庭課を筆頭課に設けて、その筆頭課の中に各子ども家庭支援センター、子ども発達支援センター、そして母子保健が1つの課にまとまりまして、かつセンター長も設けましたので、かなり機動的な体制になるので、かなり政策的なことにもより集中して取り組んでいけるかなというふうに思っております。
以上です。

ありがとうございます。その辺が特に今回の重点事項には記載がなかったんですけど、そういった下、進めていくということで、ありがとうございます。
体制をより強化したということで、保育施設係、保育支援課ということで、部署も細かく分かれたという点からもちょっと質問をさせていただければと思っております。
まず、2番目の子ども総合計画の策定に当たってなんですが、子ども・子育て会議、この方たちによっていろいろ審議されていくと思うんですが、子ども・子育て会議以外で当事者や関係者の意見を聞いたりというのは何か検討されていますでしょうか。

子どもの意見ということでいくと、先ほどの子どもの人権基本条例でもお子さんの意見、子どもの意見を聞きますので、両方というか、計画のことだけではなくて、子ども施策全体としての意見を聞きたいというふうに今のところ検討しているところです。

ありがとうございます。子ども・子育て会議が結構重要になっているなといつも感じているんですけども、いろんな審議に対して子ども・子育て会議の役割というのがすごく重要になっていると考えるんですけども、今までもいろんなお話の中で、様々な方に子ども・子育て会議に入っていただきたいというようなお話があったと思うんですが、今回も策定に当たって、子ども総合計画という大きな計画になりますので、より多く、幅広く話を聴いていただけるような体制を考えていただければと思っております。ありがとうございます。
続きまして、3番目の先ほどの在宅親子向け講座、プログラムの実施という部分で、先ほどの委員さんからもいろいろと質問あったことに対して、さらにちょっとお伺いしたいんですが、この親子向け講座、最初と最後に保育付講座を入れるということだったんですけど、この親子向けの講座というのは、具体的にどのような講座を考えられていますでしょうか。

池沢美栄さん
おおむね話している内容は、こいぬグループのときに保護者様にお話ししているのと同様の、関わりの中で子どもたちは大きくなっていく、その楽しさを子どもにも保護者の方にも味わっていけるといいですよねといったお話をさせていただく予定です。

ありがとうございます。このこいぬ・こねこプログラムが大変保護者の方に喜ばれているというお話をずっと聞いていまして、こういったところで拡充していくという部分で期待値があったんですけども、このこいぬプログラム、そういったところを広げていくという認識で。
(「はい」と呼ぶ者あり)
はい、ありがとうございます。分かりました。すごく保護者の方が子どもたちとの向き合い方に、やっぱり一本につながったという声を伺っているので、引き続き拡充のほうをしていただけるとありがたいなと思います。ありがとうございます。
続きまして、4番目の医療的ケア児の受入れ開始という部分で、4月からというふうに、学童ですね、なっているんですが、4月からどれくらい実際入られているかってありますでしょうか。

令和6年度においては、いわゆる医療的ケアを必要とするお子様、3名のお申込みがありまして、3名お受入れをしているところでございます。
以上です。

ありがとうございます。これから三鷹市の学童保育については、この医療的ケア児の拡充という部分で進めていくかと思いますので、この3名の方からということで、いろいろ御意見等を伺って、より体制の強化を進めていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
続きまして、こちらの別紙のほうの資料について、保育所入所状況について少しお伺いしたいと思います。先ほど具体的な数字は伺ったんですけれども、この保育所の利用率が増えているというお話があったんですが、未就学児、就学前の児童数の中で保育所の利用率が増えているというふうに認識しているということは、やはり幼稚園の部分というのが低下しているのと連関しているというふうに考えますでしょうか。

まさにおっしゃるとおりで、保育園の利用率が増えている、子どもが減っているのに増えているということで、幼稚園のほうはかなり減少傾向にあり、今、3歳以上の未就学児の方において幼稚園を利用される方の割合は2割を切っているところになっています。

ありがとうございます。例年、幼稚園の減少というのが課題にもなってきていて、こういった数字を見ても明らかだと思うんですけども、やはり今回、保育支援課が設立されたりですとか、より保育園のマッチングというところに力を入れていく部分だと思うんですけども、この全体的なバランスを見る中で、やはり幼稚園と保育園のバランスというのが極端にどんどん離れていく現状についてどう考えていくかというのも早急な対応が必要ではないかと思いますので、保育園のマッチングの強化と併せて、その辺も考えていただければなと思っております。
そうですね。今後、そういった──今回、新しく保育支援係という係ができたんですけども、今のこの現状を見て、保育支援課の役割というのはどの辺に重点を置くべきだと考えていますでしょうか。

保育支援課の目指すべきものというか、大切に考えていきたいことは、やはり子どもたちが、どこで、どういうふうに過ごしても、本当に幸せで、自分らしく生きていけるかといったところを大人がどれだけ保障したり、そこの環境を一生懸命つくっていけるところかといったところだと思います。保育の中身のところは、やっぱりその施設施設で特徴のあるものというふうにしてつくっておりますが、芯の部分、本当に子どもにとって大切なところ、大事に育てて、育んでいきたいところをみんなで共有したりだとか、そういったところを大事にしていきたいなというふうにして考えておりまして、各保育園にいろいろお邪魔をさせてもらって保育巡回をしたり、中身のところを補強していったり、あとは、制度的、または法的にしっかりとした環境が守られているのか、指導検査等を通して、法的にもしっかりしたものになっているのか、そういったところをしっかりと確認をしていきたいというふうにして考えております。

ありがとうございます。すごく丁寧に保育士の皆さんは接していただいているなと感じているところではあります。ありがとうございます。昨年も、今年度入園に当たっての保育園の応募において、やはり希望に沿えなかったというような市民の方の御意見をたくさんいただきました。何度かちょっと御相談もさせていただいたんですけども、やはりこの保育支援課のマッチングといいますか、お子さんに合ったいい園を選んでいくという部分では、いろいろ難しい部分はあるとは思うんですが、待機児童ゼロという国のこの指標に基づいたというところだけでは見えない、認証だったり企業主導型だったりというふうに割り振りはあると思うんですけども、やはりお子さんにおいて、あと保護者において、しっかりとマッチングができるような体制の強化をまた今年度もしていただきたいなと思っております。本当に最近はゼロ歳のときから皆さん幼稚園選び、保育園選びが始まりますので、いよいよ、もう今6月、7月というところで、入園の申込みは10月ですけども、もう既に動き出している皆さんもたくさんおりまして、いろいろ問合せ等もこれからますます増えていくかと思いますので、そういったところでもしっかりと対応していただけますようお願いいたします。
ありがとうございます。