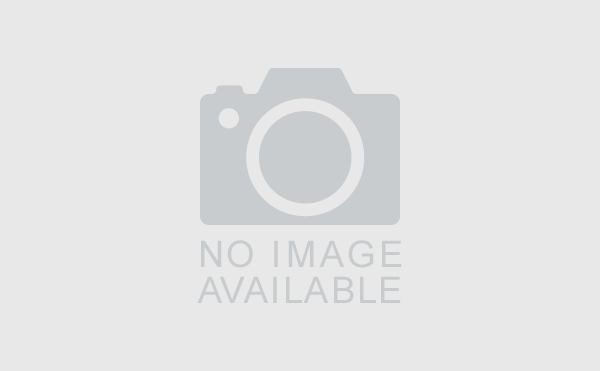令和6年2月7日 厚生委員会
2024年2月7日

健康福祉部報告、本件を議題といたします。
本件に対する市側の説明を求めます。

よろしくお願いいたします。それでは、まず障がい者計画のほうから質問させていただきます。今回のパブリックコメントを見て、やはり全体的に相談の充実というところに対してパブリックコメントが多いなという印象を感じております。やはり相談の充実というところは、もちろん今回の素案のほうにもしっかり入ってはいるんですけども、このパブリックコメントを見ていても、やはり不足していると感じている方が多いということで、そこがやはり大きな課題なんだなというのが、改めてパブリックコメントからも読めました。
それから、すみません、次に17番です。先ほどの委員さんからもあったんですけど、私のほうからは、今回のバリアフリーのまちづくりに関することなので、庁内連携が取れて、どういうふうにやっていくのかなというところを気になってはいたんですけれども、先ほどの回答から、まちづくりのほうと連携しているということが読み取れたんですけど、やはり三鷹駅前、多目的トイレやフードコートというのが不足のところで、こういった意見をよく聞いていますので、先ほど回答をいただいていたんですけども、まちづくり推進課ですか、庁内連携を取って個々に進めていただければなと思いました。
次に、40番です。40番になるんですが、こちらも多分恐らく子育て支援課、発達支援課との連携した回答になると思うんですが、障がい児保育というのは、医療的ケアだけではないと思うんですけれども、新事業として病児保育を行うことはできないだろうかという提案ですって、とてもいい提案ではないかなとは思ったんですけども、現行の体制によって一定の成果を上げていますので、現段階では、行政による派遣事業の実施は考えておりませんということで、この一定の成果という部分が、医療的なケアというのは三鷹市も実施はしているとは思うんですけれども、障がい児保育というところでは、保育園でしたり幼稚園でしたり、足りない部分がたくさんあるかと思われるので、この辺はどのように考えられているか、伺いたいと思います。

立仙由紀子さん
すみません、おっしゃるとおり、こちらのほうの所管が子ども政策部の所管になりますので、私のほうでちょっとお答えできる範囲ではないんですけれども、ただ、障がい児や医療的ケア児については、本人の支援だったり家族の支援というのも、医療的ケア児支援法なども成立しているところから、重要なところと私たちも認識しております。
その中で、本人への支援も必要ですし、また家族への支援も必要ですし、また、それに関わる方たちの、支援者の方の質や量の支援というところも必要なのかなというふうには認識しております。
引き続き、子ども政策部や教育のほうとも連携をしながら、そういった当事者、または家族にとっていいような形で支援を進めていきたいと考えております。

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
あと、最後になります。パブリックコメントを出すタイミングで、もろもろの数字というのを、今回でいろいろ追加になった部分があると思うんですが、やはりパブリックコメントを出すのにいろいろと準備段階で大変な思いをされて、皆さん出されていると思いますので、最新の情報でしたり最新のデータという中で、パブリックコメントを出されたほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。

おっしゃるとおり、私たちも最新の数値でお出しはしたいんですけども、こちらの数値を算出する基になるものが出てくるのが年明けとかになってしまいますので、このタイミングでのお示しになってしまいます。申し訳ございません。

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
次に、高齢者計画のほうに行きたいと思います。17番から21番。こちらに関しましても、先ほど課長さんのほうからお話があったとおり、やはり介護人材不足への対応についてのパブリックコメントが多いなというふうに思うんですけども、まさにこの辺について、どんぐり山に期待しているんだなというところも感じてはいるんですけれども、17番から18番、同じ回答がずっと続いておりまして、それぞれの方に回答する分にはあまり支障はないとは思うんですけども、三鷹市としてはこのどんぐり山、またこの自主財源に加えてというところからの、これ以上の部分というところは何か記載はなかったんでしょうか。

隠岐国博さん
まさにこちらにつきましては、いろいろな補助金等を活用していくということ、また改めての研修の補助事業というようなところも検討していきたいというようなところで、書かせていただいております。
また、どんぐり山においても、こことはしっかり連携していくという姿勢は変わらず持ってございますので、具体的なところについては、また検討を進めながらお示しできればというふうに思っております。

ありがとうございます。
関連しまして、63番に関して、同じようなどんぐり山に関してなんですけども、こちらに関しては、まだまだどんぐり山の市民に対しての周知ですとか、そういったものが届いていないのかなという印象も受けましたので、今後こういった介護人材不足でしたり、どんぐり山の機能をもっていろいろ対応していくということであれば、このどんぐり山に対しての周知、またその辺もしっかりと市民の方に知っていただくということが重要かなと思いますが、いかがでしょうか。

まさしく今回、こういった御意見をいただいたことによりまして、やはりまだ届いていない部分がしっかりあるというようなところも、逆に認識させていただいたところでございますので、しっかり社会福祉事業団と連携しながら、どんぐり山の機能を知っていただくということで、また市民の方に来ていただくような機会をどんぐり山のほうでも設けていくようなことも展開しながら、市民の皆様の施設としてしっかり育ててまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、25番、33番、72番もちょっと関連するんですけども──ごめんなさい、25番から行きます。25番、こちらも地域包括支援センターの負担軽減の部分です。今回、この計画の策定の背景と趣旨というところで、前期計画から引き続きであるとは思うんですけども、地域包括ケアシステム、ここに力を入れていくという中で、この25番の回答に関しては、国の制度改正等を踏まえて検討していきますということで、33番、70番についても回答がしっかりと書かれてはいるんですけども、やはり今後、ニーズでしたり、地域包括という、この重要性、必要性、今後さらに増やしていったり充実を図っていかなければいけないと思うんですが、市独自としてこちらも期待するところだと思うんですが、この辺も、もう少し深くあったらいいかなと思ったんですが、いかがでしょうか。

まさしく地域包括支援センター、地域の核となって動いているということは深く認識しているところでございます。そういった意味では、今後、高齢者もますます増えていくような状況、また多様に、認知症等の対応も地域展開が必要だというような認識の下に、今後体制についてはしっかり議論して、必要なところでの強化を図れればなというようなところで、現在、検討を進めているところでございます。
以上でございます。

ありがとうございます。
すみません、続きまして45番です。安心キーホルダーの登録の件なんですけども、こちらの市民意見の方からの、市の窓口の職員さんがキーホルダーの存在を知らない、包括支援センターの方も知らなかったというところなんですが、安心キーホルダー、駅前のほうの包括ではかなり充実していて、地域と密着してこの安心キーホルダーの促進を図ってきたんですけれども、ちょっとやはりこれは残念な意見だったなというふうに思っています。
やはり、ここも地域包括センターと絡むところではあると思うんですが、安心キーホルダーの徹底というところをしていただいて、登録会などを行うなどというふうに書いてあるんですけども、こういう意見が来るということは、やはりちょっと徹底が不足だったのかなと思いますので、こちらもよろしくお願いします。
最後に、41番なんですけれども、先ほど課長のほうからも少しお話がありまして、こちら、直接的でなく、体制づくりに関する内容だと思いますというようなお話があったんですけども、福祉住宅については、丁寧な説明、これは、これまで支えてくださったワーデンさん含め、またそこに住む方たちに対しても丁寧な説明が必要だなと、直接的には関係ないかもしれないんですが、こういった御意見が出るということは、しっかりと丁寧な説明をしていく。今後、こういう体制になっていきますということでなく、このような背景でしたり、本当に私も下連雀のピアさんなんかに行くと、ちょっと依存しているような方たちもたくさんいらっしゃいますので、段階を踏んで変化していく、変えていくということだと思うんですが、この辺も丁寧に対応していただければと思いますが、いかがでしょうか。

小嶋義晃さん
福祉住宅につきましては、やはり今までのいろいろ経過がございます。そうした中で、御入居されている方、ワーデンとしてお願いをしている方、オーナーさん、それぞれありますので、見直しの方向性によっては、しっかりと適宜情報提供するなり御相談に乗るなり、丁寧な対応にはしっかりと努めていきたいと考えています。
以上でございます。

よろしくお願いいたします。
以上になります。

生活環境部報告、本件を議題といたします。
本件に対する市側の説明を求めます。

よろしくお願いします。本当にこのコミュニティ創生、この過渡期においてすごく重要で、難しい問題の中で、必要なものは全部入っているなということを感じたんですけども、パブリックコメントで、5番から7番、このコミュニティ活動の拠点というところ、これは市民の意見に関しては、特にコミュニティ拠点ってコミュニティ・センターというのはエリア制があったと思うんですけども、何かこれはエリアというのを確認して意見を聞けたりはしているんでしょうか。どこのエリアの方といいますか。
ほかのエリアを使っているということであれば、もちろんそうだと思うんですけど、コミュニティ・センターはエリア制があると思うので、この意見がどの辺の方か確認した上で意見を収集できているかという。

パブリックコメントでそこまでの個人判別というかはしておりません。お名前等があるので、知っている人がいれば、この人知っているなというのはあるんですけれども、そこまでの判別をした回答という形にはしてございません。

ありがとうございます。やはりコミュニティ・センターは本当にエリアによって使い方が異なっている部分かと思いますので、このエリアによって大きく活用方法が違う中で、どういったターゲットに、どういったものが必要かというのは変わってくるのではないかなというのを受けましたので、その辺も分かると、政策により反映しやすいのかなと思いました。
11番、計画に盛り込みますということで入っているんですけれども、これは、庁内各部署が常に念頭に置いて連携していくということなんですけども、例えば社協さんですとか社会福祉事業団ですとか、そういったところ、いろんな関係団体との連携というのはもちろんそうだと思うんですが、特に市のいろいろな施策をやっている、そういった事業団、社協なども連携していくということがあったら、よりいいのかなと思いましたが、いかがでしょうか。

今、委員さんのほうでおっしゃっていただいたことというのは、私どものこの方針の核になる考え方のところでございますが、きちっと分かるように表記されているかというところはもう一回点検をして、もし不足しているようであれば追記をするという対応をさせていただきたいと思います。

ありがとうございます。
同じく23番もそういった視点なんですけども、地縁型コミュニティとテーマ型コミュニティの意味が不明確なのでというところの点で、同一団体でも複雑に混じり合っていることで、本方針であえて厳密には定義をしていませんということなんですが、ここも、やはり横のつながりの部分かと思いますので、いろんな支援団体、地域活動をしているところというのは社協さんとのつながりがとても大きかったりですとか──協働センターも含めてなんですけども、そういったところがもう少し入り込むと、よりイメージがしやすいのかなというところを思いました。活動している方は特にイメージがしやすいのかなというふうに思いました。
以上です。

申し訳ありません。先ほど、スケジュールの件なんですけども、令和6年2月中旬の住民協議会と学識者等にヒアリング、この住民協議会というのは、役員さん向けに説明という形でしょうか。

ほぼ役員会にお邪魔をして、御説明をします。蛇足ながら、前回はこの方針全体のことを御説明したんですが、ちょっとやっぱりボリュームが多過ぎるので、今回は、コミュニティ・センターと住民協議会に関わるところを、本文を使って御説明をしようと思っています。

ありがとうございます。今までも役員会向けの説明というのは何度もしていただいていると思うんですけども、やはり役員の皆様、御高齢なところも多くありまして、そこに属している部員の皆様までに全く周知がされていないという現状があるなというのをすごく感じてはいたんですけども、なかなかそこから伝達をしてという──難しいとは思うんですけど、役員さんじゃない方たち、子育て中のママたちとかパパとかいたり、広く、年齢も幅広く関わっている方もいらっしゃるので、何かちょっとこういう形がいいというのはすぐ言えないんですけど、役員さん以外にも何か周知ができる方法があると、理解が深まるかなと。
皆さん、今後どうなるんだろうという心配はしているんですけども、どうしても役員さんからという形だと思うんですけど、そこに付随している部員さんたちまでには、なかなか情報が。それは、事務局のほうが何かするしかないかもしれないんですけど、実際、住民協議会にいて、役員だったから情報を知れたけども、ほかの方たちは知らないという現状があったので、そういった子育て世帯とか、なかなかそこに来れない方たちにも、本当に重要なコミュニティのことなので、知るすべがあるといいなと思います。
以上です。

川鍋章人さん
その部分については、住民協議会の役員さんを通じてというよりは、市の広報であるとか、そういったものを通じて広く市民の皆さんに周知していくということを行っていくということになると思います。
以上でございます。

そうしましたら、じゃあ、またそういった広報紙とかに掲載されるというタイミングがあるということですかね。分かりますか。

こちらの方針、それからこの後続く、推進計画という名前になるかどうかは別として、ここに挙げたものを実現していくための計画については、今後も情報発信はしてまいります。
それと、あと役員さんというか住民協議会として、私たちからの働きかけ以外に、住民協議会の中で考え方を共有していく働きというのは、やはりどうしても必要だろうと思います。それがなければ、地域で、そこでコミュニティの核になっていただこうと思っているわけですから、やはり御自身たちでももちろんやっていただくんですけれども、先ほど部長が申し上げたとおり、私たちとしても広めていく努力はしてまいります。

ありがとうございます。今回、パブリックコメントについても、恐らく前回のとき、私、関係団体のほうにも直接的に連絡してほしいというようなお話をさせていただいて、直接的に連絡いただいていたようなので、広くそういったコミュニティに関わる団体ですとか関係者に御連絡いただいた上で、回答が少なかったのかなというのはお察ししたところなんですけども、幅広く知っていただいて、これから、本当にコミュニティのつくり方は難しいので、そういった子育て世帯、あと参加できない方々にも知っていただけるようにお願いできればと思います。
ありがとうございます。