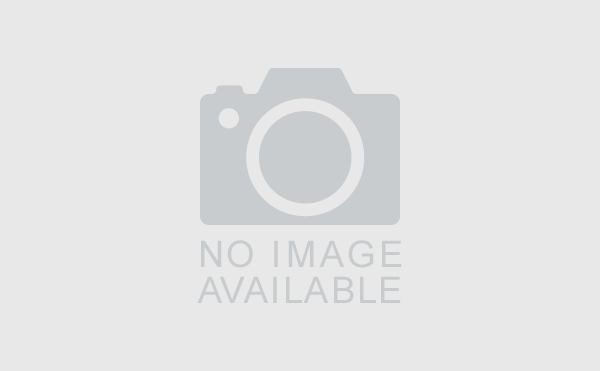令和6年9月10日 厚生委員会
2024年9月10日

議案第34号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、本件を議題といたします。
本件に対する市側の説明を求めます。

原島法之
おはようございます。よろしくお願いいたします。本日は、議案第34号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例、こちらにつきまして市民部から御説明いたします。
本条例改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正、こちらに伴いまして紙の被保険者証が廃止されることから、国民健康保険条例につきまして規定整備を行うというものです。
それでは、詳細につきまして、お手元の厚生委員会審査参考資料に沿って、担当の黒崎課長より御説明させていただきます。

よろしくお願いいたします。それでは、私のほうからは、審査参考資料に基づきまして御説明させていただきます。
かがみをおめくりいただきまして、説明資料の1ページ、三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例のあらましでございます。冒頭、部長から御説明がありましたとおり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律、略称マイナンバー法により被保険者証が廃止されることから、国民健康保険条例の改正を行うものでございます。
今回の改正の趣旨は、国民健康保険の被保険者証が12月2日に廃止になることから、被保険者証の文言の削除をするものでございます。現行の条例では、国民健康保険条例のみこの文言の記載があることから、項目1のとおり、項ずれを修正するとともに、第24条の虚偽の届出等に対する過料における被保険者証の文言の見直しを行うものでございます。
項目、2項目めの施行期日は、現行の被保険者証が廃止となる12月2日です。
その他、項目3です。令和6年12月1日時点で被保険者に交付をしている国民健康保険の被保険者証は、転職等により保険者が異動した場合及び転居等により被保険者証の記載事項に変更があった場合を除き、12月2日以降も、有効期限である原則令和7年9月30日まで引き続き使用が可能というふうになっております。
マイナ保険証への移行に向けたスケジュールにつきましては、6月の厚生委員会でも御報告をさせていただきましたが、参考に表を載せさせていただきましたので、御確認をいただければと思います。
説明資料の2ページ以降につきましては、三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表をつけさせていただきましたので、御参照いただければと思います。
説明は以上でございます。

委員長(大城美幸さん) 市側の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方。

よろしくお願いします。先ほどからいろいろとお話しいただいているんですけども、やはり移行に関する皆様の御不安というところで、チラシ、ポスター等は特に考えられてないというお話だったんですけども、恐らく窓口での対応が増えることが想定されると思うんですね。やっぱりこのマイナンバー保険証に関しては、不安というところからいろいろな御意見が出ているかと思いますので、もちろん現場の状況ですとか、健康福祉部から情報が市民課のほうに来るというようなお話があったと思うんですけども、この辺、やはり始まった当初は一緒になって現場の状況などを吸い上げていただいて、どのような御不安でしたり、どのような対応をなされているかというのを聞いていただいて、随時改善というか、分かりやすい説明と、あと心配を払拭していただくような、厚生労働省なども各医療機関にマイナ受付のステッカーやポスターを貼っていて、医療機関や薬局に、マイナ保険証はどういうふうに安全が保たれているかですとか、いろいろな情報というのを発信しているので、ポスターやチラシというのはされないということだったんですけども、窓口、受付に来て、そういった御不安を払拭するためにも、そういった厚生労働省から出ているポスターだったり、そういうのを貼っていただくことで窓口の対応の軽減になったりということも考えられますので、ぜひその辺を丁寧にといいますか、不安という部分をこういう、先ほど課長からもおっしゃっていただいたひもづけの仕組みですとか、そういったところをしっかりやっぱり認知していただくことが、こういったいろいろな御意見でしたり、トラブルの解消につながると思いますので、やはり国なんですけども、三鷹市としてもやはりそこら辺はしっかりと、この安全性ですとか、御不安の払拭というところで、これから移行に向けて取り組んでいただきたいなと思います。
厚生労働省のほうでは、マイナ保険証が使える医療機関、薬局はどんどん増えていて、こちらのデータを見ると、96.4%、マイナ保険証が使える医療機関、薬局ということで数字が出ております。薬剤師会ですとか、現場の声を聞きますと、やはりマイナポータルのそういったカードリーダーを設置していくという方向で進めているというふうに聞いておりますので、その辺の現場との連携というのも、どうしてもやはりいろいろ御心配があると思いますので、現場のほうも混乱することが考えられますし、健康福祉部からということではなくて、一緒になって対応していただくことがいいんじゃないかなと思っております。先ほど課長のお話からも、三鷹市のほうで数字はきちっと把握していないけども、東京都の集計で約50%ぐらいは保険証の加入というような数字も先ほどいただきました。これもやはり、これからDX化していく中で、どういうふうに三鷹市としても対応していくかということを明確にしていくことで、この申請率というのも上がっていくのかなと思いますので、いろいろ御意見があると思うんですが、市民の方の不安というところでできる限りのことをちょっと対応していただければなと思っております。窓口の対応とかというのは、何かこの期間強化するというのは考えていますでしょうか。

保険証廃止前後につきましては、問合せ等いただくことは想定しておりまして、こちらにつきましては、事前の広報、あと、今御指摘いただきましたけれども、医療機関等にはポスターとか掲示がされておりますが、市の窓口のほうでも分かりやすくできるような対応は検討してまいります。

金木恵さん
先ほどの答弁の中で、確かにポスター、チラシを作成しないというような答弁をしているんですけれども、市の経費で独自に作成はしないという趣旨ですので、もちろん国のほうで様々、機を捉えて作成していただいているものについては最大限有効に使っていくことが前提であるということをまず申し添えさせていただきたいというところと、あとやっぱり窓口にはこれから多分御不安な方がいらっしゃると思うんですよね。カードは作ったけど、この後どうしたらいいか分からないとか、どうするのというような方も一定程度窓口にはいらっしゃるでしょうから、そういった方がもし連携を御希望するのであれば、そういったことがお手伝いできるような体制をどうやって整えていこうかとか、現行、マイナンバーカードセンターでもそういった御支援はさせていただいていますけれども、その他、それをどこまで多様化できるかといったところも課題であるというところは認識をしているところです。やはり一番皆様が御心配されているのは、本当にお医者さんにかかれるのという、多分そこだと思っているんですよね、やっぱり。自分たちの生活に何の影響があるのかというところが一番の御心配事だと思っていますので、マイナ保険証を持っていても持っていなくても、このまま引き続き安心して医療機関にかかれますよということを一番の主眼として広報を進めていきたい、そのように考えております。

ありがとうございます。あと、やはり保険証の対応をする現場の皆様が今までと変わった対応というのをいろいろと、現場のほうにもたくさん来ると思うので、現場とも連携というところで、皆さんいろいろ情報は得られていると思うんですけども、現場の皆様も対応がスムーズにできるように何か広報していただいたりとかということをしていただくと、現場の皆さんは御不安にされていると思いますので、その辺も少し軽減できるのかなと思います。
すいません。以上になります。よろしくお願いいたします。

1件だけ確認させてください。現場の不安、今後の対応の煩雑化という、大変御苦労されているというのはお話を聞いていて分かったんですけども、これ、やはり先ほど、システムを整えていくためにゆっくり進めてほしいとお話があったんですけども、現行の保険証から資格確認書という形で、紙の保険証はなくなるんですけど、この資格確認書になることでやはりよりこの業務の煩雑化というのは可能性としてあるということでお考えですか。

三澤克己さん
ありがとうございます。ちょっと正直言うと、まだ、今うちの国保のところで把握している段階でもかなり煩雑になるだろうなという、今後の事務手続がですね。例えば、私たちの事務所の窓口業務に関してもかなりちょっと、いろんな、例えばマイナ保険証の登録をしているかしていないかというところをちょっと、うちのところではカードリーダーがありませんので、一人一人に口頭で確認するしかないんですけども、そういったところも含めて、かなりきめ細やかな対応が今後、資格確認書が発行されたとしても、そこのところも含めて一個一個確認していかなければならないところが、現行の保険証だけよりもちょっと増えていくのではないかなというふうに今想定はしているところです。

分かりました。ありがとうございます。
以上です。

生活環境部報告、本件を議題といたします。
本件に対する市側の説明を求めます。

垣花 満さん
厚生委員会、生活環境部からは行政報告を1件させていただきます。「三鷹市コミュニティ推進計画2027(仮称)」の策定に向けた考え方についてです。
説明につきましては、担当の鎮目部長のほうからさせてよろしいですかね。

鎮目 司さん
私からは、三鷹市コミュニティ推進計画2027(仮称)の策定に向けた考え方について御説明します。お手元の資料1を御覧ください。
番号1、計画の目的です。この計画は、令和6年3月に策定した三鷹市コミュニティ創生基本方針で整理した市のコミュニティの現状やコミュニティ行政の課題を踏まえ、市が目指す地域の姿の実現に向けて、基本方針で定めた4つの施策の柱を踏まえ、重点的に実施する個別事業や指標及び数値目標を定めることを目的とします。
次に、番号2、計画期間です。今年度策定、改定を予定している庁内各部の他の個別計画と同様に、令和6年から令和9年度の4年間といたします。
次に、番号3、計画策定の進め方です。計画策定に当たり、今回お示しする骨格案を基に、住民協議会、町会・自治会、テーマ型コミュニティ、NPO法人みたか市民協働ネットワークや学識経験者へ意見聴取を行います。また、パブリックコメントによる市民意見の募集や庁内各課及び外郭団体への意見照会、三鷹市市民参加でまちづくり協議会(通称マチコエ)からの政策提案の内容を踏まえながら、市内のコミュニティや関係団体、市民の皆様等の意見を反映し、策定作業を進めてまいります。
次に、番号4、今後のスケジュールです。令和7年3月の策定に向けて、資料に記載のとおり、骨格案と計画案の段階に応じて、議会報告、意見聴取、パブリックコメント等を丁寧に進めてまいります。
次に、番号5、三鷹市コミュニティ推進計画2027(仮称)骨格案でございます。別紙1の骨格案の冊子を御覧ください。
初めに、冊子のレイアウトについてです。本計画では、より伝わる紙面レイアウトといった視点により、各団体等への内容説明や策定後の閲覧性を高めるため、図や表、グラフが見やすく、またデジタルメディアと親和性の高い横長のレイアウトといたします。
資料、1ページをおめくりください。左側に市長の挨拶、右側に目次となります。本計画は第1章から第3章までの構成とします。第1章では、計画の基本的事項として、位置づけや策定経過、目的、計画期間を定めております。第2章では、今年3月に策定したコミュニティ創生基本方針の概要として、市のコミュニティの現状、コミュニティ行政の課題、今後の基本的な考え方、そして4つの施策の柱について記載します。第3章では、目指す地域の姿の実現に向けた施策の展開として、本計画が目指すビジョンと4つの施策の目的について詳細に説明をし、より実効性の高い計画とするため、複数の指数及び数値目標を定めます。巻末には施策の体系図を掲載しております。
1ページおめくりください。ページ左側には、本計画をお読みいただける方に計画が目指すイメージを共有していただくため、背景に市内の町会や自治会活動の様子を組み写真でレイアウトし、メッセージを掲載したメッセージページを設けております。右側からが第1章となります。
1ページおめくりください。左側、2ページ、計画の位置づけです。こちらは、今年3月に策定した三鷹市基本構想と6月に策定した第5次三鷹市基本計画、そして個別計画である本計画との位置づけを示すものです。
右側、3ページには本計画策定までの経過を、これまでに整理した基本的な考え方、論点整理、基本方針を踏まえて、実行計画である本計画を策定する流れを段階的に時系列でお示ししております。
1ページめくり、4ページを御覧ください。左側、計画の目的です。本計画の目的を、三鷹市が目指す地域の姿の実現に向けて、コミュニティ創生基本方針で定めた4つの施策の柱を具体化する計画とし、重点的に実施する個別事業や指標、数値目標を定めることとしております。
右側、5ページ、計画期間です。さきの説明のとおり、庁内の他の個別計画と同様の考え方によるものです。
1ページおめくりいただき、6ページを御覧ください。第2章、コミュニティ創生基本方針の概要です。
この後、右側7ページから12ページにかけましては、基本方針からの内容の抜粋となりますので、詳細な説明は割愛させていただきます。
それでは、ページを飛んで13ページを御覧ください。右側、第3章、目指す地域の姿の実現に向けた施策の展開です。
1ページおめくり、14ページを御覧ください。先ほど計画の目的で記載のあった、本計画で目指す地域の姿の説明となります。こちらは本計画のビジョンとなるもので、基本方針でお示しした、現代のコミュニティは多様化しており、一元的に定義できるものではないこと、またコミュニティは顔見知り関係から始まる様々な集まりであること、そして活動する市民のエネルギー源は楽しいやうれしいといった感情がなければ継続が難しいことといった内容を踏まえたものとなっております。本計画のビジョンとして、あえて目指すコミュニティの姿とはせずに、多様なコミュニティがそれぞれの違いを尊重し、緩やかにつながり合う地域とし、イメージ図にあるように、既存のコミュニティの枠組みを超えて、個人や団体が網の目のようにネットワークを形成し、連携、協働する地域づくりを目指すとするものです。
右側の15ページから資料18ページにかけましては、4つの施策の柱の目的をそれぞれ詳細に記載しております。
それでは、資料19ページを御覧ください。こちらは施策の達成度を測る指標及び数値目標を4つの施策ごとに複数設定しております。
1ページおめくりいただき、20ページを御覧ください。4つの施策の柱と19の個別事業の施策体系図となります。個別事業の事業名は現時点の案ではございますが、今後の意見聴取等を反映し、次の計画案の段階で詳細をお示しする予定となっております。
説明は以上となります。

よろしくお願いいたします。もう本当にこれまでのこのコミュニティ推進計画に行き着くまでのいろいろなヒアリング等、ありがとうございました。7ページの三鷹市のコミュニティの現状という部分で数値化していただいているんですけども、ここに、あえてかもしれないんですが、世代、年齢別というか、そういったことが入っていなくて、例えば、地域で何かしらの活動をしているか、していないが74.9%、これ多分世代間によってすごく違いが見えてくる部分かなと思っていて、この4つの指標に年齢的なところが1つもないんですけども、今このコミュニティの現状の中での大きな1つの課題としては、やはり生活の変化でしたり、世代間で地域との関わり合い方の変化というのがあるので、もちろんもともとの基本方針のほうには記載はあるんですけども、そこの世代間での地域コミュニティとの関わり合い方というのは大きなポイントになるのではないかなと思ったんですが、これをあえて入れてなかった何か理由とかってありますでしょうか。

ただいま7ページのコミュニティの現状について、世代間の違いが分かるような表し方がいいということで、御質問いただきました。ここにつきましては、大変ごもっともだと思います。今後の計画の段階で適宜検討させていただいて、盛り込めればと思います。ありがとうございます。

ありがとうございます。そうですね。やっぱりここが一番ポイントかなと思います。関わっている世代は大変関わっていますけど、やはり子育て世帯とか、あと仕事を辞められた男性の方ですとか、地域にどう関わっていったらいいのか分からないという方がいるよというのを共通の意識として課題を持つというのは必要かなと思いますので、よろしくお願いします。
あと、基本方針、抜粋ということなんですけども、11ページの、多様なコミュニティが生まれ、連携、成長していく仕組みということで大きな項目が8つ挙がっているんですが、この多様なコミュニティというのも、恐らくこのコミュニティの在り方というのが多様だということなんですけども、目的別でまた多様なコミュニティの対応の仕方が変わってくると思っていまして、例えば地域の課題を解決するためのコミュニティ、また趣味を一緒にやるコミュニティ、交流するためのコミュニティ、スキルアップをするためのコミュニティということで、多様なといっても、目的別で考えていくようなコミュニティがあると思うので、それはまたその解決方法ですとか対応方法も変わると思うので、その辺もちょっと検討材料といいますか、意識していただけたらありがたいなと思います。
次に、14ページなんですけども、ここが本当に、三鷹市コミュニティ推進計画2027という、目指す地域の姿、これまでは住協とか町会・自治会という中で、今回、緩やかにつながり合う地域という、ここが大きなまたポイントになると思うんですけど、この今までの住協とか町会という、組織というか、ある程度固定化していたところから、緩やかにつながっていって、誰でも参加していいですよというふうに見せていくというところで、この後の施策の目的につながっていくと思うんですけども、さきに書かれていたように、このコミュニティは行政が適度に関与しながら政策を展開する必要があるという上で、行政として、今回のこの施策のように、コミュニティ・センター、住協、デジタル、中間支援というふうに施策を展開していきますよというところだと思うんですけど、市民の心といいますか、市民の意識が動いていかないと、ここにも乗っていけないということに対して、どのように政策に盛り込んでいくと考えているのか、伺いたいです。

市民の機運醸成をどうしていくかみたいな御質問というふうに捉えさせていただきました。これ、行政だけで、行政が制度をつくると市民がそういう機運になるか、そういうことは全くないですよね。私たち、今やはり、今まで例えば協働センターとか、住協さんとか、町会さんとか、様々なテーマ型コミュニティさんとお話をしてきて感じることで、やっぱり市民同士が刺激し合って高めていかないと広がっていかない。例が適切かどうか分かりませんけれども、例えば、おうちのコンポストの、いわゆる段ボールコンポストみたいなものの運動も見ていると、やっぱり市民同士で高め合っていってて、じゃあ、行政は何ができるかというと、それをしていくときの会場だとか、何か支援の方法、要は環境づくりといったものがメインになってくるのかなと思っておりまして、やはりできるだけ多くの市民や活動している団体が知り合ったり、何かを始めていく環境をつくって、そこで盛り上がっていく。緩やかなつながりであったり、少し厳しいつながりであったりすることもあるかと思いますけれども、そういった場を提供していく。そこに、先ほど人材育成のお話もありましたけれども、ただ緩やかにわあっといるだけだと、なかなか形になっていかないので、例えがこれまたいいかどうか分かりませんけども、豆乳の中ににがりを落とすような、少し固めてあげるような、そういうことをしてあげられるコーディネーターという者を養成していくのがいいのかなというふうに思っています。結構時間のかかる話だと思うんですが、先ほどの中間支援と同じように、まち中に様々な支援してくれる人がいっぱいいて、その人たちを基点にいろいろな活動が広がっていくということを目指して、こういった図を描いているところです。
以上です。

ありがとうございます。やはり本当に、地域の方たちが目的を持って集まったところにコミュニティが生まれてくるというところだと思いますので、そうやって本当、住協とか町会という、既にある組織の中に入っていくというところからまた一歩踏み込んだ、この緩やかにつながる地域というところで進んでいくという、政策の目的としては、コーディネーターですとかデジタル活用というところで行政が支援して、それを相乗効果を上げていくというところが分かるんですけども、やはり一番最後の指標も、先ほども御指摘ありましたけど、まずは整備、環境を行政のほうで整えながら、最終的に市民の地域活動に参加したいと感じている割合というのを伸ばしていくというところがゴール地点だと思いますので、本当にいろんなやり方をしながら、試しながらというところだと思うんですけども、この30%というのはどういった点で出された数字になりますか。

実はこの30%、地域コミュニティやコミュニティ活動に参加したいと感じている市民の割合についてですけれども、こちらの数字につきましては、第5次三鷹市基本計画で設定している指標となっておりまして、そちらと合わせているところでございます。実際に数値としてはハードルは高いなとも思うんですが、先ほどの御質問にもちょっと関連するんですけれども、委員おっしゃるように、いわゆる仕組みですとか施設整備ですとか、そういうものを行政がやり、そして中間支援ということで進んでいくんですけれども、機運醸成も含めて、やはりそれぞれのコミュニティの目的ってすごい大事だと私たちも思っています。それと同時に、やはりキーマンとなる人をいかに見つけ出せるか、その方々と共感して一緒に歩みを進められるかというのがすごくキーになってくるのかなというふうに今、関係団体とのヒアリングの中でもそこが一番の話題になっていまして、そういうものがうまくいけば決して難しい目標じゃないのかなということで、なるべく前向きに進めていきたいというふうに考えているところです。

ありがとうございます。よろしくお願いします。
最後に、先ほども出ていたんですけども、20ページの施策体系図、ここに先ほど鎮目部長がおっしゃっていた地域活動の見える化。私自身、地域活動をずっと長年していて、なかなか行政との連携というのはできませんでした。地域活動はいつ終わるか分からない、また変わるか分からないという点で、なかなかそういった連携というのが難しくて、市のそういった広報紙ですとかにも掲載したりというのがすごく難しくて、なかなか私たちの活動というのをほかの人に知ってもらう機会というのは、自分たちでどうにかしなきゃいけないという現状がずっとあったので、本当にいろんな活動が見えることによって、そういう活動だったら私も参加したいという方々、たくさんいらっしゃると思うので、ぜひこの地域活動の見える化というのをしっかりとやっていただけると、活動を頑張っている方々にとってもそうですし、やはり、どんな活動があって、どういうふうに参加していったらいいか分からないという方も多く聞くので、その辺のハードルを下げるという部分でも、こういった情報の見える化、重要だと思いますので、ぜひお願いしたいと思うんですけども、具体的にどのようなことを考えているか、教えていただいてもいいですか。

地域活動の見える化についての御質問にお答えいたします。個別事業の内容は、この後の計画案で詳細はお示しするところなんですが、今現時点でこちらで検討している内容としましては、例えばマップ上に既存の施設、地域コミュニティの拠点となるべき施設がどういうものがあるのか、また別のマップではどういった団体がどういう地域で活動しているのか、そしてそこに地縁型だけではなくて、テーマ型を載せたり、そういうことがデジタルメディアを使うと比較的いろいろな視点で重ね合わせて見ることができるのかなと考えていまして、それを紙媒体でやってしまうと、数か月もすると、またその情報がリアルじゃなくなったりしますので、そこはうまくデジタルメディアを活用しながら、今現在三鷹で活動している団体、どういう団体、どういう目的を持った団体がいて、自分が住んでいるところの近くはどういうものがあるのか、なかなかそこをコミュニティ団体の枠組みを超えて横串で刺したような形で見えるものが今現在あまりないものですから、そうしたところの一助になるような取組を進めていきたいと、そのように今検討を進めているところでございます。

ありがとうございます。
あと、前後しますが、住民協議会の在り方検討委員会ということで、長年いろいろ検討されてきたと思うんですけども、今後の住民協議会、行政との連携役や地域のコーディネーター役を担える体制を整備するというふうに記載があるんですけども、やはり住協、長い歴史がある中で、ここ、新しい仕組みをつくっていくというのは相当大変なことだと思うんですが、その辺についてはどのようにまた新しい体制づくりを考えているのか、お伺いします。

委員さんおっしゃっていただいたとおり、大変難しい課題かなとは思っておりますが、ここ2年ぐらいの動きを見たときに、やはり行政と住民協議会との関係性というのがかなり変わってきたなというふうに感じています。というのは、やはり私たち、在り方検討委員会もそうですし、事務局長さんたちが集まる事務局長会議というのもあります。また、7つの住民協議会の会長さん副会長さんが集まる住協連絡会というのもございますが、そういったところへ私たちも積極的にかなり関与するように、ちょっと叱られるぐらい口出しをしてみたりとか、そんなこともしているうちに、お互い何を考えているかということが少しずつ分かってくるようになったんじゃないかなと思っています。また、最近のコミュニティ創生課のほうでの取組として、まず、今回、住協のデジタル化を進めるに当たっては、職員さんを分担して、全住協の職員さんが様々なテーマでワーキングチームに入って主体的に動くというような取組をつくってやっております。これ、まちづくり三鷹さんと組んで、そういった仕組みをつくろうということでやっておりますが、どういったホームページがいいのかとか、どういった予約システムをつくったときにどういう問題が起きるのかとか、今、7住協ばらばらのルールですから、そういったものをどういうふうに統一していこうかとか、そういったことを、市から言われて、ただ決まった形でやってもらうのではなくて、住協さんと市と話し合いながら決めていくような、そういったやり方ができてきているんじゃないかとすごく期待しているところです。こういったものを続けていく中で、今後、法人化ですとか職員の一元雇用ですとか、もしかしたら人事異動とか、そういったものも含めて様々な課題がまだまだあるわけですけれども、そういったものに前向きに取り組んでいけるんじゃないかなというような反応を感じているところです。
以上です。

ありがとうございます。住協もやはり会長さんですとか役員の方々、地域の重鎮といいますか、長年地域で頑張られている方がたくさんいらっしゃる中で、若い世代が入っていくというところの、そこがすごく難しい点かなと。どこまで行政が踏み込むかというところになると思うんですけど、そこの循環するような仕組みみたいなのがあると、今までのそこの地域のいろんな在り方とか、いろんなことを継承していけると思うんですけど、今だと、その方がいなくなると、ぷつっと分からなくなるというような状況もありますので、住協は恐らく学校とか幼稚園とか、地域の近隣とも連携もあると思いますので、今もそういったところから役員さんが出てはいるんですけど、そこから住協の役員になるということはないので、やっぱりそこを循環していくような仕組みもサポートしてもらえると、なかなか本人たちは言えないですので、本当に長くやられる方に対して、住協の中の関係性といいますか、組織の体系というのも何かサポートしてもらえるともっといい形で回るかなと思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。

2つの側面からやっぱりアプローチが必要なのかなと思っているのは、1つは、おっしゃっていた仕組み、制度ですよね。強制的に少し入れ替わるような、私の知っている町会さんでいうと、35年間会長をやっているという町会さんもあれば、もう三、四年で、任期が決まっていて、会長さんが決まったときは次の会長さんももう決まっているという町会さんもあります。そういう仕組みづくりのところが1つと、もう一つは、せっかく若い人が入ってきても、私なんかも大分上の世代になってきたので、サークルなんかでは気をつけているんですけど、やっぱり、それ違うよみたいな話になってしまうと、若い人はつまんなくなってしまったりもする。だから、運営の仕方を学ぶ場、要は若い人たちと一緒にやっていけるような学ぶ場ですよね。考え方のマインドセットといいますか、そういったことを学ぶ場もこの中間支援機能の中で少し考えて、少しずつでもやっていきたいなというふうに思っているところで、そこが変わらないとやっぱり、せっかく若い人が入ってきても、やめていってしまうということが多くなってしまうので、このコミュニティ創生基本方針の一番の問題意識の中に、やはりコミュニティの高齢化と世代間の分断というのがあります。そこを基に前の冊子は作ったようなものなんですけれども、そこを何とかしたいということで、使えるか使えないか分からないような制度も含めて、いろいろ並べてあるというふうに御理解いただけたらいいかなと思います。

もうまさに本当にそこが課題だと思うんですけど、あと一方で、本当に担い手がいないために辞められないという御高齢の方もたくさんいらっしゃるので、もう何も引き継げなくって、体、体調を患いながら必死に出てくるという方たちもいらっしゃるので、ぜひそこの運営のサポートといいますか、循環していく仕組みというのを、住協に限らず、町会ですとか、地域のコミュニティは全てそうだと思うんですけど、そこの運営をどういうふうに回していくと地域の中で継承できたり、あとやはり、ずっと長年やっている方からせっかく教えてもらえるので、そこで分断しないように、そういった流れができていくと、もっとコミュニティに対しての楽しみだったり、地域に関わる意義みたいなのを感じていけると思うので、ぜひ行政としてもそういったところをやっていただけるといいかなと思います。
以上です。ありがとうございます。

健康福祉部報告、本件を議題といたします。
本件に対する市側の説明を求めます。

本日、健康福祉部としては2件です。ア、「三鷹市健康福祉総合計画2027」骨格案について、イ、「市内病院機能の維持に向けた支援に関する方針」についての2点でございます。
まず、アの計画につきまして、私のほうから説明させていただきます。資料の1を御覧いただけますでしょうか。資料の1でございます。三鷹市健康福祉総合計画2027骨格案についてでございます。
1として、概要でございます。三鷹市基本構想及び第5次三鷹市基本計画を上位計画といたしまして、健康福祉分野の施策につきまして、基本計画との整合性を図りながら、全ての市民の健康及び福祉に関する個別計画、施策を総合化して策定するものであり、健康福祉総合条例に基づく健康福祉に関する総合計画となります。
(1)の基本目標と施策推進の基本的な考え方でございます。基本目標といたしましては、全ての市民が、地域において、健康で安心して、生き生きと自分らしい生活を送ることができる高福祉のまちをつくるとしております。
また、施策推進の基本的な考え方といたしましては、自助、共助、公助が相互に連携して推進されることによって高福祉のまちの実現を目指すものでございます。あわせて、サービスの質を確保しながら、利用者の視点に立ったサービスの提供を目指してまいります。
計画期間につきましては、令和6年度から令和9年度までの4年間としているところでございます。
(3)の計画の構成(案)でございますけども、この表のとおり、地域福祉編、高齢者福祉編等、6編に分けて考えているところでございます。
1枚おめくりいただきまして、2ページ目の上段になります。今回新たに追加する計画といたしまして、1の重層的支援体制整備事業計画、2の再犯防止推進計画、3の成年後見制度利用促進基本計画、4として三鷹市子ども総合計画(仮称)については、今回の計画に取り込む形で策定したいと考えております。
なお、本日、健康福祉部の説明に関しましては、子ども総合計画の部分につきましては、調整中というところもありますので割愛させていただきますが、この後、子ども政策部のほうから説明があるというふうに聞いているところでございます。
3の計画策定に向けたスケジュールでございます。この6月に基本計画が確定していますので、それを受けまして、現在、9月ということで骨格案を御説明させていただいていますけども、この後、確定させて、11月には素案を確定するとともに、パブリックコメントを年末年始にかけます。その間、健康福祉審議会等に報告する中で、3月には計画を確定させたいと考えているところでございます。
3ページ以降は、健康福祉施策の現状と今後の方向性ということでございます。ポイントだけ御説明させていただければと思います。
3ページ、地域福祉ですけども、作りはそれぞれの形、こういう形で作っております。最初に、前文といいますか、内容について書いてありますけども、今回は、最初に大きな方向性等を文言で書くとともに、中段に、基本計画の主要事業ということで、この6月に確定しました基本計画の主要事業を載せております。その下に、本計画における重点事業ということで、現在考えているものを載せさせていただいております。
3ページの地域福祉計画でいいますと、重層的支援体制整備事業の推進ということで、地域福祉コーディネーターと連携していく中で、市民が相談しやすい環境をつくりたいということですとか、災害時における要支援者、要配慮者の支援体制の強化ということで、例えば福祉避難所の運営マニュアルの作成等を行う中で、しっかり災害に備えていきたいと考えております。
おめくりいただきまして、4ページでございます。高齢者福祉編でございます。こちらも作りは全く一緒ですけども、一番下の本計画の重点事業ということで、福祉Laboどんぐり山による在宅医療、介護の推進ということで、引き続き研究等を進めていきたいと考えております。また、認知症施策の推進ですけれども、条例の制定、計画の策定等、しっかり取り組んでいくというところです。その中では、認知症御本人やその家族の方の意見もしっかり反映させていきたいと考えています。3つ目として、地域包括支援センターの充実ということで、やはり単身高齢者や認知症高齢者が増えていることが見込まれることから、機能の充実を図ってまいりたいと考えております。
5ページの障がい者福祉でございます。一番下の本計画における重点事業ですけども、心のバリアフリー推進事業というところで、しっかり広報啓発活動の充実に取り組んでいきたい、また、障がいのある方との交流の機会もしっかりとつくっていきたいと考えています。2点目、調布基地跡地福祉施設(仮称)整備事業です。この施設につきましても今回補正予算を出させていただいておりますけれども、引き続き整備を進めてまいりたいと考えております。また、担い手の確保、定着というところで、高齢部門もそうですけども、障がい部門もしっかり人材の確保、定着について取り組んでいきたいと考えているところでございます。
6ページ、生活支援でございます。本計画における重点事業といたしまして、引き続き、生活保護制度の適切な運用、生活困窮者自立支援事業の推進ということで、特に生活保護制度につきましては、第3のセーフティーネット、最後のセーフティーネットというところですので、しっかり市民の生活が守れるように取り組んでまいります。
7ページ、健康増進編でございます。こちらも、自らの健康は自ら守り、つくるという意識を持っていただくとともに、しっかり予防事業等の充実を図ってまいります。また、疾病予防といたしまして、がん検診、予防接種などを推進していきます。また、感染症対策の行動計画を策定し、危機管理体制の強化を図ってまいります。
8ページ以降は現在考えている体系でございます。例えば、8ページなんですが、地域福祉編には、地域福祉計画、重層的支援体制整備事業実施計画、9ページになりますけども、再犯防止推進計画といった計画を織り込んでいく形で作っております。子どもの部分については現在調整中ということで、割愛させていただいております。
続けて、申し訳ないんですけども、資料の2、市内病院機能の維持に向けた支援に関する方針についてでございます。こちらは今年の8月9日に確定したもので、コロナの検証を行っていく中で、やはり病院支援は必要だろうというふうに一定の方向性を出したところでございますけども、この間、例えば井口グラウンドの市内病院誘致に関しても、そうした提案を受ける中で、市内病院が抱える課題、老朽化であるとか、感染症対策というところが弱いということが明らかになってまいりました。また、市内の病院が介護医療院に転換したり、近隣市においては病院の閉鎖ということがあるという状況もございます。そうしたことを踏まえまして、今回この支援に関する方針を策定したものでございます。
これに関して、詳細につきましては担当課長より御説明させていただきます。

白戸謙一さん
それでは、私から、市内病院機能の維持に向けた支援に関する方針について御説明をさせていただきます。
まず、資料の2の1を御覧いただければと思います。概要でございますけれども、地域医療を支える医療資源を十分に確保し、その機能を維持、継続するための支援に関しまして、ただいま部長が申し上げたように、令和6年8月に市内病院機能の維持に向けた支援に関する方針を定めましたので、御報告をさせていただくものでございます。
2の背景、目的でございます。地域医療を支える病院は、三鷹市における健康福祉施策を進める上で、重要な医療資源と考えております。平時の地域医療機能だけではなく、災害時における医療拠点としての機能を有しており、三鷹市地域防災計画においても7つの病院を医療拠点として指定しまして、災害時には市の医療本部と連携して対応に当たることとしています。加えまして、在宅医療、介護を進める上でも欠かせない医療資源となっています。また、地域医療が抱える課題は多様化、複雑化する一方、病院施設の老朽化や感染症対策などの課題が顕在化し、病院設備等の再構築が必要な状況となっています。病院が介護医療院になる、あるいは病院そのものが閉院となる、こういった状況も踏まえまして、このたび、医療資源を確保するための支援に関して方針を取りまとめたところでございます。
3の方針の内容でございます。まず、(1)の概要を御覧ください。方針の内容としまして、3つの項目で構成をしています。アの市内病院と災害時の位置づけ、イの市内病院の機能と役割、ウの市の支援の方向性でございます。
(2)の市の支援の方向性につきましては、アとしまして病院機能の維持、拡充に向けた支援、イの病院の建て替えや改修に向けた支援、ウの感染症対策に向けた支援の3つの項目により整理をしまして、地域の医療体制や各医療機関の状況などを踏まえながら、具体的な支援内容について検討を進めていくこととしております。
その他でございますけれども、4に記載のとおり、具体的な支援に当たりましては、市への貢献度や公益性、市の計画との整合性などを考慮し、市内の医療機関に限定して行うこととしています。
なお、御参考までに本方針の全文を添付しておりますので、御確認をいただければと思います。
私からは以上です。

よろしくお願いいたします。まず、総合計画の骨格案についてなんですけど、これ、具体的なところはまた今後出てくるということで、またそちらで確認していきたいと思うんですけど、5ページの障がい者福祉についてなんですけど、障がいのある方が地域で暮らしやすい環境づくりというところでは地域生活支援の充実というふうな部分に入るのかなと思うんですが、障がいのある方の移動手段として、そういったものの支援充実というと、バリアフリーをイメージするんですけども、バリアフリーについては、第三期三鷹市障がい者(児)計画のほうにもバリアフリーのまちづくりということが書いてあるんですが、そういった障がいを持たれている方、例えば車椅子の方ですとか、そういった方が地域で例えばお茶をしたいですとか、それは事業者の問題になるかもしれないですし、ちょっと管轄が違うかもしれないんですけど、障がいの方から、三鷹駅前で車椅子で入れるお店は1つもないということを聞いたりですとか、あとトイレも少ないということをすごく聞いていまして、こういった視点というのは、都市再生部のほうにも書いてないですし、もしかしたらちょっと商工振興とかでも、そこまでは確認できてないんですけども、そういった地域に根差して障がいの方が暮らしやすい環境づくりというところは健康福祉部のほうの所管とはまた違うという形ですか。また、そういった検討、まちづくりと地域生活の支援というところと、そういった障がいの方たちが地域になじんで生活していくというような視点でこういった基本方針を検討されたことはありますでしょうか。前回の資料を見ても、そういったことがちょっと書いてなかったので、そういった視点があったのか、お伺いしたいと思います。

立仙由紀子さん
難しいんですけども、バリアフリーのまちづくり基本構想というのがございまして、こちらのほうで主にハード面については、おっしゃるように、都市整備部のほうでやっております。また、心のバリアフリー、気持ちのところについては、主に健康福祉部のほうで進めているところでございます。また、お店とか、そういったハード面のところにつきましては、このバリアフリーのまちづくり基本構想の中で重点整備地区を設けておりまして、そこについて今後整備をしていくのかと考えております。また、これにつきましては、今年度、改定の時期に来ておりますので、バリアフリーのまちづくり協議会という、そういう考えるところがございますので、そちらには障がい者支援課だったり高齢者支援課の各所管も参加しておりますので、一緒に考えていけたらと思っております。

ありがとうございます。おっしゃるとおり、都市整備部、都市再生部のほうでは、バリアフリー法で、障害者等の移動等の円滑化を促進する法律ということでいろいろ提起されているんですけども、地域で暮らしていく障がい者の方たちという視点ですと、本当にトイレだったり、お店をちょっと利用したいなといっても、行く場所がない。僕たちはどこも行く場所がないんだということを聞いていまして、何かそういったところも、事業者と連携するのか、商工振興でやるのか、ちょっと分からないんですけど、そういったところがちょっと抜けているのかなというか、そういったところも必要なのではないか。

バリアフリーマップというものを作成をしておりますので、そちらのほうにはお店ですとか、ハード面で車椅子対応ができるとかというところも掲載をしております。ただ、そちらのほうがマップのラミネートされたものだったり、あとはホームページに掲載をしていますので、そちらのほうの周知が行き届いていないという部分はあるかもしれませんので、今後そういったことの情報発信もしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

ありがとうございます。恐らく事業者さんのほうで、駅前は事業者さんが商店会とか地域に配られている車椅子マップというのがありますので、そういったものはあると思うんですけども、その車椅子マップの中でも、車椅子の方ですとか、ちょっと障がいを持たれている方というのがまちでほっとする場所ですとか、以前はスペースあいというものが駅前にありまして、そこは車椅子対応をしていたので、たくさんそこに集まられていて、スペースあいは唯一そういった障がい者の方が集まれる場所だということを聞いていたんですけども、やはり段差だったり階段がある場所ばっかりなので、そういったところはどこの所管なのか、そういった対策というのがどうなのかというのをちょっとお伺いしたかったので、ちょっとまた検討というか、また状況が分かれば教えていただきたいなと思いました。ありがとうございます。
次に、すいません、資料2のほうで、市内病院、先ほどからいろいろとお話を伺っているんですけども、今回これは、三鷹市の地域防災計画において7病院を医療拠点としている、これは地域防災計画のほうに記載してあることなんですけども、その地域防災計画のほうを見ると、市内病院7病院以外でも、五師会、薬剤師会ですとか医師会ですとか、いろんなところが連携してこの地域防災計画を進めていこうというような資料になっているんですけども、今回のこの方針には病院のことしか書いていなくて、あくまでも災害ですとか、コロナ禍というお話が出たんですけど、災害時の位置づけとして病院をどういうふうに支援していくかという視点で読み取ったらよろしいでしょうか。

小嶋義晃さん
御指摘のとおり、災害時の視点というのももちろんございます。いつ起こるか分からない災害に対してしっかり市民の方を守るという視点から、災害時においても当然、医療機関というのは非常に重要な資源になるわけですから、そういったことも当然踏まえているところでございます。また一方で、通常の診療、診察も含めて、やはり老朽化という課題がございますので、災害時にかかわらず、日常からの市民の健康を守っていただくという視点からも支援が必要ではないかということで、こういう形で方針をつくらせていただいたところでございます。
以上でございます。

ありがとうございます。部長おっしゃるとおり、そういった平常時、また市の支援の方向性という視点からも、この方針の中にほかの病院以外のところとの連携というのが何も書かれていないということがちょっと、あくまでも病院を支援するということだけにとどまってしまっているので、少し誤解を生むような──誤解といいますか、何ていうんだろう、本当に病院だけではできない部分になってくると思うので、防災の計画なども連携というところがたくさん、いろんな場所と連携して病院が成り立つというところでの視点で記載があるので、この方針、何度読んでも、病院のことしか書いていませんので、その辺はどういうふうに捉えているか、もう一度お願いします。

今回はやはり病院──今まで病院の支援というのはなかなか市としても行ってきていない現実があります。そうした中で、やはり近隣市の動向、私も報道等の知識しかないんですけど、そういう事態になれば市としてもやはり緊急の対応が必要になるようなことも聞いています。そうした中で、やはりまずは、もちろん我々がしなければいけない仕事というのは非常に数多くあります。そのために計画づくり等も今推し進めているわけですけども、今回のコロナ禍でも、医師会さんのみならず、薬剤師会さん等にもお世話になっております。また、休日診療所も、医師会、歯科医師会、薬剤師会さん、三師会が一緒になって入っていただいて、そういったところもしっかりと体制づくりに取り組んでいるところでございます。そうした中で、やはり今、病院さんは非常に大きな規模の建物をお持ちでありますし、医療従事者も多い。そういったところはやはり、非常に規模的にもしっかりとして市が支援していくんだという方針を打ち出すことによって、病院さんが建て替え等で今後困る、そういった課題が出たときに、一定程度、こういう方針があることによって、病院さんにも安心していただいて、三鷹市での経営を続けていただけるのではないかと、そういう思いもございまして、今回は病院に特化した形で方針をつくらせていただいたところでございます。
以上でございます。

ありがとうございます。タイトルがといいますか、市内病院の機能と役割という形ですので、病院が機能する上では、そういった関係、関連するところは絶対に必要だと思いますので、今回は病院ということだったと思うんですけど、大前提として、そういうのを見据えた上で病院に特化したということで理解してよろしいでしょうか。

そうですね。そういう形で、今回はあくまで市内の病院に特化した形でこういう方針をつくらせていただいて、具体的なことにつきましては、また今後いろんなケースが出てくると思いますので、そういった形で、その都度判断をさせていただければなというふうに考えているところでございます。

ありがとうございます。終わります。

子ども政策部報告、本件を議題といたします。

子ども政策部からは4点行政報告をさせていただきます。まず、1点目の(仮称)三鷹市子どもの権利に関する条例の制定については、私、近藤から、以下、担当する部課長より順次説明をさせていただきます。
まず、資料1を御覧ください。(仮称)三鷹市子どもの権利に関する条例の制定についてということで、1については、これまでの背景等も踏まえて、いま一度確認、記載させていただいております。子どもの権利につきましては、1989年に国連総会で、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)が採択され、1990年に発効、そして日本は1994年に条約を批准したと。また、2023年(令和5年)4月でございますが、日本国憲法、それからさきの条約の精神にのっとり、全ての子どもが将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するということで、国においてこども基本法が施行されております。
三鷹市ではということでいいますと、子どもと大人の共通目標として三鷹子ども憲章を平成20年に制定いたしまして、三鷹の子どもたちが未来に向けて夢や希望を持ち、明るく、楽しく、元気よく、心身ともに健やかに成長していくことができることをこれまで目指してまいりました。さらに、昨年度末の議案になりますが、人権を尊重するまちづくりの上位規範としまして、一人一人の人権が尊重され、誰もが暮らしやすいまちを実現するということを目的に、人権を尊重するまち三鷹条例が制定され、令和6年4月に施行となっております。
こういったことも踏まえまして、子どもの尊厳が守られ、幸せに生きることができる権利、これを保障し、子どもにとって最善の利益を考え、子どもが幸せに過ごすことができるまちを実現させるため、三鷹市が取り組むべき政策の基本となる事項を定める(仮称)三鷹市子どもの権利に関する条例を制定することといたします。
なお、この仮称につきましては、これまで施政方針や第5次三鷹市基本計画におきましては、三鷹市子ども人権基本条例(仮称)というふうに記載しておりましたが、人権を守るための中身を実現させるということで、基本的な事項を定めるということもありまして、改めて今回から(仮称)三鷹市子どもの権利に関する条例と表することとしております。ただ、現時点での仮称ですので、今後検討を進める中、皆さんの意見も伺いながら、名称のほうについてはまとめてまいります。
次、2、この条例に盛り込む現時点での主な内容でございます。基本的なことになりますが、基本理念、それから子どもについての定義、それから子どもの権利保障、そして子どもの意見、それから市、市民、保護者、事業者等、それぞれの役割、そして権利を守るためのまちづくり、子どもの権利を擁護する機関の設置、こういうのを現時点で主なものとして挙げております。
条例制定に向けた取組といたしまして、3つ大きくございます。まず、学識経験者を中心とする検討委員会の設置、それから小学生からおおむね18歳までのワークショップ、そして市内小・中学校全児童・生徒へのアンケート、また、それ以外に多世代交流センター利用者、高校生、若者へのアンケートも実施いたします。さらに、市内の関係団体や各部で所管しております協議会、審議会等への意見の聴取、そしてパブリックコメントといったものを予定しております。
今後のスケジュールですが、まず本日、行政報告をさせていただいた後、11月から12月、年内にまず第1回検討委員会を開催できるよう委員会を設置してまいりたいと。そして、ワークショップも年内に開催する予定でございます。令和7年、令和8年で、令和7年には小・中学生等のアンケート、令和8年にはパブリックコメントに条例案として提示させていただきたい。令和8年度中の条例案というふうに考えております。その他、適宜、厚生委員会への報告、それから検討委員会を開催するというものを予定しております。
私からは以上です。

清水利昭さん
私からは、資料の2のほう、三鷹市子ども総合計画(仮称)の策定について御報告申し上げます。資料2のほうを御覧ください。あわせて、この後御説明しますが、資料2の別紙1、それから別紙の2のほうも御覧ください。
まず、資料2のほうです。まず、1番として、計画の基本方針です。現行の子ども・子育てビジョンの基本理念をこども基本法の目的に準じた内容とし、5つの方向性を、第5次三鷹市基本計画及びこども大綱を勘案して、総合計画では基本方針として見直すことといたします。また、子ども・子育てビジョンは、子ども総合計画(仮称)に統合することといたします。
次に、2番です。子ども総合計画(仮称)の骨格案についてです。これは計画の構成ということになります。まず、第1部としては総論という形、それから、そのページの下のほうに参りまして、第2部として、計画の基本方針等について触れます。裏側のページに参りまして、第3部として、計画の施策体系、事業の内容という、まずは3部の構成といたします。
では、順次御説明申し上げます。まず、第1部でございますけれども、総論の部分です。総論の部分の第1として、計画策定の背景、目的について触れます。
次に、2番、計画の位置づけということで、(1)のこども基本法のほか、(2)に掲げてございます計画に包含する他の法律に基づく主な計画として、アからキに掲載させていただいているような法に基づく計画もこの計画の中に包含するということで総合計画ということになります。
それから、3番、定義及び対象となる子どもの人口について記載します。(1)で、まず定義ですが、子ども、それから若者、それから青少年ということで定義を記載したいと考えています。子どもはおおむね18歳までの者、18歳以上であっても継続的に支援が必要な者または心身の発達の過程にある者という表現をいたします。それから、若者については、思春期、青年期の者ということになります。続いて、青少年については、乳幼児期から青年期までの者というように定義したいと考えています。
(2)で対象人口です。そこに対象となる人口を掲げます。これは基本計画のほうで掲げている人口と連動する形になります。
それから、4番、計画の期間ですが、令和7年4月1日から令和12年の3月31日までの5か年といたします。
次に、5番、第2期三鷹市子ども・子育て支援事業計画の達成状況ということで、現行の計画の、こちらの達成状況について記載をいたします。
次に、第2部です。計画の基本方針等ということで、まずは1番で、裏側のページに参りますが、基本理念ということで、子どもの最善の利益を追求し、全ての子どもが、心身の状況や置かれている環境にかかわらず、その権利が守られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる地域社会の実現ということで掲げます。
それから、2番です。基本方針ということで、大きく4つの柱立てといたします。まず1として、子どもを主体とした子ども施策の推進、次に2として、全ての子どもが幸せに育つことができるための支援、3として、子どもの可能性を引き出す環境等の充実、次に4として、子ども、若者が健やかに成長し、生活できるための支援という、この4つの柱立てといたします。
これを受けて、第3部のところには、これに基づく施策、事業の体系が記載されて、それぞれの事業についての説明を記載するという形を想定してございます。
最後に、3番のスケジュールですが、今年11月に計画の素案策定といたします。12月には厚生委員会のほうに再度行政報告という形でさせていただいて、その後、パブリックコメントの実施、それから年が明けた令和7年の2月に子ども・子育て会議への計画案の諮問、答申、そして厚生委員会への行政報告、それから令和7年の3月に計画策定というようなスケジュールで考えているところでございます。
次に、この計画改定に当たりましては、前年度にニーズ調査、それから生活実態調査という2つの調査を実施しております。非常に質問数も多いので、一つ一つ御説明するのは非常に難しいですので、特徴のあるところと概要について御報告をさせていただきたいと思います。
まず最初に、別紙の1のほうの、緑色で印刷されているかと思いますが、そちらのほうの資料を御覧ください。三鷹市子ども・子育て支援事業計画改定に伴う子育て支援ニーズ調査の概要です。
まず、1番、調査の目的、方法ですけれども、こちらは、目的としては、子育て家庭の現状や子育て支援に対する要望、意見を把握する、今後の三鷹市における教育、保育などのニーズの見込みや支援施策提供体制の確保の検討を行うことを目的としております。方法ですが、ゼロから5歳までの未就学児の保護者を対象として実施する。そして、5年前実施した調査との比較を行う。それから、小学校の2年生、4年生の保護者を対象としまして、子どもの放課後の過ごし方の実態ですとか、今後の意向等を把握するために実施をいたしました。
右側のほうに参りまして、2番の調査の種類、回収状況等が記載されております。未就学児の保護者は、配付としては対象が2,000件ということで、そちらに回答の件数と有効回答率が記載されているところです。以下、小学2年生の保護者、それから小学4年生の保護者ということで、それぞれ数値が示されております。
3番ですが、分析の枠組みのイメージですが、先ほど実施の仕方について御説明しましたが、それをイメージとして図示したものが3番になってございます。過去の調査と比較をしながら実態を把握するということでございます。
次に、4番の主な調査結果でございます。全部で6つのカテゴリーにまとめております。まず、1番は子育て環境について、それからまる2、母親の働き方、子育てに関する変化について、まる3、父親の働き方、子育てに関する変化について、まる4、保育園や幼稚園等の利用ニーズについて、まる5、子育て支援事業について、まる6、放課後の過ごし方についてという6つのカテゴリーに分けました。
まず、まる1のところを御覧ください。全て読み上げますとちょっと時間かかりますので、特に特徴かなというふうに考えるところを御紹介いたします。まず、1の子育て環境についてですが、前回の調査と比べますと、丸の2つ目になりますが、預け先としては、預けられるところがないの割合が前回よりも高くなりました。緊急時、もしくは用事のあるときに祖父母等の親族に預かってもらっているという方の割合が低くなったという特徴がございます。
次に、まる2で、丸の2つ目のところですが、前回の調査と比較をしますと、働いていない人の割合が減少しまして、短時間勤務の割合が増加しているという傾向が見られます。
次に、まる3、父親の働き方、子育てに関する変化ですが、丸の3つ目のところ、育児休業を取得した父親の割合は、前回調査よりも増加しており、取得期間も、約5割は30日以上、約2割が90日以上取得しているというような結果が出ました。
次に、まる4です。保育園や幼稚園等の利用ニーズについてです。最初の丸のところですが、現在利用している施設、事業としては、認可保育園と答えた方が約60%、幼稚園と答えた方が約25%で、前回調査と比較しまして認可保育園の割合が増加しております。
次に、まる5、子育て支援事業についてです。2つ目の丸のところですが、子育てに必要なサポートの自由記述では、相談事業に関する要望が最も多く、SNSや電話などを用いて簡便に相談や情報共有が行える場の要望というものが見られました。
次に、まる6です。放課後の過ごし方についてです。丸の2つ目、5歳児の保護者にお伺いしたところでの小学校低学年における放課後の過ごし方については、約5割の方が公立の学童保育所を希望するというふうに回答していらっしゃいます。それから、丸の4つ目、子ども自身の地域子どもクラブの利用の意向については、低学年では約6割、高学年でも約5割というような高い割合の回答が見られたところです。
次に、右側のところに行きまして、5番です。今後重要と考えられる施策等についてということで、前回調査と比較しますと、働き方や祖父母をはじめとする周囲との関わり方など、子育て世代を取り巻く環境に変化が見られます。子育て支援事業のさらなる充実を図るなど、多様な保育ニーズに対応できるよう施設、事業を整備していく必要があると考えます。2つ目に、子育てに関する情報共有ですとか相談についてのニーズがあります。保護者が必要とする情報提供に努めるほか、既存の相談機関に加えて保育園や幼稚園とも連携した地域ぐるみの相談支援体制の強化や新たな相談手法を検討する必要があると考えます。3つ目に、小学校低学年時は、公立の学童保育所に対するニーズが高いということで、引き続き学童保育所での定員確保に努める必要があると考えます。4つ目に、高学年の児童については、過半数の児童が地域子どもクラブへの参加意向を持っており、友人、異学年児童との交流や運動を通じた身体的能力の向上を求める割合が高いです。地域子どもクラブを拡充するとともに、地域における子どもの居場所づくりの取組を推進していく必要があると考えます。
以上がニーズ調査の結果です。
次に、別紙の2のほうです。水色で印刷されているかと思いますけれども、三鷹市子育てに関する生活実態調査、子どもの生活実態調査というふうに呼んでおりますけれども、こちらの概要についてです。
まず、1番、調査の目的、方法についてです。まず、目的、子どもや子育て世帯がどのような生活困難を抱え、どのような支援を必要としているかを把握する、社会の状況の変化に伴って新たに生じてきた課題についても今後の子ども・子育て支援へ反映させることを目的として、質問の中に設けたところでございます。方法としましては、小学校の5年生、それから中学2年生とそれぞれの保護者及び18歳未満の子どもがいる児童扶養手当受給世帯の方を対象として、同様に5年前の調査との比較を行っているところでございます。このほかに、現状や課題をより多角的に捉えるために、地域の子育て支援に関わる様々な関係機関を対象としたアンケート調査も併せて実施をしたところでございます。
右側の2番は、ただいま御説明したことをイメージとして図示したものでございます。
次に、3番、主な調査結果でございます。こちらは、調査の内容、対象者で分けて、カテゴリーに分けております。まる1は、保護者、それから児童扶養手当受給世帯の回答結果、まる2は、小学生、中学生、子どもたち自身に質問をして得られた回答について、それからまる3は、子育てに関わる関係機関の方からの回答ということで分けております。
まず、まる1の保護者の回答です。特徴のあるところを幾つか御紹介します。まず、丸の上から2番目で、子どもとの体験活動ということについては、児童扶養手当の受給世帯では金銭的な理由によって総じて機会が少なく、家族旅行や学習塾、習い事についても控える傾向が見られました。
それから、2つ下の丸、4つ目の丸に行きまして、親の子どもへの進学期待について、大学またはそれ以上と回答した割合は、小・中学生の保護者で80%、児童扶養手当受給世帯で約65%となっております。
次に、また2つ下に参りまして、6つ目の丸、児童扶養手当受給世帯の保護者では、小・中学生の保護者に比べて、神経過敏ですとか気分の落ち込み、自己肯定感の低さを感じた割合が高く、過食、飲酒、喫煙などの嗜好、依存傾向も小・中学生の保護者調査の結果と比較するとやや高い結果が出ました。
次に、その下の7つ目の丸、新型コロナウイルス感染症拡大の前との状況の比較については、父親、母親ともに影響がないとの回答が最も多かったところですが、父親は、テレワーク、お子さんと話をすることが増えたという回答が見られたのに対して、母親については、いらいらや不安を感じたり、気分が沈むですとか、支出の増加を感じる割合が高い傾向が見られました。
次に、まる2、小学生、中学生の回答の結果からでございます。最初の丸のところですが、毎日、ゲーム機で遊ぶですとか、スマートフォンなどでインターネット──SNS、ユーチューブということになりますが、こういったものを見る子どもの割合が増えている結果が出ました。
それから、一番下の丸ですが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、学校以外で勉強する時間、それから夜遅くまで起きている回数が増えた小・中学生が約3割いました。中学生では、いらいらや不安を感じたり、気分が沈むことが増えた割合もやや高い結果となりました。
次に、子育てに関わる機関からの回答です。上から2つ目の丸ですが、保育園、幼稚園では、子どもの権利を擁護するため、保育、教育に関わる職員の意識向上に向けた取組や保護者への支援が必要というような御意見が見られたところでございます。
これらを受けまして、その右側のところの4番ですが、今後重要と考えられる施策等についてということで、全部で5つ掲げてございます。
まず、最初のところ、1つ目ですが、小・中学生の保護者の調査の結果と比較しますと、児童扶養手当受給世帯は金銭的な理由から子どもとの体験活動、習い事等を抑えているというような状況が見られます。保護者の子どもへの進学期待についても、大学またはそれ以上の回答が低い割合となっております。親の経済状況や家庭環境等に影響を受けることなく、子どもの学習環境の確保や多様な体験活動の機会の創出が求められると考えます。
2つ目ですが、児童扶養手当受給世帯では、保護者が神経過敏や気分の落ち込みを感じる割合、それから嗜好、依存傾向がやや高い傾向があるということから、包括的な相談支援体制の強化が必要であると考えます。
3つ目、前回調査と比較しまして、ゲーム機で遊んだり、スマートフォンなどでインターネットを見る時間が長くなっている傾向があります。子ども同士でのトラブルや犯罪被害のリスクを回避するため、スマートフォンやSNSの適切な利用に向けた対策が必要であると考えます。
それから、4つ目、子育てに関わる関係機関調査では、子どもの権利擁護の重要性についての回答が見られましたので、こども基本法やこども大綱にのっとって、子どもの意見表明の機会を設定するとともに、虐待やヤングケアラー等といった様々な課題においても、子どもの権利が尊重される地域づくり、組織体制の強化を推進していく必要があると考えます。
最後の丸のところです。新型コロナウイルス感染症拡大前と比較して精神的ないらいらや不安を感じる等、保護者、子ども両方に影響が見られました。今後、長引く感染症のような危機的局面への対策等を想定しておく必要がある、このように考えます。
私からは以上です。

よろしくお願いいたします。子ども総合計画についてまずちょっとお伺いしたいんですけど、4月から母子保健の部分が子ども政策部に移行になったんですけども、今まで健康福祉総合計画の中に入っていた子ども・子育て支援計画の部分については、どちらに含まれるようになるんでしょうか。

子ども・子育て支援事業計画についての御質問ですね。これは今回のこの総合計画の中に含まれますし、かなり占める割合が大きい部分になろうかというふうに考えています。

補足させていただきます。子どもに関する計画については、母子保健に限定したことではなくて、これまでも福祉の総合計画とこの子ども・子育て計画、両方に記載がございました。ですので、そこは基本的に両方に、どちらかというと福祉の総合計画はこの子どもの計画をぎゅっと狭めた形になろうかと思いますけれども、策定していくということになります。

分かりました。ありがとうございます。
続きまして、緑色の資料、子ども・子育て支援事業計画改定に伴うニーズ調査、まず、これは放課後の過ごし方の実態などを伺ったということなんですけど、この調査の際に中学生の保護者とかには聞かなかったのでしょうか、お伺いいたします。

こちらは保護者、子どもと一緒に答えていただくような形で保護者に依頼をした調査となっています。

中学生の保護者には、中学生と中学生の保護者という形では聞いてはいないということか。

こちらのほうは小学生の2年生と4年生の保護者ということになります。

分かりました。あくまでも小学生の保護者を対象に子どもの放課後の過ごし方を聞いたという認識でよろしいでしょうか。

放課後の過ごし方についてももちろん聞いておりますが、それ以外にも様々質問をしているところです。

未就学児、小学校2年生、4年生に伺っているということなんですけども、これはエリアとしてはどのような割合で聞いているんでしょうか。

こちらは学校を通じて配付させていただいているところです。エリアに分けているわけではございません。全域です。

分かりました。ありがとうございます。放課後に関してはエリア性も、放課後にどういう過ごし方をしているのかというのはエリア的な部分での違いはあるのかなと思うんですけど、それはもうあくまでも学校側にお願いしてという形ですかね。

集計されたものはそれぞれ無記名というような形になっているので、エリアについての特徴というものはちょっと拾いにくいのかなというふうに思います。

分かりました。放課後の過ごし方は恐らくエリアによって違うのかなと思いますので、そういう視点も持っていただけるといいかなと思いました。
あと、今後重要と考えられる施策等についての部分で、小学校低学年には公立の学童保育所に対するニーズが高いというのは、これは5歳、未就学児と小学校2年生に聞いて、こういう結論というか、こういう施策等が必要だというふうに認識しているということでしょうか。

これは、まず、御指摘のように、ゼロから5歳ですとか、あるいは小学校2年生の子が、将来小学生に上がったとき、あるいは低学年においてどこに行きたいのか、どういうところを利用したいのかという質問をしています。それから、4年生についても、どこで過ごしているのかというようなことで希望等を聞いていますので、そういうところから拾えているのかなというふうに考えています。

ありがとうございます。これ、学童に行かれている当事者の方とかにはアンケートは取られたんでしょうか。

特に学童に通っている方に限る形での調査というのはしていないです。この中には、通っている方もいらっしゃるし、通っていない方もいるというような形になっています。

ありがとうございます。放課後の居場所については、もし、例えば地域子どもクラブを拡充してほしいですかという聞き方をしたら、してほしいとなると思うんですね。学童についても、学童をもし高学年においても拡充してほしいかという聞き方をしていたら、学童も拡充してほしいというふうに当然なると思うんですけども、今回のこの、過半数の児童が地域子どもクラブへの参加の意向を持っておりというのは、地域子どもクラブに参加したいですかというような質問をして、こういうふうな回答というふうな認識なんでしょうか。

これは、まずストレートに、御指摘のように、地域子どもクラブが毎日実施された場合には参加したいと思いますかという質問のほかに、どういうところでふだん過ごしているかとか、過ごしたいかというようなことを保護者と子どもに聞いています。

分かりました。そうすると、低学年は公立の学童保育所に対するニーズが高いというのは、高学年においてあまりそういった要望はなかったということですか。お伺いします。

全然意向がないわけではありませんが、習い事ですとか、何かスポーツですとか、違うところで過ごす方が低学年に比べると結構な割合を占めていたというふうに記憶しています。

分かりました。それは現状ということですか。ニーズじゃなくて、現状そういう過ごし方をしているということが多いということ。ニーズって、もしあったらこうしたいということだと思うんですけど、現状は習い事とか、そういったところに行っているというふうに回答されたということですか。

現状についても伺っていますし、意向についても伺っているところです。

主な調査結果の4番目で、保育園や幼稚園等の利用ニーズについてという点なんですけど、これは、現在利用している施設、事業は、認可保育園が約60%、幼稚園が25%とあるんですけど、これは現状じゃなくて、利用ニーズなんですか。お伺いします。

これは現状ですね。

ありがとうございます。そうですよね。これ、恐らくニーズという聞き方をすると、またちょっと違うのかなとは──そうですね、これは現状かなと思っていて、ニーズの聞き方という部分ではまたちょっと違うのかなと思うんですけども、ニーズを聞きたかった理由というのをお伺いしてもよろしいですか。

こちらに書かせていただいているのは、現状について60%、25%と書いていますけれども、御意向、今後の意向についても別のところで聞いているところでございます。

ありがとうございます。そのニーズというのは何かありますか、数字は。もし分かれば教えてください。

平日定期的に利用したい教育、保育事業という聞き方をしたところでございますけれども、認可保育園が58.6%、次に高いのは幼稚園で29.8%、それから次に高いのは幼稚園の預かり保育ということで27.1%というようなものが上のほうに挙がってきている状況です。

ありがとうございます。預かり保育で幼稚園を利用したいという利用ニーズがあるということですかね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
分かりました。ありがとうございます。
すいません。次に、生活実態調査についてちょっとお伺いします。こちらもちょっとアンケートの取り方について伺いたいんですけども、地域の子育て支援に係る様々な関係機関を対象としたアンケートということなんですが、どのようなところに伺ったんでしょうか、お伺いします。

主にこれは要対協、子ども家庭支援ネットワークに加わっている機関等を対象として御意見を伺ったところです。

ありがとうございます。では、民間でフリースクールをやられているところですとか、そういったところには聞いてはいないですかね。

対象としたところでは──ちょっとお待ちください、例えばボランティア団体ですとか、それから朝陽学園のような子どもを預かってくださる施設等についても対象にしております。

分かりました。
あと、実態調査ということなんですけど、例えば不登校ですとか、いろんな事情があって不登校になっている方とか、そういったなかなか接点が持てない方に対してのアンケートというのは取られたんでしょうか。お伺いします。

不登校、今学校に通っているかとかというようなことについては調査はなかったかなというふうに思います。学校については、学校に通っていて楽しいかとか、楽しくないとかというようなことを前回と比較をしたりしていること、それから先生とか友達と会うということを楽しみに感じているか、感じていないかというような、そういう聞き方をした項目はございます。

ありがとうございます。実態調査というところで、そうすると、児童扶養手当の受給世帯の方とかに一斉に書類を送付したりとかって、もう課題として分かっている方たちに聞いたという形ですか。お伺いします。

基準としては、児童手当の受給世帯との比較ということで、これ、一番最初は東京都のほうが5年前に実施していて、その東京都の調査と三鷹市を比較してみようということで始まっているので、同じような基準で実施しております。これは子育て支援課のほうから、受給の世帯について抽出をして、そこの全戸の家庭に対して調査をお送りさせていただいたということです。

ありがとうございます。私自身が感じたのは、この調査結果を聞いて、今本当に学校に行けていないですとか、そういった当事者のお声を聞くと、もっと切実な御意見とかを聞いているので、その実態調査というのはどこまで踏み込んでされているのかなというのをちょっと疑問に感じたところがあって今伺ったんですけども、結構民間のフリースクールに行っている方とかは、学校に行けなくて民間に行かれているという声も聞いているんですけど、そういった必要性とかというのはどのようにお考えでしょうか。

これ、不登校ですとかということでの調査ではなく、経済的な状況で、経済的課題がない御家庭との比較というところでスタートしておりますので、そういった視点のところはやや色が薄いのかなというふうに考えているところですけれども、学校で授業が分かりますかとか、楽しみにしているか、先生と会うのは楽しいのか、そうでないのかというような聞き方をしていますので、ある一定の把握はできているのかなというふうに考えているところです

ありがとうございます。
この調査結果を基に総合計画をつくっていく、これは一部かもしれないですけども、こういったアンケート結果を基にこれから総合計画をつくっていくというところで、これからのこの総合計画は、さらにいろいろと複雑な支援に対して踏み込んでいかなきゃいけない総合計画になると思うんですけども、前回の東京都のとお話があったんですけど、これ以上何か調査とかという予定とかは考えはないですか。

この調査は、いろんな施策を考える中の1つのデータとして扱うものでございます。この子ども総合計画については、子ども・子育て会議でも審議をさせていただいております。そこには保護者の方も入っていらっしゃいますし、小・中学校の校長、もしくは保育園だとか幼稚園だとか、そういう関係者も入っておりますので、この数値を使いながら全体の、先ほどのお話がありました不登校もそうですし、何か発達のことを気にされる方への支援とかも含めて、いろんな事業を入れ込みましょうというお話をする中で、皆さんから御意見をいただいてやるものですので、ここで出た数値だけで施策を考えていくものではないというものでございます。

分かりました。いろんな地域の子育て支援をしている方ですとか、いろんな方たちにお伺いしながら、これも取り入れてつくっていくということで、1つの指標でということで、分かりました。ありがとうございます。
続きまして、学童のことについてに移ります。国の定義に合わせて待機児童ゼロということで、今まで本当に拡充でしたり、多様なニーズへの対応ということで、育成料の値上げというのは致し方ないのかなと思う部分なんですけども、主にどういったところが運営経費の増加になっているとお考えか、お伺いしてもいいですか。

学童保育所の管理運営費の大部分は指定管理料が占めております。指定管理料の中身は、やはり職員の方の人件費が主なものになっております。ですので、ランニングコストとしては人件費的なところが増えてきていると。人件費が増えてきているということと、あとお預かりする児童が増えていますので、職員の方もすごく増えてきていますので、全体的な額は増えているところがあります。このほか、表の整備状況にありますが、各年度整備事業を実施しておりますので、こういった経費も、これは毎年一定ではないんですが、かかってきているというのも結構大きな経費にはなっているところでございます。
以上です。

ありがとうございます。やはり当事者からすると、1,000円上がっていくということに対して致し方ないと思うんですが、やはりどうにか据置きできなかったのかなというところもあるんですけども、いろいろな経費がかかっていくということで、分かりました。
あと、障がい児の入所についてなんですけども、これも拡充ということで議会でもありまして、6年生まで拡大するということで、大変ありがたいんですけども、当面、障がい児ではない児童については、障がいのある児童以外の児童については、地域子どもクラブを全校で毎日実施にしていくということなんですけども、今後、可能性として、4年生以降の放課後の居場所、学童の充実というのは検討はしていく方向性ありますでしょうか。

今回お示ししている中では、学童保育所の障がいのあるお子様以外については、当面の間、3年生までとさせていただいております。学童保育所自体が今、整備を拡充しながら、何とか今、待機児童ゼロを継続しているという状況にありますので、4年生以降を受け入れることについては現在は難しいと考えているところです。この先、学童の保育所の需要が落ちていったりとかいうこともあるかと思いますが、そのときはまた検討になるのかなと思っております。

ありがとうございます。先ほど部長からお話もあったように、4年生以降になると、習い事でしたり、自分で時間を使っていくというような形で、学童の需要としては少なくなっていくというのも一部あると思うんですけども、保護者の意向としては、やはり4年生は移行期間として学童に行けることを望まれる方がやはり多いのかなというふうには感じていますので、まずは全校での地域子どもクラブの毎日実施かとは思うんですが、そういった視点も常に検討していただけたらありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
最後に、公私連携保育所に移行する件についてお伺いします。これから、保育園も待機児童がゼロという形で、幼稚園も定員が少なくなっているという中で、そういったところの対策もあるのかなとは思うんですけども、この公私連携型にすることで何か今までと変わったりというようなことはありますでしょうか。保護者に対しても、手続ですとか申請とかで。

この公私連携化、形的には私立保育所ということになるんですけれども、公私連携ということで、基本的には市と法人のほうで協定を結んで保育を実施していきます。協定の内容につきましては、今、委託で4園やっていますけれども、その仕様書に書いてあるような内容、そういった内容を盛り込んでいくので、保育の継続性というのは保てると思っています。ただ一方で、延長保育の考え方ですとか、給食費の徴収が、今、市のほうで徴収をしているんですけれども、今度は事業者のほうで徴収していただくことになるとか、そういった細かいところは変わる点はあるので、そこは保護者のほうにも丁寧に説明していきたいと考えています。

分かりました。ぜひ保護者の方にしっかり説明をしていただきたいと思います。そうですね。保育園、待機児童ゼロということで、いろいろと対応していただいていると思うんですけども、保護者の方が不安にならないように、この移行についてもしっかり進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。