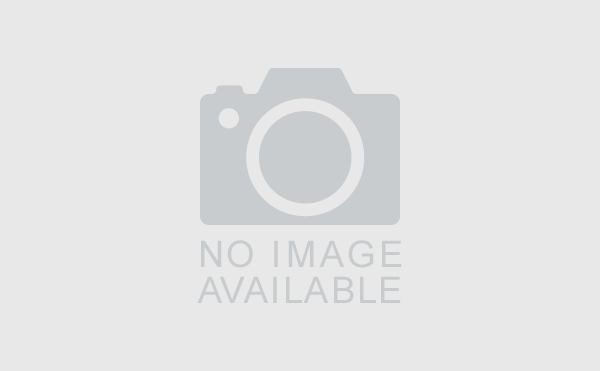令和6年 第4回三鷹市議 定例会
2024年12月3日 市政に関する一般質問

おはようございます。議長に御指名いただきましたので、通告に従い市政に関する一般質問をさせていただきます。
今回は、商店会を活性化するまちづくりについて質問をいたします。

本市は、これまで駅前の再開発がなかったことや、大型店舗が少ないからこそ、商店会の小規模事業者との連携が強く、まちづくりの重要な観点として商店会支援に大変力を入れてきたと理解しております。本市では、2007年に三鷹市商店街の活性化及び商店街を中心としたまちづくりの推進に関する条例を施行し、にぎわいと交流の場の創出、消費者の利便性向上、安全で安心な環境整備、環境負荷の低減、地域福祉の推進を基本理念に掲げ、商店街を中心としたまちづくりを進めてきました。また、現在は三鷹市産業振興計画2027策定に向けて検討が進められていることも承知しております。
しかしながら、これまでの取組において、商店街の持続可能な発展や地域全体の活性化にどのように結びついているかを改めて確認したく、さらなる実情の把握が必要であると考え、商店街が持つ歴史や背景、時代に合った支援を伴走しながら、商店街と一緒に進める必要があると考える立場から質問をいたします。
急速に変化する社会情勢や人々の生活行動の中で、近年はコロナ禍の影響による消費行動の多様化が商店街に大きな打撃を与えました。その結果、商店街を取り巻く環境は一層複雑化し、解決すべき課題が増大しています。従来の設備やハード整備を主体としたアプローチから、人を中心としたウオーカブルなまちを目指し、人々が歩きやすく、交流や循環を自然に生み出す仕組みを意図的に設けることが重要であると考えます。さらに、様々な商品を販売、提供する商いの場としての機能と、地域の人々の交流を促進する公共の場として、事業者主体の運営から一歩進み、社会的機能も両立させた商業振興と地域振興を一体的に進めるべきと考えます。また、本市の商業振興ビジョンを地域住民や商店主と明確に共有し、次世代に三鷹の魅力あるまちを引き継ぐことが、持続可能なまちづくりの基盤となると考えます。
(1)、商店会の現状と課題について。
まず、商いの場である商店街は、商店主が主体性や持続性を持って活動することが大前提であります。これまで商店街を利用する人々の消費行動から、自然と生まれるにぎわいがありました。しかし、人々の消費行動の多様化により、そのにぎわいは薄れつつあります。
そんな環境変化において、質問1、第5次三鷹市基本計画に掲げている魅力あふれる活力・にぎわいのまちとは、単に人が集まるだけのまちではないと認識しています。具体的にどのようなまちづくりを目指しているのか、市長の御所見を伺います。
次に、商店会の現状について伺います。

おはようございます。それでは、私のほうから幾つか御答弁させていただきます。
まず、質問の1、魅力あふれる活力・にぎわいのまちを目指すまちづくりについてという御質問でございます。産業分野におけるまちづくりにおいては、市民の利便性向上につながる持続可能な経済活動を基盤とし、まち中で商店主や地域住民、来街者が緩やかにつながり、まちの愛着醸成につなげていくことが必要だと考えています。そのためには、居心地のよい空間づくりの視点や、様々な立場の人が緩やかにつながる交流の場づくりの視点によるまちづくりのビジョンや方向性を共有し、鮮度の高い情報発信により、それぞれの商店会で商店街のファンを獲得しながら、商業を通じた地域コミュニティの創生を目指しているところでございます。
私は、商店街のファンづくりというのは大変重要なことだと思っています。そんなにたくさんの商店街で実施しているわけではありませんけれども、目立つところでは中央通りの商店街で、イベントや様々な事業の展開のときにファンの人たちに臨時に手伝ってもらう、学生さんもいっぱい来るみたいな、そういうことをやっていらっしゃいます。その実績は、私は相当大したものだなというふうに思っています。どうしても商店街というのは、個店というのは、古くからある場合には大体住居と一緒になっている店舗が多いわけでありまして、もともと御質問者も御指摘のように、家族経営でやっている場合が多いわけです。ですから、そういう意味で、後継者がいない場合に、それが営業している店舗の閉店につながっちゃうという、後継者問題を潜在的に持っているわけですよね。ですから、そういうファンづくりがイコール後継者づくりになるとは限りませんけれども、何らかの形でそういう外部の人たちといいますか、商店外の人たちの力や、あるいは能力とかそういうものを、専門性などを生かしていくということはかなり必須の問題だというふうに私は思っています。
業界は全く違うんですけど、似たような例でいうと、だから農業がそれで成功していますし──全然条件が違うのでイコールで見ることはできないんですけれども、後継者が自分の家族も含めてどんどん出てきているというのは、意外と農業は援農ボランティアも含めて、あるいは市民農園という形も含めて、経営の中で外部の人たちの力を借りているということが多いのではないかと思っていまして、それはJAが横断的に農家の方たちとつながっているということもあって、割とやりやすい環境にあるのかなというふうに思っています。イコールで見ることはできませんけれども、そういう開かれた形で商店街が活躍していくことは、これからの高齢化社会において、御指摘のようにウオーカブルなまちづくり、歩いて楽しいまちをつくるには、やっぱり歩いて行ける範囲の中で商店街が成立しているということが大変重要なことでありまして、一定のそういう蓄積といいますか、それをしていくためにも、商店街自身もまさにそういう形で変わっていくことが大変重要なのではないかなというふうに思っているところでございます。
前の質問者が質問されていましたけれども、立地適正化計画というのは、まさにそういう中央で考えているのではなくて、三鷹で考えている、私どもが考えているのは、歩いて通えるところにそういう商店街も含めて、民間の力も含めて、それぞれのところで中心的なところをつくってほしいという、そういう計画であります。ですから、三鷹がやってきたコミュニティ行政の展開からいえば、コミュニティ商店街みたいな形で展開されていくことが、私たちの住宅都市としてのふさわしい、魅力あふれる、そしてにぎわいのある、そういうまちづくりにつながっていくものというふうに思っているところでございます。そういう意味で、もちろんこれによって補助金が下りるとかそういう話もありますけれども、重要なのは、それをなぜやるのかということは、そういう目標を──住宅都市である三鷹にとってどういう形で高齢化社会、少子化社会に対応していくのか。やっぱり歩いて行けるところ、乳母車をやりながら公共的なサービスも、そして商店街の様々な買物も十分対応できるまち、それが私どもが目指すまちなのではないかというふうに考えているところでございます。

質問2、これまでの商業振興施策の評価と、商店数が減少し、衰退傾向にある商店会の現状と課題をどのように分析しているのか、御所見を伺います。

鎮目 司さん
私からは市長の答弁に補足をいたしまして、残りの質問に順次お答えいたします。
初めに、質問の2点目、これまでの商業振興施策の評価と商店会の現状と課題についてです。市の商業振興施策において、商店会のイベント事業への補助など、主に資金面での支援により、にぎわい創出に寄与してきました。しかし、商店会の現状は、後継者不在による廃業や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を要因に、実店舗数や加入者数、若手商店主の数が減少し、担い手不足に直面するなど厳しい状況にあると認識しております。今後におきましては、商店会への補助による支援に加え、商店街エリアへの面的な支援や各個店の付加価値向上への取組支援が必要だと、課題として認識しております。

質問3、これまで商店会は、地域経済やにぎわいの要として、また地域住民のインフラ機能としても重要な役割を果たしてきました。今、価値観やニーズが多様化し、集客力や話題性に乏しい商店街での消費行動が低下してきている中で、商店会の新たな役割として、地域情報の発信や高齢者や子どもたちの見守りなど、福祉の観点からも重要な役割を担うことが考えられます。こうした新たな役割から消費行動につながるケースも生まれつつあります。助成金や補助金だけでない今後の商店会の新たな可能性を視野に入れた支援の方向性について御所見を伺います。

質問の3点目、今後の商店会支援の方向性についてです。地域の特性に合わせ工夫を凝らした取組を実施している商店会による好事例の事例研究会の開催などにより、情報共有の場づくりを行うほか、商店主や地域住民等による緩やかなつながりの場を設け、商売を通じたコミュニティの広がりにより、商店街のファンをつくり、まちへの愛着と滞在時間の増加を目指してまいります。

続きまして、市民の利便性向上という観点から、質問4、市内の商店街では購入したいものがそろわないなど、消費者のニーズに対応できていない現状があり、厳しい経営環境の中で、商店主側の努力だけでは商店街の利用促進を図ることは難しくなっています。まちに必要な業種を誘致するなど、市民の利便性向上につながるエリアマネジメントのような仕組みをつくり、商店街全体の利用促進につなげる対策が必要と考えますが、市の御所見を伺います。
続きまして、事業者支援についてお伺いいたします。

質問の4点目、商店街の利用促進に向けた対策についてです。現代社会の消費者のニーズは多様化しており、市内の商店主の努力だけで対応するには一定の限界があると認識しています。市では、これまで創業支援や新規出店者への支援金など立地誘導施策を展開していますが、今後の事業実施に当たっては、より複雑化、多様化する消費者ニーズに対応するため、商店街全体の出店状況や業種のバランスなどの視点も踏まえ、まち全体の利便性の向上につなげていくことが必要だと考えております。

質問5、商店主や経営者の高齢化による後継者問題や、店舗等の老朽化などが理由で事業を継続できない店舗が増加傾向にあります。現在の事業者支援メニューには、補助金や三鷹商工会による経営相談や財務相談等がありますが、今後さらに店舗は減少し、ますます拍車がかかると考えます。同族経営、同業種経営だけでない、三鷹で事業をしたい方とのマッチングなど、新たな対策も必要と思いますが、市の御所見を伺います。

質問の5点目、商店の事業継続に向けた新たな対策についてです。事業承継については、これまで三鷹商工会との連携により、セミナーの開催や相談体制の確保を行ってまいりました。三鷹商工会によると、事業者の事業承継に向けた着手の開始時期が遅れ、円滑な経営者交代が進んでいないケースが多いことが指摘されております。市としましては、なるべく早期に着手することで、資産の譲渡や第三者承継など、多くの選択肢が広がることを周知啓発していくほか、関係機関との情報共有に努め、広域的に支援を行っている東京都事業承継・引継ぎセンターや東京都中小企業振興公社等によるマッチング支援との連携により、店舗の維持、廃業の減少に取り組んでまいります。

質問6、商店会の担い手不足解消、店舗の増加に向けては、若い世代の新規参入を期待するところです。本市はほかの自治体に先駆け、まちづくり三鷹主催のビジネスプランコンテストや三鷹起業塾など、長年創業支援について積極的に展開してきたと理解しています。しかし、時代の急速な変化に伴う働き方の多様化に対応し、若い世代が三鷹での事業意欲を高められるような仕掛けや多様なチャレンジを促す必要性があると考えますが、今後の取組について伺います。
続きまして、商店会の広報についてですが、商店会独自でも助成金等を活用し、商店会チラシやパンフレット、ホームページ、SNSも活用されているところが多くあります。三鷹市のホームページにも、「商店街の御案内 地元の魅力再発見! 商店街に出かけよう!」というページで商店会の一覧があります。外部リンクとホームページリンクに飛べる仕組みになっております。ホームページについては商店会独自のページですが、この外部リンクというのは、地域情報アプリ「ミィね!mitaka」と連動しています。その状況についてお伺いします。

それから、続きまして質問の6、若い世代の事業意欲、挑戦を促す取組について御答弁させていただきます。みたかビジネスプランコンテストについては、全国から応募が寄せられる一方、コンテストの応募者の地域性が希薄であることや創業後の成長支援が、こちら側の問題としましては不十分であるという課題がございます。今後、創業の地として選ばれるため、株式会社まちづくり三鷹との連携により、三鷹で開業する創業者を対象とした育成カリキュラムの実施を検討してまいります。これにより、コーディネーターや金融機関などによるサポート体制を構築するほか、令和7年度に開設予定の三鷹産業プラザ、新創業支援施設におけるチャレンジスペースの活用など、ソフト面、ハード面の伴走的な支援により、三鷹での挑戦や成長を支援してまいります。
御指摘のように、様々な形でまちづくり三鷹も、そういう三鷹で創業したいという人たちを支援する、支える仕組みとして十分まだまだ活躍していただかなければいけないと思っていますので、ぜひ連携しながら、御指摘のような点を三鷹としても頑張っていきたいというふうに思っています。
私からは以上です。ありがとうございました。

質問7、商店会の広報ツールとして、三鷹商工会が運営している地域情報アプリ「ミィね!mitaka」があり、各商店会の情報を掲載しています。アプリのシステムとしては機能性が高く、商店会の活性化に有効なアプリであると認識していますが、市内全域の商店会の最新情報の発信はできておらず、現在はその機能を十分に発揮できていないと感じます。市としても商店会の広報を支援する取組が必要だと考えますが、御所見を伺います。
次に、商業振興と地域振興について伺います。
地域コミュニティ機能が弱体化している中で、そのための対策も急がれますが、商店街を核として多様な人を巻き込む取組は、これまでも多くの成果があります。そして、地域振興にもつながることから、さらなる強化が必要と考えます。

質問の7点目、商店会の広報を支援する取組についてです。三鷹商工会のアプリ「ミィね!mitaka」は、令和6年10月末時点で累計1万3,200件のダウンロードがあり、これまで商店会情報のほか、みたか散策マップ、みたか太陽系ウォークなどとも連携をし、これまで地域情報をPRする広報媒体として一定の効果を発揮しております。一方、最新情報の収集や更新作業に係る体制や費用面における課題があります。これについては、三鷹商工会で今後の活用について検討を進めていると伺っているところです。
今後の商店会への広報支援につきましては、各商店会や個店の発信力を高めるため、三鷹商工会等との連携により、SNS活用セミナーの開催や、アドバイザー派遣などによる支援を進めてまいります。

質問8、これまで商店会は、地域におけるにぎわいの創出に大きく寄与し、地域の人と人のつながりや地域コミュニティづくりに商店会が大きく関係してきたものと認識しています。商業機能の回復は、地域住民や地域コミュニティを支援することにもつながると考えますが、市の御所見を伺います。

質問の8点目、商業環境の回復と地域コミュニティについてです。商店街は単に市民の買物の場としてだけではなく、魅力的な商品やサービスの提供、商店主との会話、商店街に集まる市民等とのコミュニケーションなど、実店舗ならではの様々な機能や魅力を有しております。そうした場で生まれる多様な交流は、地域における緩やかなつながりやまちへの愛着を高めることから、商業機能の回復は、地域コミュニティの視点からも大変重要な課題であると認識しています。

最後に、本市の産業振興と市民主体のまちづくり活動を行うまちづくり三鷹へは、商業振興と地域振興をつなぐかけ橋となることを期待することから、質問9、まちづくり三鷹では、これまでも買物支援、創業支援などの実績があります。地域に身近な機関として、これからさらなる商業、地域振興への取組を期待いたします。市民や地域のニーズをいち早くキャッチし、全市的に商店街が抱えている課題の解決と地域ニーズを満たすまちづくりの勉強会や講習会などを行うなど、より実践的な取組が必要と考えますが、まちづくり三鷹へのさらなる支援や、本市との連携の必要について御所見を伺います。
以上で壇上での質問は終わります。御答弁によりましては自席での再質問を留保いたします。御答弁のほどよろしくお願いいたします。

質問の9点目、まちづくり三鷹への支援及び連携についてです。今年度から株式会社まちづくり三鷹への委託により、商店街にぎわい創出支援事業を開始し、市内商店会へのヒアリング等により実態や課題の把握のほか、商店会向け相談受付体制を設置しております。また、各商店主を対象とした課題解決や商店街振興等を目的とした事例研究の機会を設ける予定でおります。今後も引き続き、同社の機動力と地域のネットワークを生かし、地域ごとのニーズに応じたまちづくりに向けて、商店主や市民を交えたワークショップの開催や商店街のファンづくりに向けた市民との交流の場づくりなど、連携を深めてまいります。
答弁は以上となります。
~再質問~

御答弁ありがとうございました。順次再質問させていただきます。
まず、質問1に対して、市長のほうから御答弁ありがとうございました。ウオーカブルなまちづくり、ファンづくりというお話もいただきまして、まさにそのとおりに進めていただきたいなと思っております。
今回この質問をした理由は、三鷹市産業振興計画2027(素案)を拝見した際に、にぎわいのイメージとしてマルシェの写真が掲載されていたんですけれども、様々なまちづくりの計画に、こういったマルシェの写真を、にぎわっている様子の写真が掲載されているんですけれども、このにぎわいがもしイベントを通してこういうにぎわいをイメージしているのであれば、商店会の大変な状況の中で、イベントというものは関係人口を増やす目的で商店会が意図的につくっていたりですとか、もちろん助成金などをもらっているんですけれども、そういった関係人口を増やすためのイベントとしてスポットでできているにぎわいになっておりまして、平日の昼間の日常は、三鷹駅前ですら閑散としているのが現在の三鷹駅前の状況です。イベント等を行っていない、に

再質問にお答えいたします。
質問議員御指摘のとおり、産業振興計画の中で、例えば中央通り商店会におけるM-マルシェの様子の写真などを掲載していることは事実でございます。今、御質問にもありましたが、近年のネットショッピング、ECサイトの普及により、実店舗の減少というのは全国的にも見られる現象です。そうした中で、実店舗のよさというものは2つあると思っております。1つは体験、そしてもう一つは交流です。そうした体験や交流というのは、ネットショップの技術が今後進展しても、恐らく当面の間、リアルな体験と交流を電子上で再現することは非常に難しいと思います。そういう体験や交流を商店街の中で、実際に来街者を含め、市民の皆様に体験していただくものとして、イベントの実施というのは大変有効だと思っております。そして、そのイベントに来ていただいた中で、商店主さん同士がまた交流し触れ合い、顔なじみの関係をつくっていただく、そうした関係づくりができることで、それはやがてイベントのない日であっても、あの商店街に行けばあそこの商店主さんがいらっしゃる、そしてお店の方がいらっしゃる、そして常連のお客さんがいらっしゃる、そうした人のつながりができることで、中長期的に見ると大変イベントの効果は大きいと考えております。
ただ、イベントだけが盛り上がって平日は人が閑散としている状況、これがあるということも事実として把握はしておりますので、何とかイベントの活力を平日につなげていけるよう、商店主の皆さんとも情報共有をしながら今後の検討を進めてまいりたいと、そのように考えております。
以上です。

ありがとうございます。私もイベントを通して様々な交流が生まれているということは大切だと思いますし、イベントは必要なまちづくりの1つだと思っておりますので、日常的にも盛り上がるような形で、にぎわいというのを考えていただけたらなと思っております。
続きまして、質問2に関しまして、衰退傾向にある商店会の現状ということなんですけれども、私の生まれ育った上連雀エリアの商店会も、今年度をもって解散することになりました。会員数減少や人材不足等、継続できない理由を考えると致し方ないと思いますが、近所の商店会がなくなることを本当に残念に思っている市民の方がたくさんいらっしゃいます。このように商店会をやむを得ず解散しなければならない現状で課題となるのが、まず解散するためのサポートと考えます。商店会解散に向けて、何か体制など考えられていることはありますでしょうか。

再質問にお答えいたします。
商店会の解散など、担い手不足の問題は大変深刻であると私どもも考えているところです。そうしたところの担い手不足の支援につきましては、やはりその商店会ごとに課題が異なると認識しておりまして、現在進めておりますまちづくり三鷹と連携したにぎわい創出支援事業でも、実態調査として各商店会にこちらから伺っていろんな課題の聞き取りをするということをしておりますが、今後におきましても、まさしく寄り添い型の伴走型の支援としまして、実際に商店会の皆様、各商店会のほうに私どもが出向いてしっかりお話を伺って課題を捉え、それに合った支援をしていくという、そういうきめ細かな支援が必要だと思っております。制度として補助金制度をつくることもできますが、やはり課題というのは、これは町会・自治会などもそうなんですが、やはり団体ごとに抱えている課題というものはよく伺わないとなかなか見えてこないところもございますので、まずはそうしたところをこちらが伴走型の支援でお話をよく伺う、そういったことが一番大切なのかなと、そのように考えております。

ありがとうございます。伴走型の支援ということで、よろしくお願いいたします。
また、商店会の解散後のまちの変化についても課題があると感じております。今回の上連雀地区の商店会は街路灯があります。今回、商店会の解散と併せて街路灯も撤去する形になっております。撤去するための手続も東京都とのやり取りが大変であったと聞いておりますが、街路灯が撤去されると、何十年もあった明かりがなくなります。地域住民の安心安全の要であった明かりがなくなることは、地域の方々の不安にもつながると思いますが、こういった街路灯に関しても、商店街が抱えている街路灯はたくさんあるかと思いますが、それに伴う支援についてはどのようにお考えか、お伺いいたします。

再質問にお答えいたします。
商店街の管理されている街路灯について、質問議員さんおっしゃるような課題があることを私どもも認識しておるところです。具体策について今すぐに申し上げる段階ではございませんけれども、しっかりと状況を把握して、適切な支援をしてまいりたいと思っております。状況については現在こちらでも把握をしておりますので、そのように検討を進めてまいります。
以上です。

ありがとうございます。
昨日夜、私も山中通りの山中商栄会から泰成商店会に向けて車で走ってみました。やはりそこに街路灯がなくなるというところで、すごく狭い道路の中を人が歩くことで不安に思う方がいるのかなと思いますので、対応のほうも考えていただければと思います。
続きまして、商店会の合併に関してなんですけれども、先日も小金井市では、コロナ前から協議が行われていた2つの商店会の合併がありました。新たに商店会として設立をされたようです。今後、三鷹の商店会においてもこのような動きも想定できるかと思いますが、どのようにお考えでしょうか、お伺いします。

再質問にお答えいたします。
商店会の合併につきましては、今こちらのほうにそういうお申出をいただいている段階ではございませんけれども、そうしたお申出がありました際には、先行事例などをきちんと調査をして、適切に支援をしてまいりたいと思います。
以上です。

今はないと思うんですけれども、今後想定できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、質問3です。商店街の新たな価値と商店街の多機能化についてなんですけれども、駅前の商店会の事例として、ある商店に高齢者が毎日集まるようになりました。地域の方、店主の方と交流が深まる中で、認知症を患っていることや高齢者のひとり暮らしで生活に困っていることが分かり、また駅前中央通りで高齢者が転ぶ機会が多発することから、商店会と社会福祉協議会、地域包括支援センターと連携して、この夏に商店会に車椅子が設置されました。こういった動きは商店会主体で動いていったんですけれども、また通常コミュニティ・センターなどで行うシニア向けの相談サロンも商店会の中で実施したことから、商店会に来る課題を抱えていた多くのシニアの方が包括支援センター、また関係機関につながることができまして、こういった商店会から福祉に関しての動きもあります。このような事例についてはどのように思いますでしょうか。

再質問にお答えいたします。
商店会が担っていただいている新しい福祉的な役割というのを私どもも大変評価をしております。今、御質問にもありましたが、特に中央通り商店会などでは取組が盛んに行われておりまして、例えばみたかスペースあいに車椅子を配置し、具合の悪い方などに使ってもらう取組ですとか、あとタクシー会社と連携をして、お客様でタクシーが必要な方にすぐにタクシーを呼んであげるようなそういったサービス、そしてまちづくり情報コーナーとして、商店街の様々な情報を掲示しているサービス、すばらしい取組が今徐々に広がっているのを私ども認識しております。こうした自主的にやっていただく取組に加えまして、例えば場づくりとして、コンビニエンスストアに商店街のベンチを置いていただいたり、そういったことも一部進められるというふうに聞いておりまして、こうした取組が市内のその他の商店街にも広がっていくことを私どもも期待しているところでございます。
以上です。

そういった動きの中で、支援のほうも検討していただければと思います。
もう一つ事例として、三鷹の駅前、私の事例になってしまうんですけれども、商店会を拠点として子育て支援活動を始めた際に、商店会が先ではなくて、地域の子育て支援への理解とまちの居場所を増やしたくて始めた経緯がありました。その結果、子育て世帯が多く行き交うことで、商店会の商品のラインナップが変化するなど、商店会の方々の子育てに関する意識変動も見られていきました。子育て当事者から、まちが優しくなったと声をいただき、さらに子育て世帯に向けたイベントを通して、三鷹市内全域はもちろん、一番遠い方で沖縄からも三鷹に来るような、そういったような動きもありました。今回例に出したような、まちのマネジメント次第で人の行動変異が生まれるかと思います。特に高齢者や子育て世帯に対する商店会の利用価値は高くなると思われますが、御所見を伺います。

再質問にお答えします。
今、質問議員さんおっしゃるとおり、様々なそういった活動が多様に展開していくことは、三鷹市が考えているにぎわいのまちづくりにおいても大変重要なことだと思っております。そうした取組に今後、様々な新しい支援の形として適切に支援ができるよう、そちらのほうについても検討してまいります。

よろしくお願いします。商店会のにぎわいづくりの可能性として、そういったいろいろな事例を支援していっていただければと思っております。
続きまして、質問5です。商店主の後継者問題等なんですけれども、中小企業庁の統計では、これから5年以内に経営者がリタイアする半数は後継者が決まっておらず、廃業を選択せざるを得ないと言われています。三鷹で事業をしたい方との三鷹独自のマッチングでしたり、事業承継のサポートなども効果的ではないかと思いますが、先ほどまちづくり三鷹のほうでもそのようなことを進めていくというふうにお話がありましたが、具体的な創業支援にもつながるので、ぜひそのようなことも併せて検討していただけたらと思っております。
また、商店会の課題は、地域性や状況も異なります。だからこそ状況に合わせた伴走支援が必要かと思います。商店会再生に向けた試みとしては、商店会に関わる人材育成、交流を促進するための商店会同士のネットワークを強化することや、杉並区では商店会活性化サミットと題し、商店会の方々とまちづくりに関する関係者で様々なテーマをディスカッションする会などを活発に行われていますが、三鷹市において、現在の市内商店会の連携はどのようにされていますでしょうか、お伺いいたします。

再質問にお答えします。
商店会の連携として、例えば商店主を対象としたセミナーなどの開催を行っているんですけれども、それほど出席率は高くないというのが課題の1つとなっています。今後におきましては、やはり商店主さん同士の情報共有も大切ですが、それに加えて、三鷹の目指す歩いて楽しいにぎやかなまちづくり、そのビジョンを達成するために、やはりいろんな主体が関わる情報共有の場が必要ではないかなということで今検討を進めております。例えば、その中には若い世代、学生さんであったり来街者の方、もしくはまた全く違う業種の事業主さんなども入っていただき、どういったまちが望まれているのかというニーズの把握の部分で多様な主体によるプラットフォーム、そうしたものがあると非常に有効なのではないかということで、今検討を進めているところでございます。
以上です。

よろしくお願いいたします。
続きまして、商店会の担い手不足解消についてなんですが、地域で新たな事業を立ち上げるとき、商店街を選択することは、地元で一定の人流がある場所であり、また商店会にとっても新たな店舗が増えることで商店会の活性化の一助になります。双方にメリットがあることから、こちらを進めていければと思うんですが、商店会に出店するということは店舗を持つ不安や初期投資の負担からちゅうちょしてしまうという声も大きく聞いております。地域におけるスタートアップを支援する取組について、先ほどまちづくり三鷹のチャレンジショップなどとありましたが、もう少し具体的に、チャレンジショップでしたら、シェアキッチンという具体的な取組が必要と考えますが、具体的な内容を教えていただけますでしょうか。

再質問にお答えいたします。
近年、新規に市内で出店された事業者さんにつきましては、商店会に加入せずにやられているところも多いと聞いております。そうしたところには商店会の加入のメリットなど、そういったものもきちんとこれからは伝えていくことが大事だと思っております。その中で、先ほどの答弁と似てしまうんですが、やはり新規出店者の方に、そういう方のニーズがどういうところにあるのかということを我々がきちんとニーズを把握することが最初の第一の課題だと思っておりますので、まちづくり三鷹、商工会と連携して、そこをきちんと把握できるような体制をつくりたいというふうに考えているところでございます。

よろしくお願いいたします。
また、三鷹駅前では、今後マルシェの際にキッチンカーも配置できるようになります。多様な店舗の在り方は、若い世代が三鷹でチャレンジしたい、商店会を盛り上げる機会として大変重要であると考えます。本市の創業支援制度などは受けてなく、先ほどもお話がありましたが、商店会に入らないなど、なかなか三鷹につながりがないけれども、三鷹で事業を始めたいという新規出店者をサポートするような体制などは考えられていますでしょうか、伺います。

再質問にお答えいたします。
キッチンカーの普及は急速に各地で進んでおりまして、三鷹においても、例えばコミュニティ・センターのイベントなどでも、最近はキッチンカーが非常に人気であります。そうしたところへの支援というのも、これから市のほうできちんと整理をして、支援ができるように考えていきたいと思っております。
以上です。

様々な多様な出店の仕方という点でぜひ検討していただければと思います。
続きまして、「ミィね!mitaka」の件なんですけれども、このアプリ、本当に活用すればうまく使えるのではないかと思っているんですけれども、何か「ミィね!mitaka」自体を広報をするような、そういったような取組などはされていますでしょうか。

再質問にお答えいたします。
「ミィね!mitaka」の活用につきましては、これまで先ほどちょっと答弁でもありましたが、例えばみたか太陽系ウォークですとか、市のイベントのほうでも一定の活用をこれまでしてきました。その中で、ダウンロード数も増えておりますし、かつ、実は人流の流れを定点で観測する、どこにどういう人が何時の時点でいたかというような、その人の流れを測定するような機能も加わっていますので、こうした機能を今後活用することで、商店会の振興にも役立つのではないかと考えております。
また、その広報につきましては、どうしても「ミィね!mitaka」の単体の広報というのはなかなか難しいとは思いますが、先ほど申し上げた市の関連イベントなどの活用がある際には、広く市の媒体などを使って今後も広報していきたいと、そのように考えております。
以上です。

よろしくお願いいたします。
続きまして、地域コミュニティと商店会におけるお話なんですが、商店街に関わる人材育成や交流を促進するために、商店街に関心を持つ方とつながるような商店会フォーラムですとか、商店街を核としたコミュニティを積極的に取り組むのも効果的かと思いますが、御所見をお伺いします。

再質問にお答えいたします。
商店街の中でにぎわいと交流、再建と交流、そうしたものをこれから活性化させていくためには、質問議員さんおっしゃるように、商店主さんだけではなくて様々な属性の方々、そういう方々が緩やかなつながりができるような、そして意見を共有できるような、そうした場づくりが大変大事だと考えておりまして、検討を進めているところでございます。
以上です。

やはり商店会の方々だけではなく、様々な方と商店街を考えるという機会が重要かと思いますので、ぜひそのような形で進めてもらえればと思います。
現在、商店会からコミュニティが広がっている、商工会の補助金を活用したグリーンインフラプロジェクトやコンポストの取組などの事例を、今後広くほかの方たちにもお伝えしていきたいというようなお話がありましたけれども、ぜひ様々活動が生まれておりますので、そういったことも商店会からのコミュニティというところで発信していただければと思います。
最後になります。まちづくり三鷹についてなんですが、昨年会派におきまして、愛媛県にある株式会社まちづくり松山を視察いたしました。松山の商店街はちょうど再開発を控えていたために、商店街がシャッター街になっている様子も目の当たりにしました。まちが静かで人が歩いていないという状況でした。まちづくり松山では、商店街のエリアマネジメント支援事業を行い、商店街の環境調査や商店主アンケート、商店会の事務局として、商店会をサポートしているとのことでした。事務局機能をまちづくり会社が一括して行うということは、他機関との連携のしやすさや商店会の負担が軽減し、本来の商いに注力しながら、地域との関係づくりを強化できる事例として大変注目するものでした。本市でも、商店会独自で商店会活動が難しい場合や、希望があれば、事務局機能だけほかにお願いする体制も必要ではないかと思いますが、御所見をお伺いいたします。

再質問にお答えいたします。
まちづくり三鷹への支援及び今後の連携について、現在も商店街にぎわい創出支援事業をはじめ、様々な事業で連携をし、まちづくりに向けていろいろ御協力を願っているところでございますが、今後に向けましては、やはりこれまでの事業だけではなくて、多様な主体のニーズをどう捉えていくか、そしていろんな課題が山積している様々な商店会、そこのニーズ、課題をどう捉えていくか、市と共に伴走型支援という形で注意深く丁寧に課題を酌み取り、それを次の施策へつなげていく、そういうことが必要だと考えております。

商店会の人材不足という点からは、やはりこういった事務局機能をほかにお願いするというのは今後必要になってくる視点かなと思いますので、そういったところも想定して考えていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
自力では事業実施が困難な厳しい環境の下、商店会等にオーダーメード型の伴走支援をするなどして、まちづくりの観点からも商店会の意義を問い、10年、20年先も三鷹の商店会が維持できるよう、引き続き支援をお願い申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。