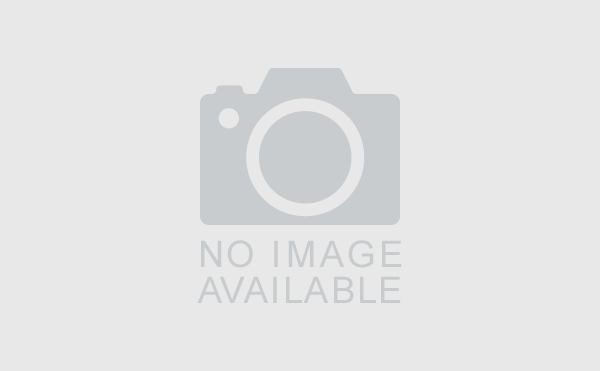令和7年 第1回三鷹市議 定例会
2025年2月26日

議長より御指名をいただきましたので、市政に関する一般質問をさせていただきます。
今回は、本市における未就学児の成長や発達に不安を抱える保護者への支援について伺います。
本市では、これまで他自治体より先進的に行ってきた子どもと子育て家庭を妊娠期から子育て期にわたり切れ目なく支援する体制づくりとして、子育て世代包括支援センターが機能として役割を担い、子ども家庭支援センター、総合保健センター、子ども発達支援センターが中核となり連携することで、全ての子どもたちに対し、本市の包括的な子育て支援の強化を図ってきたと認識しております。
さて、令和6年にこども家庭庁が発足し、児童発達支援ガイドラインも改定されました。その児童発達支援ガイドラインには、児童発達支援センターは、地域における障がい児支援の中核的役割を担う機関として期待するという位置づけから役割として明確化されました。その役割としては、1つ目に、本人支援について。個々の障がいの状態や発達の状況、障がいの特性等に応じた発達上のニーズに合わせて、本人の発達支援、本人支援を行うこと。2つ目に、家族支援について。子どもの発達の基盤となる家族への支援、家族支援を行うこと。3つ目に、移行支援について。全ての子どもが共に成長できるよう、障がいのある子どもが可能な限り地域の保育、教育等を受けられるように移行支援を行うこと。4つ目に、地域支援、地域連携について。子どもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、子どもや家族に包括的に支援、地域支援、地域連携をしていくこととあります。
本市では、発達支援センターが未就学児の発達に関する相談支援の窓口となっております。また、子どもの発達に関する支援としては、乳幼児健診や訪問支援等、様々な形で親子の現状や子どもの発達において市が関与する機会が設けられています。本市としては、発達支援に関する事業方針として、親子の関わり合いの中で大きく変化や成長が見られるという実績からも、親子プログラムに重点を置き、支援をしていることは大変評価しております。
そのような事業方針であることは承知していますが、子育てが始まったばかりで、子どもの成長に一喜一憂する時期だからこそ、子育て世帯に分かりやすい案内や丁寧な相談体制はもちろんのこと、不安を抱える子育て世帯が適切な支援につながることで、さらに三鷹なら安心して子育てができると感じられることが重要であると考えます。
(1)、発達支援体制について。
子どもの発達における相談内容は様々であると思いますが、発達に不安を抱える保護者が孤立せず、子育ての心配や不安を伴走支援し、子どもの成長において安心できる相談体制になっているのか、まずは相談に来てくれることが、孤立しない子育てにおいて支援につながる一歩になると思います。また、不安を抱える保護者にとっての初動の対応が大変重要であり、相談で終わらない継続的な支援が求められると考えます。

質問1、未就学児の成長や発達に不安を抱える保護者からの相談後、どのような体制で適切な支援につなげているか、伺います。

清水利昭さん
1点目の御質問です。未就学児の成長や発達に不安を抱える保護者への支援についてでございます。初回の面談の後に、子ども発達支援センター内におきまして支援決定会議を開催し、お子さんの発達状況や保護者の支援ニーズ等を確認した上で必要な支援内容について検討し、親子への支援方針を決定しています。その方針に基づきまして、市で実施している子育て支援プログラムや相談支援プログラムの活用、また、小児神経科医による医療相談、心理士による発達検査及び助言、さらにはお子さんが通う保育所等に専門療法士が直接出向いて実施します保育所等訪問支援事業など、一人一人のお子さんに合わせて、子ども発達支援センターの職員がしっかり伴走しながら支援を実施しているところでございます。

質問2、発達支援が必要なお子さんを早期に支援につなげる体制として、子育てステーションたかのこは、総合相談窓口としてどのような機能を果たしているのか、また、成果につながっているかを伺います。

2点目の御質問です。子育てステーションたかのこについてでございます。三鷹市子ども発達支援センターは、全ての子育て家庭の子育てと子どもの発達に関するあらゆる御相談に対応しています。子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事業として、センター内に設置している子育てステーションたかのこは、子ども及びその保護者等、または妊娠している方が地域の子育て支援事業や保育施設等を円滑に利用できるようサポートする相談窓口機能を担っています。子育て家庭が身近な場所で日常的に相談することができ、子育ての何気ない相談から育てにくさを感じていることなど、子育てや子どもの発達についての相談など幅広い相談をすることができますが、早期の発達支援につなげる視点からは、保護者の方々の中には敷居が高いと受け止められている御家庭もある子ども発達支援センターでございますけれども、そちらに直接相談をする一歩前の段階で、相談内容を限定することなく、まずは気軽に相談できる窓口となり、その後、必要な支援につなげていく相談の入り口としての役割を果たしています。

質問3、子ども発達支援センターでは、どのような専門職を配置しているのでしょうか。また、センターで対応できない専門的な事案については、どのような体制で次の支援につなげているのか、伺います。
次に、ここ数年の子育て環境の変化として、子育て情報はインターネットやSNSから習得するという保護者が増加したことであります。必要な情報に届かなければ、ある意味、情報の孤立も進んでしまいます。特に保育園、幼稚園に入園するまでの間は当事者同士の交流も少ないことから、孤立しやすい乳幼児の時期の保護者に対し、分かりやすい情報の提供と相談をしてみようかなという体制づくりが必要と考えます。

3点目の御質問です。専門職の配置、センターで対応できない事案についての対応についてです。子ども発達支援センターでは、保育士のほか、保健師、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、嘱託医、こちらは小児神経科医になりますけれども、こういった専門職が発達の支援を行っております。また、子ども発達支援センターにおいては対応が難しい肢体不自由児や先天的な疾患があって装具の作成や定期的な医療機関によるサポートが必要なケースについては、支援の主軸を病院に置きつつも継続的に相談支援を行うとともに、相談支援プログラムや保育所等訪問支援事業なども実施しながら伴走支援を行っています。

質問4、令和5年第3回定例会で一般質問させていただきましたが、総合保健センター、子ども家庭支援センター、子ども発達支援センターにおいて、相談窓口を知らない、相談していいのか分からないなどの理由で困っている保護者への周知や声がけ等で何か工夫はされているのでしょうか。相談までたどり着けない保護者に対して分かりやすい案内、気軽な相談体制の拡充を求めましたが、現在あまり変化が感じられません。改めて御所見を伺います。
続きまして、保育園や幼稚園入園後にお子さんの成長や発達について不安を感じる保護者支援についてです。入園後、個人差はあるものの、集団生活が始まり、言葉の発達や生活等気になることが増える時期でもあります。また、現場の保育士や教員も、特別支援児だけではなく、診断はないものの、個別の対応が必要な子どもに対してさらなる支援が求められます。先ほどの発達支援ガイドラインにもあるように、可能な限り地域の保育、教育を受けることができるよう、保育園、幼稚園も受入れに努めていただいております。協力体制を強化するためにも、本市で保育園や幼稚園との相互理解を深め連携することは、地域の子どもたちを地域で支える体制につながると考えます。

4点目の御質問です。相談にたどり着けないケースへの相談窓口の周知についてです。市では、全ての妊産婦に配布している冊子、子育てガイドや市のホームページ、子育て支援サイト、みたかきっずナビを活用して相談窓口の周知徹底を図っております。こうした取組にもかかわらず、相談窓口が分かりづらいとのお声があるため、両親学級等の講座、新生児訪問、乳幼児健診、親子ひろば事業など、様々な機会を捉え、折に触れて相談窓口の周知を図るようにしています。今年度からは、一部子育て支援事業についての周知ポスターを病院の周産期病棟に掲示依頼するなどの取組も始めました。一方で、最近、ホームページやみたかきっずナビからの非対面での相談が増加傾向にありますので、こうした媒体についてさらに利便性の向上を図る取組を進めております。今後は、市の子育て支援事業に関わってくださっている地域の方々にも周知について広く御協力を依頼するなど、新たな周知方法の拡大、改善について、引き続き検討してまいります。

質問5、保育園や幼稚園の巡回発達相談の件数は増加傾向にあると認識しています。巡回指導を希望する園や子どものニーズに対し、指導回数、指導者の人数を増やすべきと考えますが、御所見を伺います。
次に、市内の幼稚園に通う特別支援児、特別な配慮が必要な子どもたちに対しては、幼稚園も保護者との信頼関係をつくり、園での生活が安心して送れるよう、市の支援を受けながら体制を整えている状況であります。

5点目の御質問です。巡回発達相談の拡充についてです。市で実施している巡回発達相談は、発達の課題や保育、教育を行う上で難しさのある子どもが地域の中で健やかに成長することができるよう、保育所等の職員を対象として、保育、教育活動、環境調整、子どもとの関わり方等についての助言を行うものです。お子さんの発達のためにも、また、保育所等の豊かな保育の実践等のためにも、ぜひ気兼ねなく御活用いただきたいと考えておりますが、より多くの保育所等に偏りなく御利用いただきたいため、一定の利用回数の上限を設定しております。しかしながら、さらに支援が必要な場合には、その回数を超えた巡回発達相談にも対応しております。子ども発達支援センターとしては、相談の回数を増やすことのみでなく、助言の内容が保育所等に、より取り入れやすいものとなるよう一回一回の支援の質の向上も併せて図り、全ての子どもの育ちをしっかり支援する体制を取ってまいりたいと考えます。

質問6、市内幼稚園では、特別支援を必要とする子どもの受入れに対し、規定を上回る補助教員を配置するなど、手厚い対応のために御努力いただいております。また、認定を受けていない特別な支援を要すると判断する子どもたちも大変増加しています。そんな中で、さらなる幼稚園への支援拡充が必要と考えますが、御所見を伺います。
次に、相談で終わらせない具体的な支援についてです。冒頭にも触れましたが、本市では発達支援において、未就学、乳幼児の子どもについて、まずは親子の関わり合いの中で日常的に子どもの成長をサポートしていくということで事業を進めています。私も、大変重要なことだと理解しています。専門家にも御指導いただき、今の本市の発達支援体制があると認識しております。しかし、本市では発達相談の充実があるものの、専門的な療育支援はないことから、その見解について伺いたいと思います。

6点目の御質問です。特別な支援を必要とする子どもの受入れに対する幼稚園への支援拡充についてです。三鷹市では、障がいのある児童の保育に要する経費として、受入れに伴い教職員等を配置する幼稚園に対し、東京都の補助に上乗せをし、支援を行っております。診断の有無に関わらない特別な支援を要する児童の増加に伴う支援の拡充については、児童の発達状況を確認する基準やインクルージョンの視点を持った保育の質の向上等、今後の巡回発達相談や確認体制も含め、検討していきたいと考えております。

(2)、より専門的な療育支援について。
まず、本市では、発達の課題や障がいがあるお子さんの通所施設、くるみ幼児園があります。保護者の皆さんからは、子どもの特性に合わせた手厚い保育が受けられることに安心の声をいただいております。一方で、入園に関する案内や資料が少ないとの指摘もあり、支援を必要とする御家庭に対し十分な情報が伝えられているのか、本市のくるみ幼児園の状況について伺います。
質問7、発達の課題や障がいのあるお子さんの通所施設であるくるみ幼児園について、入園対象者の明確な基準等はあるのか、伺います。また、対象となる子どもたちの保護者に対し、どのような形で入園案内をされているのか、伺います。

7点目の御質問です。くるみ幼児園の入園対象者の基準と案内についてでございます。くるみ幼児園の入園対象者については、発達に課題や障がいがあるお子さんで、市が発行する受給者証を持っていることが入園の要件となっております。また、対象となるお子さんのくるみ幼児園の入園案内については、市の広報やホームページで広く行うとともに、子ども発達支援センターに相談に来られた際のニーズにお応えする形で職員が紹介することもございます。

質問8、くるみ幼児園では、発達の課題に応じた支援を行うことで、お子様の成長が見られ、成果が出ていると認識しています。保護者への適切な案内に取り組むとともに、ニーズに応じて受入れ体制を拡充する必要があると考えますが、御所見を伺います。
続きまして、本市では療育支援はありませんが、親子の関わり合いのプログラムの中でも、保護者が子どもの特性を見据え、家庭での対応から改善を試みるという考えの下、助言や指導をしていると思います。しかし、保護者からは、専門家ではないため、子どもの特性を理解しても、対応には限界があるとの声が寄せられています。また、共働き家庭や兄弟がいる場合など、本市の方針が全ての親子に適切なのかと考えます。発達に関する専門的な早期支援の重要性は広く認識されており、悩みの子どもに合った具体的な支援が提供されることで、発達の改善や成長によい影響をもたらす場合もあります。家庭の努力だけではなく、保護者が専門的な療育支援を希望する場合に、選択肢も必要ではないでしょうか。

質問の8、くるみ幼児園の適切な案内と受入れ体制の拡充についてでございます。私、この施設の状況を見させていただいたことがありますが、非常に私としてはすごく驚いて、よくやっているなという記憶があったことをまず申し上げておきます。くるみ幼児園の入園につきましては、一定の状況にあるお子さんとその御家庭に対して、子ども発達支援センターが一方的に御紹介するという形ではなく、お子さんの状況と御家庭のニーズに合わせて、保護者が選択肢の1つとして検討されるに当たっての必要な複数の情報の1つとして御案内をさせていただいているということでございます。なお、受入れについては、これまで定員に達したことを理由としてお断りしたケースはなく、現状の受入れ体制でニーズを満たしているということで認識をしております。

質問9、本市では、診断の有無にかかわらず特別な支援を要する場合、御家庭や地域での子どもの課題や苦手を理解し合えることを方針として発達支援に取り組んでいることは評価していますが、より専門的な指導やOT(作業療法士)、PT(理学療法士)、ST(言語聴覚士)等による早期療育支援を充実する必要もあると考えます。御所見を伺います。

質問の9、専門療法士による早期療育支援の充実についてでございます。子ども発達支援センターで行う発達支援につきましては、それまでの長い市の取組の積み重ねの経験を踏まえて、令和2年度以降は子どもの持つ障がいに対して直接治療を行う医療モデル型の支援以上に、人の生活上の課題は、人と環境との相互作用により生じるものであるという視点から障がいを捉えまして、人と環境と相互に影響し合う接点に介入するという、生活モデル型の支援に重きを置くこととしております。医療モデル型の支援以上に、ふだん生活を送る場で子ども自身ができることを1つずつ増やしていくとともに、そのために支援者や保護者ができる関わり方を身につけていくことが、子どもの発達にとってより大きな効果を現状もたらしているというふうに思っております。そういう意味で、くるみ幼児園が積み重ねてきたことは、私は画期的だというふうに思っています。
ただし、御質問者にありますように、医療モデル型といいますか、療育訓練にも固有の効果がもちろんございますので、引き続き医療モデル型の支援と生活モデル型の支援をバランスよく組み合わせた発達支援を実施してまいりたいと考えております。
もちろん財源に限りがなければと言うと、いつもの行政の言い訳というふうに捉らえるかもしれませんが、両方あるような形がいいとは思うんですけれども、市としては今、これを特化しながら、現実に様々な子どもたちと接して一定の効果があるというふうに思っていますので、この領域を市としては深掘りしていきたいなというふうに、現在思っているところでございます。
私からは以上です。ありがとうございました。

質問10、現在、本市の公立施設では提供されていない専門的な療育支援を希望する場合、保護者自身が自力で他市や民間団体を探し、選択をせざるを得ない状況です。切れ目のない子育て支援体制を掲げる本市において、そのような御家庭に関しては、切れ目のない支援体制をどう目指していくのか、御所見を伺います。
以上で壇上での質問を終わります。御答弁に当たりましては自席での再質問を留保いたします。よろしくお願いいたします。

10点目の御質問です。専門的な療育支援が必要な子どもへの切れ目のない子育て支援体制についてです。市内における民間の児童発達支援事業所において提供している発達支援で、子ども発達支援センターでは提供していないものは基本的にはないものと認識しておりますが、その実施の回数については、民間事業所のほうが頻回に行っているケースはございます。こうした状況を踏まえて、必要に応じてセンターと民間事業所を併用していただくことが、発達支援により効果を上げるケースもあります。子ども発達支援センターでは、一度相談に来られた方の中で継続した支援が必要なケースには切れ目のないよう、状況や困り事の確認を丁寧に行っています。民間事業所の発達支援を中心的に利用されている方へも同様に状況を伺う中で、必要な情報提供や支援へのつなぎを行いながら、支援を必要とする全ての親子に、切れ目なく必要な支援ができる支援体制を取るよう努めております。今後も、より一層効果的な発達支援を行うことができるよう、他の事業所等とも連携を深めながら、支援を実施していきたいと考えています。
答弁は以上でございます。
~再質問~

御答弁ありがとうございます。まず、市長のほうから質問に対して、医療モデルと生活モデルをバランスよくというお話があったんですけれども、このバランスよくということに対して、現在は生活モデルを重視しているというところがあるんですが、今現在はバランスよくできているとお考えでしょうか、質問いたします。

ただいまの再質問にお答えします。
実は三鷹市も、以前は医療型とか医学モデルというような形での、いわゆる療育というものに力を入れておりました。一定の効果をきちんと上げてきていたところですが、やはり一定のところまでいくと、壁に突き当たってしまうというようなことに非常に悩んでいたところです。そういうところで、まずは親子の愛着形成に始まって、どういう遊びから始めるか、家庭の中で親子でどんな関わり方をするのかという生活自体の在り方、子どもの接し方の部分に重点を置いたプログラムを実施するようになったところ、本当に目に見える効果が、私たち職員が見ても、専門家でない私たちであっても分かるような効果を上げるようになってきたということで、そちらのほうに主軸を置くようにしています。全く医療的なアプローチをしていないということではありませんけれども、回数はちょっと、御利用される方にとってはもう少しやっていただきたいというふうに思われている方もいるかもしれません。
以上です。

ありがとうございます。保護者の方から、やはり療育支援ですとか親子プログラムがあるのは知っているけれども、もう少しそういった専門的な知識でやりたいという方に対しては、現在はどのように対応していますでしょうか。

ただいまの再質問にお答えします。
基本的には私どもは、医学的なアプローチでの領域というのは、1人の方ですと大体月に1回ぐらいのペースで実施というふうになっておりますが、非常に頻回に望まれる方では、毎週受けたいというような方もいらっしゃいます。そういうような部分については、今は民間のほうに、役割分担ということではございませんけれども、お願いするようにしているところでございます。

民間の療育施設との連携はどのようにされていますでしょうか。

ただいまの再質問にお答えします。
連携については、連絡会を設けて、年に数回情報提供を、お互いにどんな取組をしているのか、あるいはこんなお子さんがいるので、あるいはほかの施設でもっと違う取組ができないかというようなことでお互いに連携を図っているところでございます。
以上です。

やはり保護者の方から、そういった要望に対して、月1回と今お話があったんですけれども、そういった連絡会を通して連携をしているようであれば、そういった御案内もしっかりできるような体制をつくってはいかがと思いますが、いかがでしょうか。

ただいまの再質問にお答えします。
私どもいろいろとアピールはしているつもりですが、まだまだ至らない点もあるという御指摘ですので、そこのところは引き続ききちんと対応してまいりたいと思います。
以上です。

すみません、具体的にはどのようにされていきますでしょうか。

ただいまの再質問にお答えします。
事業者間では、先ほど言った連絡会等のところで情報の交換をします。御利用されている方には、別な事業所ではこんな取組もございますよというような案内をしっかりとやってまいりたいと思います。
以上です。

令和に、最近、こういった生活モデルに変えたということだったんですけれども、その後、やはりそういった御要望を多く聞くので、三鷹市としては、やはり親子の関係性をまずは考えていくというそこの認識もしっかりと保護者とつくっていく必要があると思うんですけれども。その上で療育支援だよということをしっかりと伝えていくような、このプログラムがあるからこのプログラムをしてということではなくて、私は療育支援を受けたいのに三鷹市はできないというようなそういう思いではなくて、そこに対してもその必要性をしっかり話していく必要があるかと思うんですが、いかがでしょうか。

ただいまの再質問にお答えします。
なかなか保護者の方と、どういった支援が必要なのかということで、ニーズと、私どもから見たこのアプローチの仕方が非常に有効的であろうというものがうまく合わないようなケースもございます。そこのところは丁寧に、一体どういう体系のプログラムがあるのかということを、全体像等もきちんとお示ししながらお選びいただけるように、きちんと情報提供をしてまいりたいと思います。
以上です。

よろしくお願いします。
保育園のほうからも、療育支援を受けたほうがいいんじゃないかというような、保護者に対してそういったことを聞いて、三鷹市のほうではそういった対応がたくさんあるけどないということで、やはり保護者自身が不安になってしまうというような事例もありますので、そちらはやはり三鷹市の方針を保育園や幼稚園にもしっかり伝えていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。

個々の具体的なケースが千差万別だと思いますので、生活モデルのやり方というのが、全てのケースにもちろん万能だということはあり得ない話なんで、どうしても医療的な視点から見ていくことも、ある意味重要になってくるというふうに思いますので、ただ、御家庭の方は、保護者の方はどっちにしろ不安ですよね。ですから、生活モデルのスタイル、私が見た範囲ですけれども、かなり時間のかかる話なんですよね。というか、時間をかけて見るというスタイルなので、1つの動作が、例えばお箸を持って御飯を食べるという動作が、あまり障がいのない子どもにとっては、当たり前ですけどすぐまねができることが、非常に習得するのに時間がかかる。それを焦って考えちゃうと、分かりやすく言えば医療的な問題になっちゃったりするのかもしれませんし、諦めるということになっちゃうかもしれない。そのところを丁寧に見るというのが生活モデルのスタイルなので、そこをしっかり理解してもらった上で、医療的に問題があるというのは当然最初からそうなんですけれども、そういう視点だけじゃなくて、生活の中でしっかり見守っていくみたいな、そういう視点が生活モデルのやり方にはある。それが一定程度効果が出てきているというのが、先ほど担当の部長からもお話したことです。
ただ、不安は不安で保護者の方はあるわけなんで、そこをやっぱり専門家の方も含めて、いろいろ協議をしていくことは大事だと思いますけれども、専門家の人が意見を言ったからすぐに万能で、そっちも万能で、すぐよくなるとかいうそういう話ではないはずなので、そこはしっかりと話合いをする場所を、そういう方が多いんであれば、実際にそういう場をつくっていくことは今後必要だと思いますので、現場ともよく検討、研究をしていきたいというふうに思います。

市長からありがとうございます。やはりなかなか生活モデルで全てがということではないとは思うんですけれども、やはり保護者の状況としては、発達診断や療育につながるためには、様々な不安や心配を抱えながら、現在は自力で施設や医療を調べて、ひたすら電話や面談を取り付けて、場合によっては半年以上かかってやっと機関につながるという切実な声も聞いております。保護者自身が必死に動かなければならない状況がありますので、そういったところにも丁寧に向き合っていただければありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、子育てステーションたかのこなんですが、やはり発達支援センターというのは本市のいろんな媒体ですとか、そういったものにも掲載してあったりするんですけれども、この子育てステーションという、子育てステーションという言い方をしている方がどこまでいるかも分からないんですけれども、子育て支援たかのこを、もっともっと気軽な相談ということで見せていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

利用者支援事業のたかのこについて、周知等についての再質問いただきましたので御答弁いたします。
御指摘のように、これまで三鷹市は様々な相談、どこが受けても必要なところにはきちんとたどり着けるようにというところで、全庁的な体制として受入れ窓口をつくってまいりましたけれども、逆にそのことで、特定の窓口がどこなのかというのが分かりにくいというような一面も確かにあるのかなと思います。そういう意味では、引き続き周知の仕方、全ての御家庭に届く形で、今、一度は情報提供が行っているはずなんですが、それでもなかなか分からないということですので、看板の掲げ方ですとか周知の仕方については引き続き研究をしてまいりたいと思います。
以上です。

よろしくお願いいたします。家庭支援センターのりぼんに貼ってある支援の体制の一覧のような図で見せていただけると一番分かりやすいかなと思いますので、そういったものもいろんな部署に置いていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
再質問を続けさせていただきます。質問3の再質問をいたします。子ども発達支援センターでどのような専門職を配置しているかという点で、先ほど答弁のほうで、専門職についても市のほうで配置していると聞いて安心したんですが、専門職への相談を希望する場合はどのような形でできるのでしょうか、お伺いします。
以前、コロナ禍だったかもしれないんですが、保護者の希望に柔軟に対応していただいた例でもあると思うんですけれども、電話等で相談できたとも聞きました。希望する場合には、今後このような電話でしたりオンライン等の対応もできるかと思いますが、御所見を伺います。

ただいまの再質問にお答えいたします。
相談は、私どもの支援センターのほうに御相談いただければ、その方の相談の中身に応じて専門職の者が対応するという形で御相談に乗らせていただいております。また、電話でももちろん対応させていただきますし、今お話があったようなオンラインでのお問合せも最近は増えています。また、私も何度か見ておりますけれども、お手紙で、メールとか、そういうような形で御相談というようなものにも、本当に短い期間でお答えをするように努めているところでございます。
以上です。

ありがとうございます。いろいろ対応していただいているとは思うんですが、1回で終わらず、必要があれば続けて対応していただけるような、そういった形も要望いたします。
先ほど市長の答弁にあったように、医療モデルと生活モデルで、現在生活モデルを重視しているということなんですが、このバランスですね、その辺についてもう一度よく検討していただけるとありがたいなと思います。こういった市の様々な支援で療養支援にたどりつけない場合に、保護者が専門的な支援を民間で行う場合には、全て有料になります。保護者自身の判断で療育支援を行っているんですが、やはり相当費用がかかってきているということを聞いております。そういった点からも、全ての方が安心できる体制づくりとして、こういった支援の充実をお願いしたいと思っております。
続きまして、質問4の相談窓口を知らない、相談していいのか分からないという件に関して、部長の答弁いただきました。本市では、網目を巡らせながら、気軽な相談につながり、きっかけをつくっていただいていると思います。妊娠期間中や新生児訪問、健診、親子ひろば等で助産師さんや保健師さんが、子どもの不安や悩みを聞いたり、必要な機関につなげていると理解しています。また、みたかきっずナビでも、アプリからの相談、あとは先輩ママからの助言、ペアレントメンター相談等も、本当に相談は様々実施されているかと思います。これは例えばなんですが、当事者にとっては、同じ思いを抱える当事者同士のつながりが一番の支えになると聞いています。そして、そういった当事者のつながりから相談してみようかなというふうにもつながると思いますが、気軽な相談につながる方法として、乳幼児を持つ、こういった発達に不安を抱える保護者同士の気軽な交流会のようなものがあるといいと思いますが、現在そのようなことはされていますでしょうか。

ただいまの再質問にお答えします。
今、御提案ありましたような交流会については、お子さんをお持ちの方ということでは、母子保健係のほうでも実施しておりますし、あるいはくるみ幼児園のように保護者の方の会というようなことで、交流会というものを設けているところでございます。
以上です。

ここも実施しているかと思うんですけど、やはりまだまだ気軽な相談というところで、私、こんなことに悩んでいたけれども、いろいろなプログラムを通して前向きに考えられるというようなことにおいては、まだまだそういった当事者同士のつながりというのはあってもいいのかなと思いますので、様々な形で当事者同士のつながりをつくれるような──すくすくひろばだって様々な分かりやすいところで実施していただけるといいなと思いますが、いかがでしょうか。

ただいまの再質問にお答えいたします。
今、御指摘ありましたように、親子ひろばみたいなところは本当に遊びに行くというような感じで寄って、本当に地域の方同士が交流して情報交換したり、悩み事を打ち明けたり、そこには助産師ですとか市の職員ですとかがいて、具体的な相談があれば、相談にも円滑にスムーズに、さりげない応答の中で対応させていただくことができるという、非常に効果のある事業だというふうに私どもも位置づけています。そういった様々な接点をできるだけ増やして、それもできるだけ敷居が高いというふうには思われないように、何気なく立ち寄っても相談ができるというようなところを増やしてまいりたいと思います。
以上です。

よろしくお願いいたします。
続きまして、質問でも触れたんですが、今の子育て世帯はまずネットから情報を収集します。現在のきっずナビでは、発達支援センターのパンフレットに記載があるような情報が一覧では見られないと思います。分かりやすい掲載が必要と考えますが、御所見を伺います。

ただいまの再質問にお答えします。
きっずナビと、それから子育てガイドという情報誌がございますけれども、こちらの内容が、全く同じような状態でないような部分も一部確かにございます。きっずナビについては、今年度も一部御利用の利便性が高まるように、実は改修の作業を今進めているところで、新年度には新しい画面で御覧いただくことができると思いますし、パンフレットの形の情報誌についても、今後ともその内容について、分かりやすい、あるいはカテゴリーの分け方が非常に活用しやすいというようなところをしっかり検討しながら改訂を加えてまいりたいと思います。
以上です。

改訂を進めているということなんですが、子育て、子どもの発達に悩んでいる方は、特に必死にお子さんの状況や支援をインターネットで調べますので、本市のきっずナビ、そのような当事者目線で考えると、窓口情報は分かるものの、具体的な情報にたどり着くのが難しい状況です。その辺を踏まえて、早急な情報発信の改善を要望いたしますので、引き続きよろしくお願いいたします。
続きまして、質問5、巡回発達相談について再質問させていただきます。先ほど御答弁にあったように、巡回指導はあくまでも地域で子どもを支える園に対して、お子様が園での生活をしやすくするために、日常の行動等を見て、園への助言や指導をすることですが、園に対し、また保護者に対しても、その巡回指導の目的はきちんと理解しているとお考えでしょうか、お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えします。
私どもとしては、毎年園のほうには、巡回発達相談はこういう趣旨ですと、今年も実施しますので、ぜひ御利用くださいということで、紙に書いたものもお渡ししつつ、口頭でも園長会等の場所にお邪魔して説明をさせていただくようになっていますので、大分御理解は少しずつ進んできているのかなというふうには思われますけれども、一方で、この巡回発達相談とは違って、今度は保護者の方が、御自身のお子さんの通われている保育園か幼稚園のほうに専門の職員の派遣を依頼をして、直接そこで発達支援の取組をしてもらうという制度があります。これは保育所等訪問支援事業と呼んでいます。どうもこの2つが誤解をされているという節もあって、本当に支援のために行っているときと、そうではなくて園のほうにアドバイスに行っているときで勘違いをされるケースはあるのかなというふうに思っておりますので、引き続きそこのところはきちんと周知を図ってまいりたいと思います。
以上です。

今、部長がおっしゃったとおり、園に対しての支援なのか、やはり保護者、子どもたちを見に行っているのかというところに、誤解といいますか、まだまだ認識の違いがあるような気がしていますので、その辺については、今もしていただいているとは思うんですが、特に保護者に対して不信感や不安につながらないように、案内のほうをお願いしたいと思っております。
また、先ほど巡回指導の増加に対しては、回数を超えた対応及び質の向上を目指しているということですので、引き続き、これも園側との事業に対して相互理解を深めるためにも、引き続きよろしくお願いいたします。
やはり園のほうが認定してもらいたいですとか、あくまでも子どもたちを地域で見守るために園に対して指導や補助をしているということが伝わり切らないと、いろいろな誤解につながってしまうと思いますので、ぜひその辺もよろしくお願いいたします。
続きまして、巡回指導については、具体的にレポートのようなもので報告しているのか、その後、個別のミーティング等をしているのか、どのように指導が行われているのでしょうか、お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えします。
これは1回当たり半日程度の時間をかけて行っておりますけれども、市のほうから職員あるいは専門の者がお邪魔をしまして、様子を見ながら、お子さんを預かる側の方にアドバイスをしていく形になります。どういった状態であったかというのは、当然帰ってきた段階でセンターのほうに報告がありますし、また、園のほうにも、こういう内容でという指導の確認等をさせていただいているところでございます。

巡回指導についても保育の指導についても、これはあくまでもやはり地域の子どもたちをみんなで支えていこうという取組ですので、その辺を引き続き、保護者に対して理解があるように、よろしくお願いいたします。
続きまして、質問6、特別支援を受け入れる幼稚園の補助についてですが、園としては、配慮が必要なお子さんの増加を受けて、ほかのお子さんと同様に、安全に安心した園生活を送っていただくためには、人材の確保が不可欠であると聞いております。そのような状況から、どこの保育園も人材不足、幼稚園も人材不足、これは大変深刻な問題ではあるんですが、園の定員に余裕があっても、配慮が必要なお子さんを断らざるを得ないと聞いております。そのような状況についてはどのようにお考えでしょうか、お伺いします。

ただいまの再質問にお答えいたします。
保育園、幼稚園問わず、一定の配慮が必要なお子さんというものは増えてきているというふうに認識しております。一説によると1割程度はというような御指摘もありますけれども、そういう状況がいずれの園でも見られます。そういう意味では、きちんと受入れの体制を取れる状態にしておきませんと、インクルーシブというような形でいろいろ進めてはおりますけれども、実際は受皿がなかなか対応できないというようなことも起きてまいりますので、今、御指摘のように、人材をいかに確保するかということは非常に大切なことだというふうに私どもも認識をしているところです。
そういう意味では、非常に大きな課題だなというふうに思っておりまして、例えば、国が定めている保育士とか幼稚園教諭の配置の基準というようなものも、ちょっと今、現実的にはこの基準難しいのかなと、見直しが必要な時期に来ているのではないかなというふうに考えますし、また、こういった人材を養成している機関、学校のほうでもやはり一定程度は、こうした子どもたちに対する対応のスキルというものを学ぶ、例えば実習の機会も設けるとかというような、一定の時間を今以上に確保していただいて、現場に出たときに即戦力となるような、そういうスキルを身につける、そういう教育体制を取っていただけると非常にありがたいかなというふうに思っているところでございます。

私も子どもたちのインクルージョンな体制を進めるためにも、やはり受皿の体制をどういうふうにつくっていくかということが一番重要だと思っていまして、配慮の必要な子どもを受け入れたいと思っている幼稚園に対して、例えば、保護者への丁寧な説明と理解を得た上で、園が対応しやすいような取組を進めていくべきと思いますが、例えば、幼稚園側に対して、巡回指導の観察で特別支援認定を受けられる等、認定要件の緩和などはできないのでしょうか、お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えします。
そういった御要望があって、私どもも本当に痛いほど、対応をどのようにすると加配の対象としての証明になるのかというところで苦慮しているところでございます。ただ、証明になる文書というものは一定程度の水準のものが求められておりまして、巡回発達相談のように、単発で行って、短い時間子どもを観察することで、言わば医師の診断に代わるような形で、このお子さんには確かに発達の課題がありますというような診断めいた判断を下すということは、非常に慎重にしなければいけないことだというふうに思っておりますので、今はそういったことはしていないところで、各園にはその辺の事情をよく御説明申し上げて、御理解を求めているところではございますが、ちょっと方法についてはいろいろ検討しているところでございます。

特別支援児という呼び名にまず抵抗があるとは感じるんですが、やはりそういった形で加配をつけられるような仕組みが増えていくことで、やはりインクルーシブな体制というのも整っていくと思いますし、現在、特別支援の認定を受けるには、保護者の同意及び専門機関の判定書が必要になります。認定を受けることは、園にとっても保護者にとっても安全で安心な環境の整備にもつながると考えます。現在、特別支援児の認定の申請書は、基本的に保護者自身が直接申請するようになりました。保護者が理解して、納得してという配慮も分かるんですが、手続的なことも含めて、保護者の負担についてはどのようにお考えでしょうか。

ただいまの再質問にお答えします。
今、御指摘いただいた部分も、できる限り私どもも保護者の皆さんの御負担がないように、できるだけ軽減する方法を考えているところではございますけれども、保護者の方の同意がないままに、例えば園側が一括して、この方とこの方について認定をするためにちょっと見に来ていただきたいというようなふうにしますと、全く内緒で、本人の同意もないままにこっそりと診断をしてしまうというようなことにも等しいような行動になってしまいますので、そこのところは厳に慎まなければいけないことだと思っています。そういった難しい課題をはらんでいる部分で、どうしても保護者の方にも一定の理解はしていただければならない部分があることは、私どもも非常に胸を痛めている部分ではございます。
以上です。

特別支援児の認定ですとか、やはり配慮を必要とする子どもたちということ自体が、やはりなかなか保護者に理解していただくということが大変難しい部分ではあると思うんですが、やはり地域で子どもたちを見守るという点と協力していく体制の上で受皿の確保というところでどのようにしていいのか、大変難しい問題だとは思うんですが、慎重に考えていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、現在、幼稚園は保育園並みの預かり保育の充実があります。預かり保育時も同様に、配慮を必要とするお子さんについて加配などを利用することがあると思いますが、この点について、園に対しての支援等は検討はされないでしょうか、お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えします。
本当に幼稚園、もともと短い時間のお預かりということから、保育園並みに預かり保育ということで、長い時間お預かりされるというような取組をされて、園児の確保等にも努めていらっしゃることもよく理解しております。そういう意味で、加配が必要というようなお子さんも、当然その中には増えてきていることも承知しております。先ほども御回答申し上げましたけれども、そもそもの国の配置の基準というものが、現実になかなか追いついていないというような状態があろうかと思います。そこのところがぜひぜひ見直しがされるように、働きかけをしていきたいなというふうに思います。

よろしくお願いいたします。
続きまして、質問7、くるみ幼児園についてお伺いしたいと思います。保育園入園前に、発達支援や医療ケアが必要なお子様に対しては、認定会議を経てケアプラス保育枠での入園が可能ですが、先ほどくるみ幼児園の認定には一定の条件があるということでしたが、ケアプラス保育とくるみ幼児園のこの認定の違いというのはどのようなものでしょうか、お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えします。
基本的には、少なくとも市立の保育園においては、集団生活になじむお子さんについては、きちんと発達の課題があるとか、あるいは医療的なケアが必要であるというお子さんであっても、きちんと受入れができるように体制を整えて受け入れさせていただいております。その際に、くるみ幼児園に通うのがいいのか、それとも一般の保育園に通うことがいいのかというのは、それぞれの環境の違い等も御説明させていただきながら、保護者の方に選んでいただいているというような状況でございます。
以上です。

やはりケアプラス保育とくるみ幼児園の違いというのもなかなか分かりづらいので、当事者にしっかり説明はしていただいているとは思うんですが、分かりやすい周知といいますか案内をよろしくお願いいたします。
続きまして、くるみ幼児園は基本的に14時までの保育ですが、その後、預かり保育として、一時保育にこにこを利用することが可能です。一時保育にこにこは本市独自の事業になるかと思いますが、利用については何か制限等あるのでしょうか。また、一時保育にこにこは、くるみ幼児園同様に、発達支援に配慮した保育を行っているかと思いますが、利用に関して、市内のほかの一時保育と同様の利用であります。公式に募集はされていないように思いますが、その理由は何かありますでしょうか、お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えいたします。
にこにこという一時預かりをセンターのほうで実施しておりますけれども、メインはくるみ幼児園に通っていらっしゃるお子様を2時以降預かるための体制として整えている制度です。ただ、御要望があれば、一般の方についても御利用はいただくことができますが、同じ建物の中でもう一つ、一時保育を別に一般の方向けに、これは丸々1日の時間で──2時以降ということでなくて実施しているものがございますので、基本的にはそちらを御案内させていただいているという状況でございます。

ありがとうございます。また、くるみ幼児園は、一時保育を利用しながら、15時まで利用できます。働く子育て世帯にとっても、15時まで利用できるんであればということで、入園に対して認定等があったとしても、このような施設があることを、当事者にだけでなく、分かりやすく広報する必要があると思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えします。
先ほど来、なかなか情報提供が必要な方に届いていないという御指摘を頂戴しているところでございますので、そこのところは引き続きしっかりと方法について検討してまいりたいと思います。

本市で発達支援やそういった成長に不安を抱えられているお子さんの相談後も、このようにくるみ幼児園や一時保育にこにこなどを利用して、そういった具体的な支援があるということを知らせることは安心にもつながると思いますので、ぜひ広報の御検討をよろしくお願いいたします。
また、幼稚園、保育園では特別支援児、配慮を必要とするお子様の受入れに努力していただいていますが、保護者の同意がある場合などは、くるみ幼児園、幼稚園、保育園等の連携も必要かと思いますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えします。
課題を抱えているお子様の中には、保育園、幼稚園のほうに入園されて、その保育園、幼稚園のほうから、なかなかほかのお子さんと一緒にお預かりすることが難しいというような御相談もあり、保護者の方の御同意、理解も得た上で、一旦くるみのほうに入園をしていただくと。これはお子さんによりますけれども、そこで非常にいい経過をたどって、元の幼稚園、保育園に戻ることのできるという方もいらっしゃいますし、あるいは最初からくるみのほうにおいでになっていて、この子はもう十分にくるみでない園であっても通うことができますねというお子さんがいれば、それはまた移行していただくというところの橋渡しもしているところでございます。

ありがとうございます。部長のおっしゃるとおり、地域の保育園、幼稚園とも連携しながら、くるみ幼児園の利用促進にもつなげていってほしいと思います。来年度、くるみ幼児園、定員数もかなり空いているというのも聞きましたので、幼稚園、保育園、なかなか配慮を必要とする子どもたちを受け入れるのが大変な状況もありますので、そういった定員の状況などを見て、相談体制にもしっかり対応していただければと思いますが、いかがでしょうか。

ただいまの再質問にお答えします。
くるみに通っている子、あるいはそうでない園に通っている子ども、分け隔てなく、また、発達の課題のあるなしにかかわらず、そのお子さんにとって最も豊かな保育や教育が受けられる、そういう環境であるように、これはうちの子、それはうちの子じゃないというような分け隔てはなく、全て三鷹市の中にいらっしゃるお子さんというくくりで、広い視野を持って連携をきちんと他の事業所とも取りながら、事業を進めてまいりたいというふうに思います。

分け隔てない子どもたちの受入れ、よろしくお願いいたします。
再質問最後になりますが、また、一時保育にこにこのように、一時保育においてもインクルージョンの観点から、今後、全ての市内の一時保育園が特別支援児、配慮が必要な子どもの受入れができるなどすればよいと考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。

ただいまの再質問にお答えします。
大きくは、やはりインクルージョンというような形での子どもたちの育ちを保障できればいいというふうに考えておりますので、保護者の方が選択する上で、ここでないと駄目というのではなく、ここも選べる、あそこも選べるというような形になることが望ましいというふうに思っていますが、先ほどの御指摘にもありましたけれども、人材の確保というようなところ、あるいは環境の整備というようなところで、なかなかそこまで至らないような状態のところも少なくはないわけです。そういった意味では、そういうところをきちんと一定のレベルまで引き上げていく、あるいはサポートさせていただくというのは、例えば、私どもでいいますと、専門性向上研修ですとかというようなところできちんと側面支援をしていって、いずれのところでも保育していただけるというような環境を整えていくことができるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
以上です。

ありがとうございます。長くなりましたが、本市の切れ目のない子育て支援の中でも、発達支援事業の詳細な部分は市側と当事者、関係者にしか分からず、見えにくい部分です。先ほど、医療モデルから生活モデルにしてまだ浅いとのことでしたが、私自身これまで10年以上の子育て支援活動をしてきている中でも、乳幼児の発達支援体制においては、市の支援を手厚くしてほしいとの声をたくさん聞いてまいりました。子どもの発達に悩まれる保護者から、療育支援やその後の就学を考えた場合、支援の手厚い自治体に引っ越すなどと聞くたびに、残念な気持ちになりました。大変センシティブな部分で、慎重かつ丁寧な対応が求められると思いますが、本市の網目を巡らせた相談体制を生かしながら、本市の掲げる切れ目のない子育て支援という発達支援の体制について、今回のお話が考えるきっかけになればありがたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。